「起立、礼」 「おはようございます」 「着席」 「みなさん、おはようございます。それでは出席をとります」 学級委員長の号令に従って、担任に挨拶する。若い女性教師だ。 それにしても、こんな風に挨拶するのって何年ぶりだろう。 くっ、くくっ 席に座って女性教師の顔を見ながら、自然と笑みがこぼれる。 「さやかちゃん、どうしたの? 何だか嬉しそう」 「え? なんでもない……よ」 小声で話しかけてきた隣の席のまどかに、そう答えながらも、また頬が緩んでくる。 昨日まで営業ノルマに追われていた俺が、こうして女子中学生やってるなんてな。 そう思うと、ついにやにやしてしまう。 机の下に目を落とすと、そこにはむきだしの太もも、そしてその根元を覆う短いスカート。 じっと見ていると、それまで感じる暇もなかった欲望を覚えてくる。 この太ももって俺の太ももなんだよな。だから触ってもいいよな。 左手を机の下にそっと下ろして太ももの上に乗せると、その感触を確かめる。 すべすべして、気持ちいい。 自分が本当に女の子になったことを手の平越しに実感できる。 スカートの裾に手が触れると、自分がスカートをはいていることを意識させられ、尚更興奮してしまう。 スカートの奥には、今の俺の体には、アレがついているんだよな。ちょっと触ってみようかな。 太ももに置いた掌を少しづつ脚の根元にずらしていく、スカートの中に指を潜り込ませる。 1本、2本 あと少し、もう少しで。 だが、指先が股間に達しようとしたその時、何か殺気のようなものを感じた。 ぞくっ 誰かに見られてる? 周囲を見回すと、ほとんどの生徒は教師のほうを見ている。 だが、窓際の席に座った長い黒髪の美少女だけが、冷たい視線を俺に向けて睨んでいた。 「あ……と……」 見られたかな。 気まずくなった俺は、視線を逸らすと、手を机の上に戻した。 彼女も、昨夜あそこにいた女の子の一人だよな。名前は確か…… 魔法少女さやか☆アキラ 第3話「それはちょっとうれしいなって」 作:toshi9 イラスト:SKNさん その後もちらちらと机の下を気にしながら午前の授業を受ける。 尤も、朝のホームルーム以降、いつも誰かに見られているような気がして、とても自分の体に興奮する余裕は無かった。 トイレの個室に入った時でさえそうだ。 あ〜あ、折角女の子になったのに。 そう思う一方で、授業の中身に驚かされていた。 何なんだ、この問題は。 英語も数学も、黒板に書かれる問題が全くわからない。文系だったとは言え、大卒の俺にわからない問題がぽんぽんと出てくるのだ。 今時の中学校のカリキュラムって進んでいるのか? それとも俺、頭も中学生並みに? 教師に指名されて黒板の前に立ったものの、回答できずにじっと固まっている俺に、クラスから笑いが漏れる。 「さやかさん、席に戻っていいわ。ちゃんと予習してくるのよ」 「は、はい」 「さやかちゃん、ドンマイ」 席に戻る俺を、まどかが隣から小声で励ましてくれた。 つ、疲れる。 休み時間になると、すぐにまどかとひとみが俺の席に寄ってくる。 「さやかちゃん、時々ぼ〜っとしているけど、大丈夫?」 「う、うん」 「次は体育だよ、早く着替えに行こう」 「た、体育……ね」 「全く、陸上なんて、いやですわ」 「ふふっ、ひとみちゃんって運動苦手だもんね」 「さやかちゃん、今日は得意の50m走もあるよ。ほむらちゃんとどっちが速いのか、競争だね」 「そ、そう……なの?」 「ほむらちゃんて、勉強もできるし、スポーツも何やっても凄いもんね。ほら、早く行こうよ」 俺は、まどかに押し出されるように教室を出て、更衣室に向かった。 勿論着替えるのは、他の女子と一緒だ。 更衣室の中に入ると、女子の匂いが溢れかえっている。 きゃあきゃあと着替えをしているその中に、俺はまどかの後について入った。 女の子の中で着替えか、うわぁ、中学生って言っても発育のいいのもいるじゃないか。 それとなく見回すと、小学生とあまり変わらない幼児体型の女の子もいるけど、大人顔負けのスタイルの子が何人もいる。 「お、あれなんかいいな、きゅっと腰がしまって」 一際目を引く均整の取れたスタイルの女の子がスカートのホックを外している。どれどれ、顔はっと。 げっ! それは長い黒髪のあの美少女……ほむらだった。 彼女は俺の視線に気づいて、脱いだ制服で上半身を隠すとキッと睨み返す。 「え、え〜と」 慌てて視線を逸らす。 「どうしたの? さやかちゃん」 「え? うん、ちょっと」 怪訝そうに俺を見るまどか。 「どうしたの? 暁美さん、早く行きましょう」 「え? ええ」 暁美ほむら、彼女は人気者なんだろう。まどかに何か言いたそうだったが、他の女子に引っ張られて行ってしまった。 「さやかちゃん、早く着替えようよ」 「え? うん、そうだね」 まどかに促されて、スポーツバッグから体操着を取り出す。 だが、紺色の布地を広げて、俺は絶句していた。 (ブ、ブルマー、今時ブルマーかよ。これを俺がはくのか!?) 「何してるの? さやかちゃん、授業始まっちゃうよ」 「え? うん」 ブルマーを両手で握り締めて固まっていた俺は、意を決すると、上着、リボン、そしてブラウス、スカートと脱いで下着だけになった。ぎこちない動作で服を脱ぐ俺を、まどかは不思議そうに見ている。 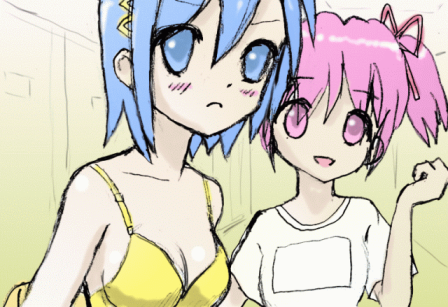 「さやか……ちゃん?」 「あ、ごめん」 広げたブルマーにゆっくりと脚を通して腰まで一気に引き上げると、小ぶりのお尻に布地がぴったりとフィットする。 股間にピタッと伸縮性のある生地が密着する。 名前とクラスが書かれた布が縫いこまれた白い上着を頭から被ると。両胸が上着を盛り上げた。 体操着に着替えた俺は、顔を真っ赤にしていた。 「さやかちゃん、顔赤いよ。やっぱり気分悪いの? 保健室に連れていこうか?」 「え? ううん、大丈夫だから」 俺は、恐る恐る更衣室を出た。 体育の授業が始まると、50m走、走り幅跳び、走り高跳びのグループに分かれて、それぞれの記録を記録係がチェックしていく。 その中で一際目立っていたのは、長い黒髪の美少女、ほむらだった。 今もあざやかな背面跳びで走り高跳びをこなしている。 飛び終えてマットから起き上がった彼女を、クラスの数人の女子がきゃあきゃあ言って迎えている。 ほんとに人気あるんだ。 「ほむらちゃん、今日もすごいな」 俺と同じグループになったまどかは、彼女を見ながらそうつぶやいた。 「彼女って、いったい何者なんだ?」 「え? さやかちゃん、何て?」 「い、いや、何でもないよ」 その時、ほむらが俺たちのほうを向いた。そしてまたも目が合う。 彼女の目は、まどかの傍らにいる俺のことを非難しているかのように見えた。 「じゃあ、あた、あたし、は、ここで」 ようやく1日が終わり、登校した時と同じようにまどかとひとみの二人と一緒に帰る。 だが、俺には行ってみたいところがあった。 二人と別れてそこに向かおうと切り出したのだが、女言葉はどうにも恥ずかしい。 本当にずっとこのままだったら、女言葉を使うのにも慣れるしかないんだよな。 そう思いながら、意識してしゃべるようにしているが、女の子そのものの声を自分が出しているということもあって、やはり恥ずかしい。 「さやかちゃん今日も上条君のお見舞い? 彼の手って動くようになったんでしょう?」 まどかが、このこのって感じで俺をこづく。 え? 上条って誰だっけ? とくん そう思った瞬間胸の奥が鳴り、きゅんと締めつめられるような感覚を覚える。 え? なに? 「さやかさん、上条君のことですけれど」 内心戸惑う俺に、ひとみが言いにくそうな感じで話す。 「え? 何か?」 「一度あなたに相談したいことがあるんですの」 「相談って?」 とくん、とくん 胸の中で心臓がとくとく鳴り続けている。 「あ、今すぐじゃなくって、また今度で構いませんので」 「そお? え〜っと、今日は、その上条君のところじゃなくって別な用事だから」 「そうなんですね。それではあたくしもここで」 どこかほっとした様子でひとみが別れる。 「じゃあさやかちゃん、またね」 「うん」 まどかとも別れて、俺は一人駅に向かった。 それにしても、さっきの動悸は何だったんだ。 それはいつの間にかすっかり治まっていた。 二人と別れた俺は電車に乗ると、さやかの家ではなく、元の自分のマンションに向かった。 実は、自分の体が気になっていたのだ。 今、俺は女子中学生になってここにいる訳だが、元の俺はどうなっているんだろうか。 ふとそれが気になると、確かめずにはおられなかったのだ。 「ん? 何か騒がしいな」 マンションの前にたどり着くと、エントランスには非常灯を回した救急車が止まっていた。 そしてマンション中から一人の女性が出てくる。彼女はハンカチで目を押さえ、泣いていた。 (か、母さん!) 「あ、あの、この救急車、どうしたんですか?」 俺は、恐る恐る母さんに声をかけた。 「息子が意識不明の重体で……いいえ、まだ助かるかもしれない」 「ええ!?」 「仕事で無理していたのかしら。管理人さんから連絡があって、心臓発作を起こしたらしいって。あ、ごめんなさい、こんなことを見ず知らずのお嬢さんに」 「い、いえ」 母さんが救急車に乗り込むと、救急車は非常灯を回しながら走り去っていった。 俺は、遠ざかる救急車をただ見ているしかなかった。 俺はここにいるんだ、母さん。 両目から涙がぽたぽたとこぼれてくる。 「何てことだ、こんなことって」 仕事のつらさから逃げ出したい為に、安易に女の子になることを願ったことを、俺は今更のように後悔していた。 よく考えると当然のことだ。さやかという少女として生きるということは、元の体と今までの俺の人生の全てを失うということだ。 両親や友人に、もう二度と今までの俺として会うことができないのだ。 それを考えると涙が後から後からあふれ出てくる。 「俺って……ばかだ」 “そう、君はばかだ。駄目な人間さ” 「そうだな、何でこんなことを願ったんだろう」 “そうだね。もう生きていても仕方ないよね” 「そう……かもな」 “死ぬしかないよね” 「もう死ぬしか……ないのかな」 “死ぬのって気持ちいいんだよ、ねえ、早く死のうよ” 「うん。……って、待て、さっきから誰だ、な、何を言って」 ぼーっとしながら歩いているうちに、いつの間にか風景は一変していた。まるで絵画の中に入ったかのような光景が俺の前に広がっている。 「なんだ、これ!?」 『魔女の結界だ。君は引き込まれたんだ。変身して、さやか』 「へ!? 変身? QBなのか?」 『さやか、忘れないで、君は魔法少女なんだ。魔女を狩るチャンスじゃないか。結界の主を退治すればグリーフシードを手にすることができる』 「グリーフシード? おいQB、お前まだ何か隠しているだろう」 『話は後だ、それより早く変身した自分の姿を思い浮かべるんだ。大丈夫、魔法少女の君がどういう姿になのかすぐにイメージできるはずだよ』 「イメージって、そう言えば」 ある姿を思い浮かべた瞬間、俺の着ていた制服は全く別の衣装に一変していた。 胸とウエストだけを覆ったトップレスの青いキャミソールとミニスカート、そして肩に巻かれたマント。 手にはサーベルが握られている。 『君は《変換の祈り》を契約の証にして魔法少女になったんだ。攻撃力は杏子やマミにも負けやしないはずだよ。剣にはその力が秘められている。やってごらん』 「やってごらんって、そんな簡単に」 焦る俺の周りを、奇妙な風景の中からぞろぞろと現れた道化とも人形ともつかない怪しげな集団が取り囲もうとする。 「で、でやぁ〜」 俺は、意を決して異形の集団に向かって剣を振るう。 だが、何度やっても巧みに避けられて、うまくヒットしない。 「く、くそう、はぁはぁ」 そのうち完全に包囲された俺は、集団の向こうから伸びてきた長い触手に絡み取られてしまった。 触手に縛り上げられた両腕は、毒蛾に刺されたように、みみず腫れになっていた。 慣れない剣を振り回しているうちに瓦礫にぶつけた脚には、あちこち傷ができ、血が流れ出している。 命がけだった。 何とか逃げようともがいても、俺の体にぐるぐると巻きついた触手はびくともしない。ぎりぎりと、もの凄い力で締め付けられて、意識が朦朧としてくる。 そして、喉元に鋭いトゲのついた触手が突きつけられた。 狙いをつけたように一瞬止まったその触手が、ひゅっと動き出す。 や、殺られる! 殺気を感じた俺は、そう思って一瞬目をつぶった。 だが次の瞬間、取り囲んだ集団を切り裂くように俺の前に赤い影が現れた。 「あ〜あ、見ちゃいられないな」 そして瞬く間に周囲の異形を手に持った長槍でなぎ払っていた。 槍が一振りされる度に、異形は次々に消えていく。 「もう少し真剣に戦ったらどうなんだ。お前、全く成長しないな」 「き、君は!?」  それは昨夜あの現場にいた少女たちの一人、ブルゾンとショートパンツを着ていた女の子だった。 今は赤い衣装に身を包んでいる。 『杏子、見てたのかい?』 「QB、この獲物はあたしがもらうよ」 『まあ僕にとっては、どっちでも構わないけどね』 「上等!」 彼女は持っている長槍をぐるぐると振り回すと、瞬く間に俺の周りに群れる異形たちを消し去ってしまった。 その向こうには、そこには巨大な芋虫のようなものが横たわっている。そしてこっちに巨大なイソギンチャクのような髭のついた口を向けていた。 「覚悟しな!」 杏子はそう言って一気にジャンプすると、その頭部にぐさりと槍の刃先を突き立てた。 「グゲェ〜」 絶叫とともに塵となって消える、巨大芋虫。 そして、周囲がいつもの町の風景に戻る。 「お前なぁ、何の為に魔法少女になったんだ。もうちったぁ腕を上げろよ。まっ、これはもらっていくぜ」 杏子は、芋虫の消えた後に転がっていた黒い宝石を拾うと、ジャンプして飛び去っていった。 「え、えーっと」 『初心者の君にはまだ荷が重かったかもしれないね。でもすぐに慣れるよ。がんばってね、さやか』 「慣れるって、下手したらその前に死ぬじゃないか」 『大丈夫、君ならできるさ』 「な、何の根拠があって」 その場にへたり込んだ俺は、しばらくの間、動くことができなかった。 (続く) |