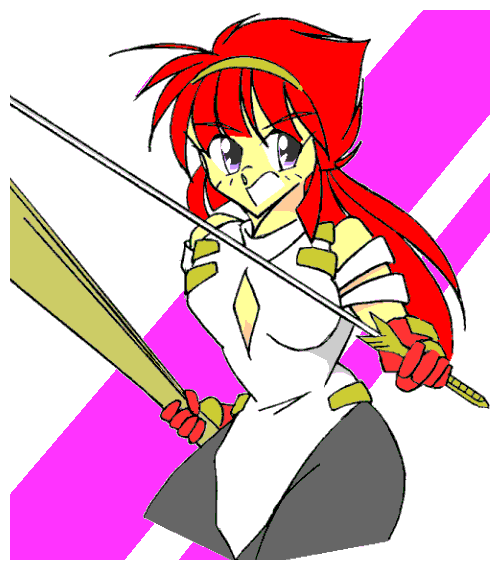
怪人たちを後ろに引かせ、蜜樹たちの前に出るDr.シマムラ。
その姿がゆらりと揺れ、新たな輪郭を描き始める。
それはかつて見たことのある姿。
「……え? どうして?」
(そ、そんな……嘘でしょう!?)
冷酷な目をしたその姿を、蜜樹は驚きの目で見つめ、彼女の中のハニィも息を呑んで絶句した。
「……あなたの息を止めてあげるわ、スウィートハニィ」
彼女たちの前に立っているのは、パンツァーレディだった。
戦え! スウィートハニィⅡ
最終話「大団円」
作:toshi9
「奈津樹姉さん? いいえ、そんな筈はない……姉さんはあたしのことを励まして、送り出してくれたんだから」
そう思いながらも、目の前に立つパンツァーレディそっくりの姿に変身したDr.シマムラの姿に動揺を隠せない蜜樹。
「そ、そうか、あたしを混乱させる為にそんな姿に……この卑怯者!」
「卑怯者? ふふん、何を言っているの? あたしを封印したあなたがそんなに狼狽するなんてね」
ふふんと笑うDr.シマムラ。だがその目は全く笑っていない。
(先生、違います、こいつは奈津樹姉さんじゃない。彼女がオリジナルのパンツァーレディ……いいえ……彼女はそんな名前じゃなかった)
「?? どういうことだ、ハニィ」
(私……全てを思い出しました、あいつのこと。そして私自身のこと……)
ハニィの声は段々小さくなって、最後まで聞き取れない。
「私自身? ハニィ、何が言いたいんだ!?」
心の中で問う蜜樹。
そんな彼女の様子に、くくくと笑うパンツァーレディ。
「どうしたの? そんな様であたしを倒せるのかしら?」
「くっ、貴様は誰なんだ」
「この女の体は借りていたに過ぎない。あたしの名前はアフロディア。こう言ってもまだ思い出せないのかしら? アルテミス」
「アフロディア? アルテミス?」
「そうよ、このあたしを封印したのはあなたなのに……その様子だとすっかり忘れているようね」
「どういうこと?」
「どういうこと? やれやれだわ」
どうしようもないといった様子で首を振り、両手を広げるアフロディア。
「ハニィ、教えてくれ。何がどうなっているんだ?」
(彼女の名前はアフロディア……遥かな昔、一国を滅亡の寸前まで追い込んだ魔女。そして、あたしの姉でした)
「姉? 彼女は奈津樹姉さんじゃないんだろう?」
(はい。でもあたしの姉だったんです。そう、あたしの名前はアルテミス……生田蜜樹じゃありません)
「な、なんだって!?」
ハニィが死んだ本物の生田蜜樹じゃない? どういうことだ??
混乱する蜜樹の頭の中に、ハニィの声が響く。
(お話しします。あたしが思い出した遠い遠い過去の物語を──)
遥かな昔、砂漠の中に緑豊かな国がありました。周囲を砂漠に囲まれていることもあって外敵が来ることもなく、水が豊富なオアシスを中心にした国は豊かで、人々は慈悲深い王様を中心に平和に暮らしていました。
でもある日、町の郊外で大きな火柱が立ってから、全てが変わってしまいました。
王様に様子を見てくるように命じられた兵士たちは、火柱の跡からグロテスクな魔像を持ち帰ってきました。
王様はその魔像を宝物庫に入れるように命じましたけど、王様付きの巫女だったあたしと姉は、その魔像がただの像ではないことに気がついたんです。
ただの彫り物のように見えたけれど、実はその中に禍々しい「意志」が宿っていることに。
ですが、その像を処分しましょう──と進言したあたしたちの言葉は、聞き届けられませんでした。
だから、あたしたち姉妹は独断で魔像を封印しようとしたんです。
でも逆に一瞬の隙をつかれた姉は、魔像に中にいた「意志」に全てを乗っ取られてしまいました。
外見は美しい姉のまま、でも中身は魔像の中に潜んでいた魔物に。
禍々しさの失せた魔像を見て、封印が成功したと思い込んだあたしは、最初は姉の身にまさかそんなことが起きているなんて気がつきませんでした。
でもそれからの姉はやりたい放題。姉とは思えない行動が目立つようになったんです。
そして段々と姉のまわりには、異形のモノが増えていきました……
異形のモノたちは、元々は決して悪いモノばかりじゃありませんでした。
中には人間を襲うようなモノもいましたけれど、多くは闇に潜み、生活圏を人間たちと棲み分け、人との共生を望むモノたちでした。
そして人間と彼らの間に入り、その関係を良好に取り持ってきたのが、巫女であるあたしたち姉妹の役目だったんです。
でもそんなある日、異形のモノたちは一斉に人間に襲い掛かってきました。
人々は恐れおののきました。
全ては姉アフロディアの姿をした魔物の仕業でした。姉の姿も巫女の力も全てを自分のものにした魔物は、姉の巫女の力を利用して、陰で異形のモノたちを操っていたんです。
そんな真相を知らなかったあたしたちの目の前で、彼女は暴虐の限りを尽くす異形のモノたちの前で祈りを捧げました。
たちまち異形のモノたちは全て町から姿を消しました。
人々は狂喜しました。でもそれは策略だったんです。
騒ぎが収まると、王様をはじめ町のほとんどの人間は姉を崇め、ひれ伏すようになってしまいました。さすが選ばれし巫女アフロディアだと。
あたしもその時、姉の力に感動していました。
だけど平和を取り戻した町では、熱にうなされたように宴が延々と続きました。それは日に日に過熱し、段々と人々の心は荒み、いつしか町も荒廃していきました。
そしてその間に、少しづつ姉の魔力に意志を奪われ、隷属する人間が増えていきました。
姉を乗っ取った魔物の望みは、町の破滅と人間の滅亡でした。異形のモノたちが再び町に現れ、彼女に操られた人間の集団と一緒に、正常なままの人間たちに襲い掛かり、そして逆らう人間は、次々に魔物に改造されていったんです。
昨日までの仲の良かった家族や友人が、次の日には殺し合う……本当の地獄でした。
姉の異変に全てを悟ったあたしは、姉を乗っ取った魔物を封印する為に対決しました。
それは悲しい戦いでした。姉との完全な融合を果たした魔物は、もはや魔物でも姉でもある存在になっていました。
あたしが対決したのは、そんな相手でした。
指輪と髪飾りが発掘された後、どうして生田家と桜塚家に分けて保管されることになったのか私にはわかりません。生田博士が封印の聖具を守る為に行なった措置なのかもしれません。
ですがいずれにしても、それぞれの聖具を奇しくも両家の娘である、生田蜜樹と桜塚マリアが手にすることになりました。
ひとつだけでも大きな力を秘めた聖具は、二人に大きな力をもたらしました。
でも、巫女の印としての本来の力が発揮されるのは、一人の女性が両方の聖具を手にした時──その時こそ、災いをもたらすものに対して、強烈な封印の力を発動させることができるんです。
そして、今、その二つを先生が身につけている……
あたしが再び目覚めたのは、生田蜜樹が指輪を嵌めた瞬間です。
どうして遠い国の少女が巫女の指輪を嵌めているのか……いいえ、それ以前に何が起きているのかさえも、あたしにはわかりませんでした。
長い眠りの中であたし自身の記憶がほとんど失われていたのです。
でも、シスターを倒して家族を救い出したいという彼女の強い意志に、指輪の持つ巫女の力とあたしの力が呼応し、全てを生み出す指輪の力とあたし自身の巫女の力が、彼女──かつての生田蜜樹に与えられたんです。
その力で、彼女は自分の理想の姿だった「スウィートハニィ」に変身し、シスターと全力で戦ったのです。
あたしは自分が何者かを思い出せないまま、いつしか「生田蜜樹」の意識と同化していきました。皆を助けたいというその真摯な願いに、強く共感したのかもしれなません。
でも彼女は、シスターによって改造された姉の手にかかって死んでしまいました。
あたしとよく似た境遇の少女の死に、あたしは指輪の中で泣きました。
そして、あたしは再び指輪の中で眠りにつくことになったんです。
彼女の願いであり、あたしの祈りでもある、「生田蜜樹」の意志を受け継いでくれる人間が現れるのを待ちながら──
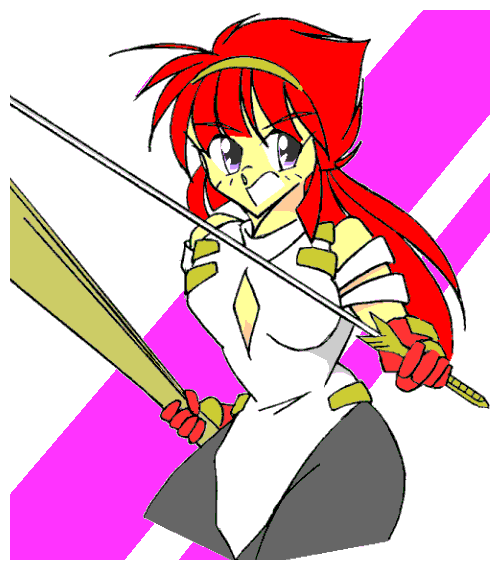
「許さない? だったらどうしようって言うの?」
空に差し上げたアフロディアの両手の間がバチバチと閃光を放つと、そこに光の剣が生まれる。
「あなたこそ覚悟するのよアルテミス。よくも私の邪魔し続けてくれたわね……」
アフロディアは手にした光の剣を投げつけた。
蜜樹はそれをぎりぎりで避ける。
ドゴン──!!
壁にぶつかった光の剣が教室の壁を吹っ飛ばし、巨大な穴を開けた。
「ふふふ、うまく避けたわね。でもこれはどお?」
次々に光の剣を放つアフロディア。
蜜樹もシャドウマリアも、そしてレディ・ティーゲルも避けるのが精一杯だった。
「ほらほらほら、さっきまでの元気はどうしたの?」
「くそう、反撃する隙がない」
「ハニィ、あきらめないでだニャ」
「このままでは埒が明かん。わたしが盾になる、ハニィ、後ろに続け」
「え? でもそれではあなたが」
「この鎧は伊達じゃない。あの光の剣の威力は大体見切った。数発なら耐えられる筈だ。一気に奴との間を詰める」
レディ・ティーゲルはそう言うと、着ていた甲冑をポンと叩く。
「確かなんだな?」
「こんな時に嘘をついてどうなる。お前に奴を倒してもらわない事には、たとえ生き残っても我らの眷属全てが、いつまでも奴に支配されるしかないからな」
「でもレディ・ティーゲル、あいつのスピードを上回ることができるのか?」
「そうだですニャ! ジェットストリーム・アタックをかけるんだですニャ!!」
突然、シャドウマリアが提案する。
「は? なんだそれ?」
「あたしがレディ・ティーゲルの後ろにつく。ハニィはさらにその後ろに、あたしの後ろにつくんだですニャ。あたしが右に飛び出すから、ハニィは0.05秒後にジャンプしてあいつに一撃を加えるんだですニャ」
「時間差攻撃ね。でもそれってマリアちゃん、いやシャドウガール、ええっと……」
「ふふっ、シャドウマリアでいいんだですニャ」
「うん、それってシャドウマリアを囮にするってことじゃない!? レディ・ティーゲルを盾にした上に、そんな危険なこと──」
「もう十分危険な状態だし、あたしは大丈夫なんだですニャ!」
「ハニィ、ぐずぐずしている時間はない。彼女の作戦で行こう。その代わり──」
「その代わり?」
「一撃で仕留めるんだ。二撃目はないと思え」
「わかった。必ず」
「よし、決まった。奴を油断させる」
そう言うと、レディ・ティーゲルは手に持ったサーベルを投げ捨てた。
「……あらあら、万策尽きたようね。死を選ぶしかなくなったの? それじゃ遠慮なく殺してあげる。その後であなたたち三人とも改造怪人にしてあげるわ」
「むざむざ殺られやしないさ……覚悟!!」
アフロディアに向かって真一文字に駆けるレディ・ティーゲル。
後に続くシャドウ・マリア、そして一瞬躊躇したものの、蜜樹もその後ろについて駆け出す。
三人は一本の線となってアフロディアに迫った。
「ふふん、目くらましを──」
バチバチ輝きを放つ光の剣を両手で差し上げ、アフロディアはそれをレディ・ティーゲルに向けて投げ放つ。
ドゴン──!!
光の剣が、レディ・ティーゲルの胸に直撃する。
「……くっ、なんの」
しかしレディ・ティーゲルは怯むことなく、一直線に突き進む。
「殺されるしかないのに何を考えているの? ほらほら、避けてみたらどおなの?」
二発、三発と光の剣を放つアフロディア。それを全て体の正面で受け止めるレディ・ティーゲル。
ドガッ──! ドガガッ──!! 「……ゲホッ! いけ、二人とも。頼む……ぞ」
口中から血をツツッと滴らせ、アフロディアの足元に倒れ込むレディ・ティーゲル。
その瞬間、シャドウマリアが右にすっと動いた。
「ふん、所詮目くらまし……死になさい!!」
両手を差し上げ、シャドウマリアに向かって四発目の光の剣を繰り出そうとするアフロディア。
だがその一瞬の隙をつき、レディ・ティーゲルの肩を踏み台にして、蜜樹がそこへ向かって一気に跳んだ!!
「なっ、仲間を踏み台にするだと!?」
アフロディアはシャドウマリアに向けた光の剣をあわてて構え直す。だが、
「輝けっ、プラチナフルーレ!!」
蜜樹の手にしたプラチナフルーレが、一気に輝きを増す。
「行っけぇ!! 奥義っ、桜・華・天・昇ぉ──っ!!」
閃光に、アフロディアの動きが一瞬止まる。
同時に輝く剣先が、その胸元を袈裟斬りにした。
グハッ──!!
その瞬間、アフロディアの手から光の剣がかき消えた。
「く……くそう、こんな、こんなことで殺られは──」
だが、よろめくその体を、幽鬼のごとくゆらりと立ち上がったレディ・ティーゲルが背後から羽交い絞めにし、両腕でがっちりと首を固める。
「は、放せっ!」
「いやだ……ね。長い間好き勝手にしてきたのだろうが、これで最後だ」
「や、やめ……」
レディ・ティーゲルの着ている甲冑に、アフロディアの体がぴたりと密着する。
「くっ、や、やめろぉ」
「ハニィ、今だ、やれっ!」
「ど、どうすれば──」
(先生、剣とハリセンを交差させて。あいつをレディ・ティーゲルの甲冑に封印しますっ)
「わかった!」
蜜樹は右手の剣と左手のハリセンを交差させた。
(さあ、あたしと一緒に唱えてください)
蜜樹の心の中で唱えられる呪文、それに合わせて蜜樹も口ずさんだ。
「(汝、とこしえの眠りにつかん──)」
呪文とともに、交差した剣とハリセンが光輝く。
そしてその光がアフロディアとレディ・ティーゲルを包み込んでいく……
「や、やめて……もっと楽しみたい…………もっともっと、迎えが……まで……もっと──」
必死で光から逃れようとするアフロディア。
だが、蜜樹は渾身の祈りを光に込めた。
「(輝け! ……そして包み込め!)」
光はどんどん膨らんでいき、部屋を覆い尽くした。
それとともに、蜜樹の指輪にピキピキと小さなヒビがいくつも入りだす。
だが、それに気づくことなく、彼女は祈り続けた。そして──
「(いっけえええええええええっ!!)」
気合いをふり絞る。一気に膨れ上がった輝きの中に包み込まれるアフロディアとレディ・ティーゲルの体。
そしてその光が消滅した時、そこにはレディ・ティーゲルだけが残されていた。
「あ、あいつはどこだですニャ?」
「レディ・ティーゲルの甲冑の中に封印した……レディ・テーゲル、あなたの体は大丈夫?」
「ああ問題ない。むしろ暖かい光に傷が癒された」
「良かった。それじゃ、早くそれを脱いで」
「承知した」
蜜樹に促されて、レディ・ティーゲルは纏っていた甲冑の留め具をすばやく外していく。
「これを人目につかないところに隠して、封印が二度と解かれないようにしないと──」
「だが、こんな目立つものをどこに隠す?」
「だですニャ」
足元に脱ぎ捨てられた甲冑を見下ろし、三人が途方に暮れていると、
「そういうことは私に任せろ」
「お、親父?」
ぴたりと動きを止めてしまった生き残りの怪人たちを掻き分けて現れたのは、マリアの父親桜塚教授と、蜜樹の父生田賢造だった。
アフロディアが封印されたことで、旧校舎に張られていた結界が消えたのだろう。
「お父さん!」
「蜜樹、無事か!?」
「はい! お父さんこそ。……あの、謙二君と幸は?」
「二人とも宝田君に病院に連れて行ってもらったよ、心配するな」
「そう、良かった……」
「おい親父、『任せろ』って、なんか心当たりでもあるのかだですニャ?」
シャドウマリアが訝しげに桜塚教授を見る。
「なあに、封印を破ろうとする人間が侵入できない場所なら、いくらでも心当たりがあるぞ」
桜塚教授はそう言って、男臭い笑いを浮かべた。
「よろしくお願いします」
「まかせておけ、蜜樹ちゃん。それにしてもマリア、お前ますますややこしい話し方になったな」
ぺこりとお辞儀する蜜樹と、その横に立つシャドウマリアを見ながら、桜塚教授が言った。
「余計なお世話なんだですニャ」
「まあそれはともかく、その衣装はなかなかよいぞ。父の前では常にそういう格好でいてもらいたいものだ、なあ賢造」
「う、うむ、……こほん」
「…………」
思わず同意したものの、蜜樹がじとっと睨むのを見て、慌てて咳払いする賢造だった。
「それにしても美少女二人の見事な構図だな、これは何としても記念に」
並んで立っているシャドウマリアと蜜樹に向けて、桜塚教授はおもむろにニコンF2を構えた。
どかっ──! 「こ、こ、こんなところで何写真撮ってるかだですニャ!! この変態親父!!」
「ま、まあまあ……」
父親をどつき倒し、さらにがしがしと足蹴りをくらわせるシャドウマリア。
あわててそれをなだめる蜜樹。
だが、
「──あ!」
その時、マリアの腕を押さえようとした蜜樹の指から、ばらばらと何かが落ちた。
それとともにスーパーハニィの変身が解け、通常の赤いバトルスーツ姿に戻ってしまう。
「え……?」
床に落ちたもの、それは粉々に砕けた指輪の残骸だった。
(先生、指輪が──)
「ああ、結局また砕けちまったな、それもこんな粉々に。これじゃもう修復は……」
落胆する蜜樹。だがその肩を桜塚教授がポンポンと叩く。
「心配するな蜜樹ちゃん。時間はかかるかもしれんが、私がもう一度修復してやる」
「できるんですか?」
「大丈夫、この私を信じるんだ」
一転真顔で話す桜塚教授。
「は、はあ」
「龍一郎、頼んだぞ」
「まかせとけ。……なあに、もう戦いに使われることはないんだろう? 時間さえもらえるならば必ず直してやる。砂漠の発掘品をいくらでも修復してきたこの腕は伊達じゃないぞ」
「よろしくお願いします」
「蜜樹、確かに終ったんだな」
「はい、帰ったら詳しく話しますけど、もう二度と『虎の爪』が復活することはないでしょう」
「恭四郎は?」
「そこに……」
全てが終わった中、未だ虚ろな笑顔でふらふらと踊り続ける少女を、蜜樹は指差した。
「これが、この少女が恭四郎なのか?」
「はい。委員長の……相澤くんの妹の未久ちゃんの姿をコピーしてシスター・ミクを名乗り、再び『虎の爪』を活動させようとしていたんです。でも影で支えていたアフロディアに愛想をつかされた挙句、キノコ怪人の毒を無理やり食べさせられておかしくなってしまいました」
「ふむ……いろいろ複雑な事情がありそうだな」
「はい。それはまたゆっくりとお話します」
「とにかく、今となっては最早、身寄りのない記憶喪失の少女というわけか」
そう言って少女──かつてのシスター・ミクを抱き止めた賢造は、その腕に注射を打った。
彼女は途端に、ぐったりと意識を失う。
「鎮静剤だ。何かの役に立つかもと思って持ってきたのだが」
「もう自分が誰だったかさえも覚えていないでしょう。このままどこかの施設に預けて、普通の少女として更正させたほうが彼にとって幸せかもしれないですね」
「それが良いかもしれんな。心当たりに打診してみるとするか」
そう言って、賢造はシスター・ミクだった少女を両手に抱え直した。
「お願いします、お父さん」
一方、シャドウシスターズはマリアから抜け出ると、シャドウレディとシャドウガールの姿に戻った。
ネコ耳と尻尾が引っ込み、マリアも元の姫高制服姿に戻る。
「三人とも危険な目に遭わせてごめんね。でもありがとう」
「今更何を言うんだです。あたしとハニィは親友なんだですから──」
「それはあたしの台詞だニャ。あたしがハニィの一番の親友なんだニャ!」
「まだ言うかですっ!!」
「ちょ、ちょっと」
「やめんか、二人とも!」
「「……はい」」
シャドウレディに一喝されて、マリアとシャドウガールは揃って身を縮めてしまう。
「マリアちゃん、これ」
蜜樹は髪飾りを外すと、マリアの髪につけた。
「あ、でもこれは」
「この髪飾りはマリアちゃんのものよ。これからもずっと大事にしてね」
「も、勿論だです」
頭につけられた髪飾りを、マリアは大事そうに撫でた。
それを黙って見ていたシャドウレディは、蜜樹に向き直った。
「スウィートハニィ、いろいろ世話になったな。生き残った怪人たちは、私とレディ・ティーゲルで連れて行くとしよう」
一方、がっちりと生田賢造と握手する桜塚教授。
「賢造、今日は楽しみにしているぞ」
「うむ。で、指輪の修復はどうだ?」
「まだまだだ。気長に待ってくれ」
「期待しているぞ」
さらに遅れて、姫高のクラスメイトたちが現れた。
「おーい、遅れてごめん」
「あ、みんな遅いんだです~」
「絶対間に合わせるつもりだったのに撮影が伸びちゃって。何てお詫びしたらいいのか……ごめんなさい」
「えへへ、許してねっ」
「オソクナリマシタ」
マリアが頬を膨らませ、コタローを先頭に、ルミナ、サラ、レンといった姫高のクラスメイトたちがぞろぞろと庭に入ってきた。
「あれ? マッチは?」
「一緒じゃなかったけど……あ、来た来た」
「遅刻遅刻、ごめ~ん。こんなイベントだもんね、今日はたっぷり取材しようと思って準備していたら遅くなっちゃって」
最後に庭に飛び込んできたのは、マッチだった。
「もお、今日は新聞部の仕事は抜きにするんだです」
「まあまあ、ちょっとだけ。ねえ、いいでしょ? ハニィ」
「うん。でもマッチも楽しんでいってね」
「わかっているわよ、うわぁ、おいしそう」
「みんな、そろそろお肉が焼けるわよ」
奈津樹と幸枝が集まった皆に声をかける。
「ひゃっほー、もうお腹ぺこぺこなんだ」
コタローがバーベキュー台に寄っていく。
「こら、がっつかない。全く、男子ってこれだから……」
サラがそう言って笑う。
パーティは賑やかに始まり、いろんなメンバーが交じり合ってわいわいと話し合っている。
大いに盛り上がるその光景に、マリアと話をしながら、蜜樹は自分の中のハニィと語っていた。
「こんな平和なパーティができるなんて思わなかったよ」
(はい先生。でも素晴らしいです)
「え?」
(先生を絆にして、こんなにいろんな人たちが集まっているんですよ。いいえ、人だけじゃなく、シャドウガールも一緒になって、あんなに楽しそうに。あたし……なんだか嬉しい……)
「そうだな。いろいろあったけど、ほんとに良かったよ……」
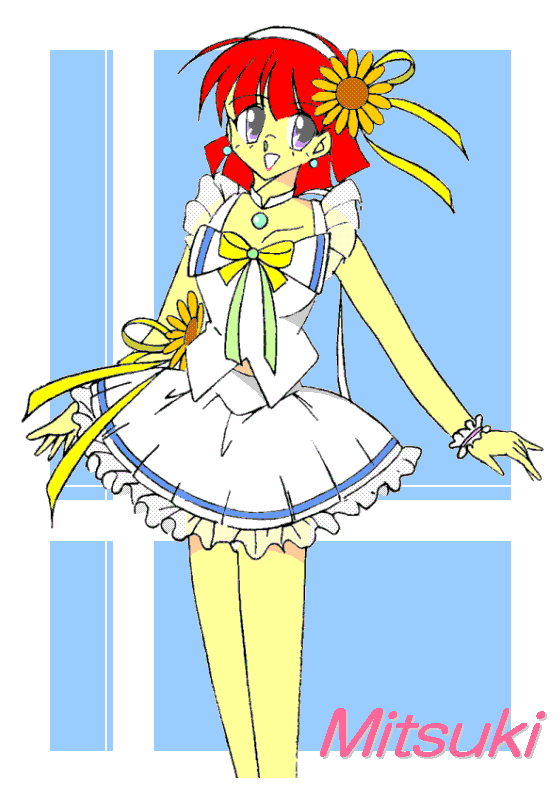
「おーい、みんなで記念写真撮ろうぜ」
「ほらっ、集まって!」
カメラを持つコタローとマッチの呼びかけに、全員が庭の中央に集合した。
そして並んだ一堂に、二人がカメラを構える。
「はい、チーズ……あ、あれ?」
「どうしたんだ?」
怪訝そうにカメラを見る二人に、謙二が声をかける。
「おかしいな? シャッターが切れない」
「こっちもよ」
その時……
「私たちも入れてもらおう」
どこからともなく声がすると、みんなの影の中から、シャドウレディやレディ・ティーゲル、ティラノレディら怪人が次々に現れた。
「げげっ!! 何だぁっ!?」
「キャーッ!!」
「あらら、結局みんな来ちゃったんだニャ」
「大丈夫、みんな心配しないで。私の素敵な友だちよ」
蜜樹は謙二たちや姫高の仲間たちに、彼らを紹介する。
「姉さん、来たのかニャ?」
「ああ、あちらが一段落したしな……たまにはいいだろう。彼らなら我々のことはある程度知っているだろうし」
「それじゃ、もう一度だ。はいチーズ」
パチリ──。
謙二や幸たち南校のクラスメイト、マリアたち姫高の仲間、賢造、幸枝、奈津樹、宝田、桜塚教授、そして愛すべき怪人たちが蜜樹の周りで笑顔を浮かべて写真に納まった。
「いやあ、それにしても凄いメンバーですね……」
謙二が桜塚教授に尋ねる。怪人たちには何度もひどい目にあわされているので、ちょっと及び腰だった。
「何の何の、皆良い奴だ……なあ」
桜塚教授はそう言うと、そばにいたティラノレディと肩を組んだ。
「お前、私が怖く、ないのか?」
「見慣れているとは言わんが、姿だけでは人は……いや、生き物の善悪は判断できんのはわかっているつもりだ。まあよろしく頼むぞ」
そう言って桜塚教授が握手の手を差し出す。
「あ……よ、よろしく」
頭をかきながら、ティラノレディがごつい手を出して桜塚教授と握手した。
「力が強そうだな。よければ今度、私たちの発掘を手伝いに来てくれないか?」
「あ、ああ……わかった」
ティラノレディは照れながらも頷いた。その姿はどこか嬉しそうだ。
「良かったニャ。あたしも今度、ティラノレディに頼みたいことがあるんだニャ」
「お前のは別だ、シャドウガール。また自分の仕事を押し付けてサボるつもりだろう」
「サボるなんてそんなことニャイニャイ。ただ時間を作ってハニィに会いに来たいだけなんだニャ」
「同じようなものだろうっ」
ぽかりとシャドウガールの頭を叩くティラノレディ。
「痛いニャア」
そんな二人の掛け合いに、全員が笑い声を上げた。
「「あはははははは」」
皆と一緒に心の底から思いっきり笑いながら、光雄は──いや、もうその名前で呼ぶことはないであろう。
そう、思いっきり笑いながら、蜜樹は初夏の空を見上げた。
頭の上いっぱいに広がる青い空、ゆっくりと動く白い雲。
平和だ。
いろんなことがあったけど、今のあたしは幸せ。
この平和、この幸せ、いつまでも続きますように……
(完)
後書き
長い間書き綴った「戦え!スウィートハニィ」シリーズもこれにて完結です。夢幻館のイラスト企画投稿用に書き始めてから8年半も経ってしまいました。夢幻館版では一度完結した作品ですが、「少年少女文庫」に再投稿するに当たってはかなりの修正を加えました。Ⅰもそうでしたが、Ⅱでは違いがさらに大きくなってしまいました。理由は「Ts☆Heart」のキャラをお借りして物語に参入させたこと。特にMONDOさんの桜塚真理亜ちゃんと父親の桜塚教授がメインキャラとして参加させてもらったことで、その後作品の基本設定自体ががらりと変わってしまいました。勿論当初から設定の変更を考えていた訳ではなく、お話しが進むに従って、ばらまいた伏線をきちんと回収消化できるのはこういう設定なんだろうなと段々考えがまとまっていった次第で、その辺りは全て最終話に織り込んだつもりです。過去の説明をする為に、仕方なく台詞がやたら多くなってしまったのはちと不本意でしたが。
何はともあれ、昨年半分ほど書いたところで執筆を中断し、6月後半にようやく執筆を再開した為、前回から1年近く空いてしまいましたが、最後まで楽しんでいただければ幸いです。最後に、ここまで読んでいただきました皆様、そして多くのイラストを描いていただいたMONDOさん、ありがとうございました。
(2011年7月25日)