――はっ!?
気がつくと蜜樹は謙二と抱き合ったまま、蜘蛛の糸のようなものでぐるぐる巻きに縛られて、床に転がされていた。
(……先生、気がつきました?)
「何だこの格好は? ええっと、何がどうなって――」
(それが……謙二くんに、その、キスされた後、先生ずっと気を失われていたみたいで)
「そ、そうか……委員長にキスされたんだったな。さっきの変な夢の正体はそれか。いや、もしかしたらキノコの毒のせいかもしれない――」
そう納得しながらも、己の唇に触れた謙二の唇の柔らかい感触を思い出して、蜜樹はぶるっと震えた。
委員長に悪気はない。キノコの毒のせいで正気を失っていたんだ。
それはわかっている、わかっているんだけど……
「…………」
蜘蛛の糸の中で謙二の腕に抱かれているのを感じ、謙二に密着した蜜樹の体は微妙に反応していた。
キノコの毒がまだ体内に残っているせいなのか、下腹部の奥が妙にほてっているのがわかる。
「……ううっ、このままじゃ駄目だ。おかしな気分になってしまう前に、早くなんとかしないと」
気持ちばかりが焦る蜜樹だが、体力を消耗し尽し、さらに体の自由を奪われた今の状況ではどうすることもできない。
「委員長、起きてっ。しっかりしてっ!」
謙二によびかける蜜樹。だが、気を失って蜜樹と一緒に縛られたまま目を閉じた彼は、目覚めようとしない。
その時、頭の上で笑い声が響いた。
顔を上げた蜜樹の目に飛び込んできたのは、さくらんぼのようなかわいい唇を歪ませて、自分を見下ろす謙二の妹の美久――いや、シスター・ミクの姿だった。
「うふふ、気がついた? さすがのあなたもそんな格好じゃ逃げられないわよね……さてと、そろそろ殺してあげましょうか、スウィートハニィ。覚悟はいいかしら?」
「何をっ! こんなことくらいで負けや――」
「負け惜しみはもうよしなさい。さあ、タランチュラレディ、ハニィを殺るのよっ」
シスター・ミクの命令に応えて、複眼のクモ女がカサカサと音をたてながら密樹に近づいていく。
その口が開くと、その長い牙からはどろっとした毒液が垂れ落ちた。
「……く、くそうっ、駄目だ。体が動かない。このままやられるしかないのか?」
(先生、あきらめないでっ。最後の最後まで希望を捨てないでください!)
「あきらめちゃいないさ……でも、こんな状態でどうしたらいいんだ……」
縛られた蜜樹たちに覆いかぶさったタランチュラレディの牙が、蜜樹の首筋に迫る……まさに絶体絶命。
だが、その時……
「お待ちください」
シスター・ミクの前に、白銀に輝く毛皮に包まれた堂々たる体躯の女怪人が進み出た。
そして、うやうやしく頭を下げた。
「んもうっ、せっかく良いところなのにっ。どうして止めるの? シルバーベア」
「スウィートハニィにとどめを刺す役、是非このわたくしめにお申し付けください」
「あなたに? 四天王のあなたが自らスウィートハニィを手にかけようというの?」
「御意、私はこいつのおかげで半数近くの部下を失いました。その恨み、なにとぞこの手で晴らさせていただきたい」
その指の間から、鋼の爪――ベアクローがシャキン! と伸びた。
(……だ、駄目か!)
再び覚悟を固めるハニィ。
「シルバーベア、抜け駆けはおよしなさいっ!」
今度は黒縞混じりの金色のボディスーツをまとった、しなやかな肢体の女怪人が群れの中から進み出た。
「あらっ、レディ・ティーゲル。あなたも帰ってきてくれたのねっ」
「はっ、さきほどヨーロッパより帰還いたしました」
「あなたが加わってくれれば心強いわ。……でも、どうしてシルバーベアを止めるの?」
シスター・ミクは怪訝そうな表情を浮かべ、進み出た女怪人レディ・ティーゲルを上目遣いに見た。
「シルバーベアの抜け駆けには納得できません。彼女の部下のほとんどはDr.シマムラが作った軟弱な改造怪人。我ら蘇りし眷族とは別物です。スウィートハニィにあっさりやられて当然でしょう。……シルバーベア、シスターに媚びるのもいい加減にしたらどうだ?」
「何をっ! 貴様こそ、なぜ止め立てする!?」
「シスター・ミク、殺さずともスウィートハニィにはまだまだ利用価値があると見ました」
レディ・ティーゲルは、そう言うやシスター・ミクの前にひざまずいた。
シスター・ミクの顔が、憮然としたものにかわる。
「何よいまさらっ。スウィートハニィには今まで散々煮え湯を飲まされてきたのよっ。このまま生かしておくなんて、あたしの腹の虫が納まらないんだからっ!」
「このような手も足も出ない相手をなぶり殺しにするなど、そのような浅慮ではとても我らを率いることなど……あ、いや、これは失礼しました」
片膝をついたままレディ・ティーゲルは頭を下げる。
「誇り高い戦士レディ・ティーゲル……さすが『虎の爪』四天王の一人ね。でもその甘さが命取りになることもあるのよ。止めは刺せる時に刺しておかなくちゃ、後で後悔しても遅いの。大きな犠牲を払って進めてきた『ハニィ抹殺計画』も、もう少しで完了するのよ」
苦虫を噛み潰したような表情で、シスター・ミクは諭すように話す。
ちなみに『虎の爪』四天王とはパンツァーレディ、レディ・ティーゲル、ゴールデンバット、シルバーベアの四人だ。だが四天王筆頭だった改造怪人パンツァーレディは元の生田奈津樹に戻り、ゴールデンバットが蜜樹とマリアによって倒された今、最強の名をほしいままにした『虎の爪』四天王の中で生き残っているのはレディ・ティーゲルとシルバーベアの二怪人だけである。
……だがこの二人、いささか仲が悪かった。
「わざわざDr.シマムラの手を煩わせることもありません。殺さずとも、この私がこいつを従順な召使いにしてやりましょう。意志のない人形にするよりも、ずっと価値がある筈です」
そう言いながら、レディ・ティーゲルは棘の付いた輪を取り出した。
それを見たシスター・ミクは、ふふん……と鼻を鳴らした。
「ふーん、いいわ、わかったわレディ・ティーゲル。じゃあ、あなたのやり方で今すぐハニィを屈服させてごらんなさい。あたしの前にひざまずかせて、このあたしに永遠の忠誠を誓わせるのよっ」
「……かしこまりました」
「よし。……タランチュラレディ、下がりなさいっ! シルバーベア、あなたもね」
「ギギッ」
牙を剥いたタランチュラレディは蜜樹の首元から牙を離すと、すすっとその体から離れた。
シルバーベアもくやしそうな表情のまま引き下がる。
レディ・ティーゲルは棘の付いた輪を手に、蜜樹にゆっくりと近寄った。
「な、何を……」
謙二と一緒に床に転がされたまま格好で、顔だけをレディ・ティーゲルに向け、かろうじて声を絞り出す蜜樹。
その耳元でレディ・ティーゲルはぼそぼそと呪文のような言葉を呟くと、蜜樹の首に首輪をパチリとはめた。
(……え?)
「あう! くうううぅぅ――」
首輪をはめられた瞬間、蜜樹は身をよじらせて苦しみだした。
「うぐぅ、……うあっ、ううう……くっ、苦しい……っ!」
(先生! 先生っ!!)
「……………………」
やがて、ぴくりとも身動きしなくなる蜜樹。
それを見たレディ・ティーゲルは、その剣で蜜樹と謙二をぐるぐると縛り付けていたタランチュラレディのクモの糸をばっさりと切り裂いた。
「立て、我がしもべスウィートハニィ。マタンゴレディの毒は消えている筈だ」
「……はい」
焦点の定まらない目で蜜樹はゆらりと立ち上がると、レディ・ティーゲルの前にひざまずいた。
「……私はあなた様のしもべです。ご主人様、何なりと御用をお申し付けください」
「スウィートハニィ、貴様は『ネオ虎の爪』に忠誠を誓うか?」
「……はい、ご主人様のお言いつけとあらば、『ネオ虎の爪』に忠誠を誓います」
抑揚の無い声で喋り続ける蜜樹。
「く――くくっ、きゃはははははははははっ! いいわこれっ。……スウィートハニィ、今度こそあなたはあたしのモノになったのね。ふ、ふふふ……あっはははっ、ほんとにいい気味っ!!」
椅子から立ち上がって、甲高い声で笑い続けるシスター・ミク。
それを見たレディ・ティーゲルが、蜜樹に命令する。
「スウィートハニィ、お前はこれからシスター・ミク様の為に働くのだ」
「……はい、ご主人様」
「ならばシスター・ミク様の前でひざまずけ。その手に接吻し、永遠の忠誠を誓うのだ」
蜜樹はシスター・ミクの前に片膝をついてひざまずいた。
シスター・ミクは勝ち誇った目で、蜜樹を見下ろした。
「うっふっふふふっ、いいザマねスウィートハニィ。……今からあなたはあたしのために働くの。せいぜいこき使ってあげるわっ。あ〜いい気持ち!」
シスター・ミクは蜜樹に向かって小さな手を厳かに差し出す。
「……このスウィートハニィ――」
蜜樹はシスター・ミクが伸ばした手に己の手を添えた。
満足気な、勝ち誇った表情で彼女を見下ろすシスター・ミク。だが次の瞬間、蜜樹はシスター・ミクの手をぎゅっと掴んで握り締めると、にやりと笑った。
焦点の合っていなかった目には、何時の間にか強い意志の光が宿っている。
「このハニィ……必ずあなたを倒してみせる!」
「な……っ!?」
シスター・ミクの手をぐいっと引っ張り、くるりとその背中に回りこむと、蜜樹は小さな彼女の体を羽交い絞めにした。
「……あぐっ!? な、何? どういうことなのっ!?」
訳も分からず、捕まえられたシスター・ミクは足をばたばたさせた。
「れっ、レディ・ティーゲル! 何をしているのっ! 早く私を助けなさいよっ!!」
「あっははは、シスター・ミクよ……いや、井荻恭四郎と呼んだほうが良いのかな? 私はお前に従う気などはなっからないっ」
「な、なんですってぇ!?」
「お前のことは前々から、シャドウレディに聞いているんだよ」
「シャドウレディ? あの裏切り者から?」
「私は以前からシャドウレディと親交が深くてな。ヨーロッパ方面に出撃した後も、国内組のシャドウレディとよく連絡を取り合っていたのさ。シャドウレディから『虎の爪』壊滅の経緯は聞いた。私がここに来たのはお前を助ける為ではない。スウィートハニィを助ける為だ」
「スウィートハニィはあなたに操られていたのではなかったの!?」
「残念だけど違うね。彼女には私に操られるふりをしろって囁いたのさ」
そう言って、レディ・ティーゲルは周囲の怪人たちを牽制しながら、にやりと笑った
「……いきなり『シャドウレディに頼まれた。操られたふりをしろ』なんて囁かれるから、びっくりしたよ」
(咄嗟にしては迫真の演技でしたね。でも、よく敵の怪人である彼女の言葉を信じましたね)
「彼女の目は濁っていない。信用できると思ったんだ」
(さすがですね、先生。それにレディ・ティーゲルも、さすが四天王と呼ばれていただけのことはあります)
「え?」
(私が戦っていた頃、『虎の爪』の幹部として作戦を立てていたのはレディ・テーゲルだったんです。ほんとに苦戦続きだった。でもシスターと意見が合わずに本部から遠ざけられたはず。ヨーロッパに出撃というのはそういうことなんでしょう。彼女が去った後、幹部としてあたしの前に立ち塞がったのがパンツァーレディ……姉さんだったんです)
「そうだったのか……ん? 待てよ?」
(どうしました? 先生)
「ここに集結している怪人たちは、シスター・ミクの元で一枚岩じゃないということか?」
(あ、そう言えばそうですね……)
レディ・ティーゲルの行動は、怪人たちの全てがシスター・ミクに盲従している訳ではなく、シスター・ミクと距離を置く怪人が存在することを暗示していた。
しかもレディ・ティーゲルとシルバーベアの行動を見ると、怪人たちの間にも仲の良し悪しがあるらしい。
だがそれが何を意味するのか、この時点の蜜樹には理解できない。ひとつだけ言えるのは、あまりにおびただしい数の怪人たちを前に、勝算のない無謀とも言える戦いを挑むしかなかった蜜樹に、勝てるかもしれないという希望が湧いてきたということだ。
しかも、蜜樹の心身は復活を遂げていた。
「本当に気分がすっきりして、さっきまでの気持ち悪さが全くない。それに体力も回復して力がみなぎっている。どうして?」
「ふふふ、どうだスウィートハニィ、パワーは回復したか?」
怪訝な表情を浮かべている蜜樹に、レディ・ティーゲルが声をかけた。
「……え? は、はい。あなたのおかげなんですか?」
「そうだ。お前につけた首輪には生物の肝機能をフル回転させるブースト作用がある。体内に残る毒を解毒し、失なわれた体力を体内グリコーゲンを急速燃焼させることで一気に回復させるのだ。本来は私の部下にベストパフォーマンスで働いてもらう為のアイテムだがな」
そう言って蜜樹から首輪を外すと、レディ・ティーゲルはそれを己の腰のベルトに下げた。
「ありがとう、助かりました。……よおし、シスター・ミク、覚悟しろっ!」
「なによっ、振り出しに戻っただけじゃないの。このあたしが二度も負けるわけないわっ!」
そう言うと、シスター・ミクは蜜樹の腕をがぶりと噛みついた。
「いってぇ〜っ!!」
まさか噛みついてくるとは思わなかった。
驚く蜜樹の腕を遮二無二振りほどくと、シスター・ミクは取り囲む怪人の群れの向かって叫んだ。
「みんなっ、早くあたしを助けるのよっ!」
怪人たちは、一斉に蜜樹に向かって飛びかかってきた。
(先生、あぶない!)
「ちっ!」
蜜樹は床に放り出されていたプラチナフルーレに向かってジャンプすると、体をくるりと一回転させてそれを拾い上げ、立ち上がるや否や怪人たちに向かって中段に構えた。
剣を向けられた怪人たちの足が止まる。
だが、蜜樹とシスター・ミクの間には、再び怪人の群れがぶ厚い壁を作っていた。
「きゃはははっ。あなたにこの壁が突破できて? スウィートハニィ」
「くそうっ、こいつらも一枚岩じゃないんだ……何か手があるはず。でもどうすれば――」
「焦るなスウィートハニィ。もうすぐあいつらが来る。もう少しの辛抱だ」
「あいつら? 誰が?」
そばに寄ってきたレディ・ティーゲルに問い返す蜜樹。
だが、その答えが返ってくる前にシスター・ミクが怪人たちに命令を放った。
「スウィートハニィと裏切り者のレディー・ティーゲル、こいつらまとめて殺っちゃって!!」
「「グエエエエエ〜ッ!!」」
怪人たちが一斉に雄叫びを上げ、その群れの中から一歩進み出たシルバーベアが、レディ・ティーゲルを睨みつけた。
「シスター・ミクのお許しが出た。今こそ目障りな貴様を葬ってくれるっ」
シルバーベアは小躍りして、ベアクローを構えた。
「ふっ……貴様ごときに殺られはせんよ」
腰に下げた剣を鞘から抜き出すレディ・テーゲル。
シルバーベア以外の怪人たちも、再びじりじりと動き出す。
その時――
「シスター・ミク。力攻めより、まず人質を確保するほうが先じゃないの?」
怪人の壁の向こうから聞こえてきた女性の声に、密樹ははっとなった。
彼女の傍らと後ろには、謙二と幸が気を失って倒れたままだ。声の主は、戦うよりもまずその二人を人質に取れと言っているのだ。
それはDr.シマムラの声だった。
「ははんっ、なるほど……ハニィの仲間を人質に取れば、スウィートハニィは反撃できない。例え人質に取れなくても、二人同時に守りながらこの数の怪人を相手にまともに戦うことなんてできないよね。うわぁ、いい作戦だわっ。……くくっ、どうするの? スウィートハニィ。きゃはははっ!!」
怪人の壁の向こうで、シスター・ミクが笑い声を上げた。
(……先生っ、このままでは幸さんと謙二君が!)
「ああ、巻き添えになってしまう……」
怪人たちは二手に分かれると、幸と謙二に向かってゆっくりと移動し始める。
「かたっぽだけでいいわっ。殺さずに人質にとるのよっ」
「「ぐええっ!!」」
「くそう、痛いところを突いてくる。二人を同時に守りながらこの数の怪人と戦うか……できるのか?」
(難しいですね。レディ・ティーゲルが一緒に戦ってくれたとしても、二人だけではどうにもできないでしょう。でも、例えそうだとしても、先生は……)
「少しでも望みがあれば……戦う!」
(はい!)
「いずれにしても、レディ・ティーゲルに協力してもらうしかない」
(それにしてもDr.シマムラって何者でしょう? あたしたちが一番して欲しくないことをずばりと突いてくるなんて――)
「恐ろしい奴だ。……とにかく、レディ・ティーゲルに二人を守ってもらうよう頼んでみよう」
涼やかな眼でシルバーベアと対峙しているレディ・ティーゲルに視線を向ける蜜樹。
その時レディ・ティーゲルがつぶやいた。
「……ふっ、ようやく来たか」
その声と同時に、蜜樹たちの立つ床の前に黒いしみができたと思うと、どんどん広がり始めた。
「間に合ったですっ! ハニィ、大丈夫かです!?」
「え? その声は?」
大きくなった床にできた黒いしみの中から、次々と踊り出てくる三つのシルエット。
「ハニィ! 助けに来たニャ!」
「よく持ちこたえたな、スウィートハニィ」
「マリアちゃん! それにシャドウガールに、シャドウレディ! あなたたち、こんな所まで──」
そう、それはスウィートハニィのバトルスーツを着たマリア、猫の姿のシャドウガール、そしてシャドウレディの三人だ。
「久しぶりだなレディ・ティーゲル。スウィートハニィを助けてくれて、礼を言う」
「礼には及ばんよ。私もいいかげんうんざりしていたところだ」
シャドウレディとレディ・ティーゲルは簡潔に言葉を交わす。
「マリアちゃん! シャドウガール! 幸と委員長を守ってっ!」
「ガッテンだニャ!」
Vサインをするや否や、謙二の体に飛び込むシャドウガール。
途端に謙二のズボンから尻尾が伸び、頭にはニョキニョキとネコミミが生えてくる。
むくりと起き上がった謙二の姿は、元の謙二の顔立ちを残しながらも、猫の耳と尻尾を持った女の子の姿に変化していた。
「ニャハハハ、シャドウガール見参だニャ!」
シャキンと爪を立てて、怪人たちに向かって身構えるシャドウガール。
「こっちの娘は私に任せろ」
マリアを制して幸の影に飛び込むシャドウレディ。
幸は途端にぱちっと目を開き、すっと立ち上がった。
「ふむ……まあこんなものか」
幸に乗り移ったシャドウレディは、シャドウガールとともに蜜樹やマリアたちにとともに怪人たちに向かって身構えた。
おびただしい数の怪人に対して、三人の心強い助っ人が加わった。
だが、蜜樹は意外な言葉を発した。
「シャドウレディ、シャドウガール、二人を巻き添えにしないで。委員長と幸の二人をここから逃がしてちようだいっ!」
「ええ!? あたしはハニィと一緒に戦いたいんだニャ!」
「だめよ! 二人に何かあったらどうするの?」
「わかった。それでは先にこの二人を脱出させよう。シャドウガール、ついて来い」
「でもあたしはハニィと一緒に戦いたいんだニャア」
口惜しそうに口を尖らせて蜜樹の傍から離れようとしないシャドウガール。
だが、マリアがその背中をシャドウレディに向けて押し出す。
「あたしがハニィを助けるですっ! ハニィのお願いを聞いてあげてですっ!」
「シャドウガール、行くぞっ」
シャドウレディの声とともに、床の影が広がっていく。
「……わかったニャ、二人を安全な場所に移したらすぐに戻ってくるんだニャ。ハニィ、それまでがんばれニャ」
「うん。シャドウレディ、二人を頼むわよ」
「了解した。ところで、パンツァーレディから伝言がある」
「姉さんから?」
「奴らと戦う時には、髪飾りと指輪を両方とも身につけて戦えということだ」
「両方を?」
「その娘がつけている指輪は修復が完全ではないらしい。だが髪飾りと同時に身につけると、絶大な効果を発揮するらしいぞ」
(髪飾りと指輪……同時に身につける……ふたつ両方……)
「そうか、やっぱり二つのアイテムには関係があったんだ」
「そういうことらしいな。スウィートハニィ、私たちが戻るまでもう少しだけ持ちこたえろ」
「うん。二人を頼むわ」
真っ黒い影の中に飛び込もうとする二人。
だが、怪人の群れがふたつに割れると、その間から再びシスター・ミクが姿を現す。
「お前たち、何度あたしの邪魔をするのよ……このうらぎりもの!」
「お前、どっかで会ったかニャ?」
「シスター・ミクだとさ」
そう言って肩をすくめ、レディ・ティーゲルがニヒルな笑いを浮かべる。
「ニャにぃ? シスター・ミク? それじゃこいつ、恭四郎なのかニャ!」
「まだそんな子どもに成りすましているのか……つくづく見下げ果てた奴だ」
影に足から沈み込みながら、シャドウレディがシスター・ミクを睨みつけた。
「うるさい、うるさい、うるさ〜いっ! みんな、こいつらをまとめてころしちゃいなさいっ!!」
「「グエエエッ〜!!」」
シスター・ミクの命令に一斉に雄叫びを上げる怪人たち。
だがそれを恐れようともせず、シャドウレディは幸の顔でにやりと笑った。
「もう遅い」
シャドウレディ、続いてシャドウガールはあっという間に影の中に消えていった。
残った蜜樹とマリア、そしてレディ・ティーゲルの三人は、怪人たちに向かって改めて身構えた。
「さあっ、これでもう人質は取れないわよっ。遠慮なくかかってこいっ!!」
「きいいいいっ! Dr.シマムラっ、あいつら何とかしてよっ!!」
「はいはい……まったくしょうのないお子ちゃまね」
Dr.シマムラの声と同時に奥の扉が開き、さらにおびただしい数の怪人たちが部屋に入ってきた。
「ふっ、増えた!?」
「こいつら、ほんとにきりがないな……」
「ハニィ、早く指輪をつけるですっ!」
指輪を抜こうとするマリア。だが、蜜樹はそれを制した。
「それは後。マリアちゃん、あたしはこのままでも十分戦えるから、一緒に戦いましょう」
「でもハニィ、あたしはこの指輪をハニィに届けに来たんだです。これはハニィが使わないと」
「ねえマリアちゃん、あなたは指輪の力で変身したの?」
「えっ? あ、そうなんだです。親父に言われて試してみたら、あの夢みたいに変身したんだです」
それを聞いた蜜樹はにこっと笑った。
「今、ここで指輪と髪飾りを交換している余裕はないわ。二人でこいつらを何とかしましょう。スウィートシスターズの力を見せつけてやるのよっ!」
ひゅっと一振りした剣を両手で握り締め、怪人たちに向かって構えるハニィ。
それを見たマリアも、怪人たちに向けて巨大ハリセンを構えた。
同じバトルスーツを着た二人が身構える姿は、見事なまでに美しくきまっていた。
「さあっ、マリアちゃんいくわよ!」
「はいですっ! ハニィ!」
「「いっけ〜!」」
同時に駆け出す蜜樹とマリア。怪人たちも二人に襲いかかる。
ぐええええええええ〜っ!!
「来た!」
「でやああああぁっ!!」
蜜樹がプラチナフルーレが空気を切り裂き、マリアの巨大ハリセンがうなる。
その度に向かってくる怪人は次々と倒れ、塵となって消えていった。おびただしい怪人の数が、みるみる減っていく。
一方、レディ・ティーゲルは、シルバーベアのベアクローと剣を交えていた。
「おのれ、貴様ごときに殺られは……このベアクローでそのすまし顔を引き裂いてくれる」
「ふふふ、そんな動きでは傷ひとつつけられんよ」
矢継ぎ早にベアクローを繰り出すシルバーベア。その先端に触れれば、瞬く間に体がずたずたに切り裂かれることだろう。
だが、レディ・ティーゲルは軽やかにシルバーベアの動きを見切っていく。
そして遂に……
「うがああああっ、しっ、シスター・ミク様……申し訳ありません!」
レディ・ティーゲルの剣に身体を貫かれたシルバーベアは、塵となって消えていった。
「ふっ、どこの世界でも誇りを忘れた者は生きていけんよ。全く馬鹿なやつ」
それから戦うこと数分……いつしかシスター・ミクの周囲には、数体の怪人を残すのみとなってしまった。
怪人の壁はもはやなくなり、彼女たちの前には落ち着かない表情で立ちつくすシスター・ミクと、マタンゴレディ、タランチュラレディ、そしてブラックピジョンとクロウレディといった見覚えのある怪人たち、そして彼女たちの後ろに離れて立つ黒いスーツの上に白衣を羽織った女性――Dr.シマムラを残すのみとなった。
「シスター・ミク! 今度こそ年貢の納め時のようねっ。覚悟しなさい!」
シスター・ミクを睨み付けてビシリと剣を向ける蜜樹。
マリアもそれに倣って、巨大ハリセンをびしっと振り抜いた。
「い、いやっ! ……な、何とかしてよDr.シマムラっ! もっと、もっと怪人を出してっ!」
二人の気迫に、シスター・ミクはたまらず背後の白衣の女性に駆け寄った。
だが……
パシィィッ!!
彼女はシスター・ミクの頬に平手打ちを見舞った。
「あ……」
シスター・ミクは頬を押さえ、呆然と白衣の女性を見上げた。だが、Dr.シマムラはそんなシスター・ミクを見ようともせず、言い放った。
「井荻恭四郎、せっかく蘇えらせた怪人たちをよくもここまですり減らしてくれたわね。作ってあげた改造怪人は全然使いこなせないし……使えない……全く使えないわ。見込み違いもいいところね」
ついさっきまでの、どこか楽しんでいるような声とは全く違う、氷のような雰囲気をたたえたその声に、蜜樹は剣をぐっと握り締めた。
「お前は……誰だ?」
蜜樹の問いに、白衣の女性は表情を変えようともしない。
「『Dr.シマムラ』ということにしておきましょうか」
「何が『ということにしておきましょうか』だっ。お前が『ネオ虎の爪』の怪人たちを生み出した張本人なのかっ!?」
「ええっ? 怪人を生み出す? ハニィ、それじゃこいつが真の敵なのかですっ?」
興奮気味の蜜樹とマリアに向かって、Dr.シマムラは淡々と答える。
「ん〜、ちょっと違うわね。あたしがやったのはこいつ――井荻恭四郎のために、眠り続けていた怪人たちを目覚めさせてやったことと、目覚めた彼らを働かせる方法を教えてあげたこと、そして手足となって忠実に動くしもべを作ってやったことよ」
「しもべ作りだと?」
「思考力の低い下級怪人の潜在能力を100%引き出す改造手術と、彼らを意のままに動かす制御装置を埋め込む手術よ。四天王たちのような思考力の高い上級怪人は、幹部として動いてもらう為に改造してないけどね」
「お前はどうして井荻恭四郎に協力してきたんだ?」
「井荻恭四郎は、気が遠くなるくらい長い間封印されていたあたしを解放してくれたの。しかもあたしにこの『島村依子』の身体を与えて自由に活動できるようにしてくれた。そんな彼に興味を持ったから、『世界を自分の思い通りにしたい』という彼の望みを叶えてあげることにしたの。だから今日まで、こいつの為にいろいろんなものを作ってあげたし、いろいろなことを教えてあげたわ。遺跡の地下深く眠っている怪人たちのこと、そして彼らが彼らの女王である『シスター』の称号(しるし)を持つ者に従うことを教えたのも、あたし」
唖然とする密樹とマリアを尻目に、Dr.シマムラはなおも語り続ける。
「……だけど、怪人たちの巫女であり女王もである『シスター』は女性にしかなれないの……当然でしょう? だから、『誰か女性をシスターに仕立てて、彼女を操り人形にして怪人を支配すればいいわ』ってアドバイスしたの。恭四郎も最初は私のアドバイスどおり、生田幸枝をシスターに仕立てようと動いていたみたいだけど、しばらくしたら『俺がシスターになる、だから生田幸枝になる方法を教えろ』なんて言い出したのよ。普通そんな風に考える?」
「……まあ、こいつの望みを叶えてあげれば、あたしたちの世界をもう一度ここに復活させるというあたしの目的も実現できるから、そんなことどうでもよかったんだけどね。だから、まず魂を他人に移す薬、つまり憑依薬を作ってあげたわ。それを使ってこいつが生田幸枝に憑依した後で、今度は遺跡で目覚めさせた怪人たちを連れてきてやったの。そして彼らの能力をコピーした改造怪人や下級の改造怪人をどんどん作ってあげたわ」
「……生田幸枝になった恭四郎に『シスター』のしるしを与えて、『虎の爪』を組織させた。そして怪人たちを使って世界征服に乗り出させたの。最初は上手くいっていた。『シスター』として大勢の怪人たちにかしずかれて、さぞかし良い気分だったでしょうね。計画も順調……そう、もう少しで世界中を『虎の爪』の支配下に置けた筈なのに、どこで狂っちゃったんだろう? 確かにスウィートハニィのおかげで『虎の爪』は崩壊したけれど、一度くらい組織が壊滅したからといったって、あたしがいればそんなものいくらでも作り直せたのに。なのにこいつときたら、折角助けて新しい組織を作ってあげようとしたら、今度は女性でも小娘になりたいだなんて言い出して、もう信じられない。いざとなったら、子供の姿の方が自分の身を守れる? バッカじゃないの? ずっとこんな小娘の姿でい続けたら、思考も段々子供化していくのは当たり前じゃないっ!」
「……今のこいつはただの幼稚な夢見る少女と変わらない。『ハニィ抹殺計画』にも黙ってここまでつきあってあげてたけど、こんなザマだもんね。もうやってられないわ。まさかこんなに使えないやつだったなんてね……そうよ、全てこいつが悪いの!」
最初は淡々としゃべっていたが、段々と興奮し始め、くやしさを滲ませるDr.シマムラ。
だが、そんな自分に気がついたのか、軽く咳払いした。
「コホン……少ししゃべり過ぎたようね。おしゃべりはこれくらいにしましょうか」
そこで話を止めたDr.シマムラは、パチッと指を鳴らした。
すると、扉の向こうから新たな怪人たちが再び湧き出すように入ってきた。
それを見たシスター・ミクは、その顔に嬉々とした表情を浮かべた。
「よおし、いいわよDr.シマムラ。今までのあたしへの侮辱は忘れてあげる。今度こそあいつらをやっつけちゃいなさい!」
だが、
「全く、きゃんきゃんうるさいわね……」
「……え?」
「お前はもう『シスター』なんかじゃないの……用済みよ。マタンゴレディ、この子に最後にいい夢を見させてあげなさい」
Dr.シマムラに促されて、マタンゴレディが自分の体から毒キノコを数個もぎり取ると、唖然とするシスター・ミクに近寄って、その小さな体を床に押しつけた。
そして、その口に強引にキノコを突っ込んだ。
「あぐっ!? や、やめろ……ん、んぐっ──」
涙を浮かべて押し込まれるキノコを飲み込む、白いドレスの少女。その目の焦点が合わなくなり、意志が段々失われていく。
やがて彼女は、うつろな声で笑い出した。
「け……けけっ、スウィートハニィ……ようやく……けけ……あたしの前に……ひっ……ひざまずいたようね……あはは、あたしの勝ち……よ……あ……あたしがこの世界の女王様……けけ……けらけらけら…………」
「ふふふ、キノコの毒が効いてきたようね。妄想の世界で女王になりなさい……たった一人だけの王国のね」
やがてシスター・ミクは涙を浮かべながら笑い出し、踊るようにふらつき始めた。
「……けらけらけら……あたしは……けらけら……世界の支配者……女王……シスター・ミク……けらけらけら……さあ、みんな……けらけら……ひれ伏し……なさい……けらけらけら……」
白いドレスの少女はだらしなく口元を弛ませ、笑いながら踊り続ける。
「狂った……」
(井荻恭四郎……彼にとっては、ある意味幸せだったのかもしれませんね)
「でも、こんなこと許されない……あいつだって人間だ。ずっとあの女の掌の上で操られていただけかもしれないんだ……」
蜜樹はそうつぶやくと、きりっとDr.シマムラを睨んだ。
「Dr.シマムラ、お前のことはお天道様が許しても、このスウィートハニィが決して許さない!」
「許さない? ふーん、あなたに何ができるって言うの? そろそろあなたも処分しなければいけないようね。自分の正体を思い出す前にね」
「正体?」
「ふっ、何でもないわ。……さあみんな、スウィートハニィを殺しなさい。ハニィ、彼女たちは改造怪人じゃないわ。本物の眷属の怪人、四天王ほどじゃないけれどみんな手強いわよ。覚悟するのね」
蜜樹とマリア、そしてレディ・ティーゲルを取り囲む怪人たち。
その只ならぬ殺気にマリアがはっと蜜樹を見る。
「ハニィ、大丈夫?」
「勿論。でもこいつらの殺気、さっきまでと全然違う。今度こそ決戦のようね」
じりじりと蜜樹たちに迫る怪人たち。その動きは今までの怪人たちと違って隙がない。下手に動こうものなら一斉に飛び掛ろうという気迫がみなぎっていた。
さすがのレディ・ティーゲルも、剣を構えたまま動けないでいる。
「くっ……」
「ハニィ、どうするんだです?」
「マリアちゃん、動かないで……じっとしててっ!」
動揺するマリアを諭す蜜樹。
「くそう……どうする?」
(先生、このままでは駄目です)
「わかっているさ……わかっているけど……」
そう、怪人たちのプレッシャーに身動きできない蜜樹にはどうにもできなかった。
だがその時、蜜樹の影が急速に広がり始めた。そしてその中から、マリアに向かって呼びかける声がした。
「娘、指輪をハニィに渡せ!」
同時に、影から二つの小さな影が飛び出す。それはシャドウガールとシャドウレディだった。
「待たせたな。あの二人は確かに賢造博士に預けたぞ」
「お父さんに?」
「ああ、この建物の外まで来ている」
「そっか、お父さんも来てくれたんだ……」
ほっとした表情を見せる蜜樹。だが、そんな彼女をシャドウレディが叱咤する。
「こいつら、一筋縄でいかん相手ばかりだぞ。……さあ娘、早く指輪をハニィに渡すんだ。お前は私らが守る。レディ・ティーゲル、貴様も手を貸してくれ」
「わかった」
「さあ、急げ。ぐずぐずするな」
「わ、わかったです!」
マリアは右手の指に嵌めた指輪を抜き出すと、蜜樹に向かって放り投げた。途端にマリアの手にあった巨大ハリセンが消え、バトルスーツは姫高の制服に戻っていく。
一方、放り投げられた指輪を左手でキャッチするハニィ。
「あ! マリアちゃんに髪飾りを――」
「ハニィ、さっきの言葉を忘れたのか? 『アイテムは同時につけろ』という言葉を」
頭に手を伸ばして髪飾りを外そうとする蜜樹を、シャドウレディが制する。
「で、でも、それじゃマリアちゃんが危険に――」
「大丈夫だ。彼女は私たちに任せろ。すぐに合体する」
「ちょっと待つですシャドウレディさん。あたしはハニィと一緒に戦いたいんだですっ。あなたと合体したらあたしの意識はなくなってしまうです。それじゃああたしはハニィと一緒に戦えない……指輪は渡せたけど、あたし、ハニィを助けたいんだですっ!」
シャドウレディを見詰めるマリア。その目をシャドウレディもじっと見返す。
その傍らで、シャドウガールもマリアの真剣な眼差しをじっと見詰めていた。
「ふむ……いいだろう。シャドウガール、アレをやってみるか」
「ガッテンだニャ!」
シャドウレディの言葉にシャドウガールが頷く。その表情は晴れやかだ。
「お前もあたしたちと一緒に戦うんだニャ」
「……え?」
「心配するな。わたしたちが力を貸してやろう」
そう言うと、シャドウガールの影に飛び込むシャドウレディ。途端にシャドウガールの背が伸びていく。
「マリアとかいったな、気をしっかり保つんだぞ」
そう言うと、一体の猫の姿になったシャドウシスターズ(シャドウレディ&シャドウガール)はマリアの体に飛び込んだ。
「う……あううっ!?」
マリアの頭から、ニョキッと猫耳が生え、そしてスカートの奥から尻尾が伸びる。
同時に、彼女の着ていた青い姫高の制服が、黒いゴスロリ風な衣装に変わっていく。
「な……なに? なんなんだですニャ!?」

頭に生えたネコミミとお尻から飛び出した尻尾を触りながら、困惑するマリア。
(さあ、存分に戦うがいい)
「シャドウレディさん……ですニャ?」
(あたしたちがついているんだニャ! さあ、一緒に戦うんだニャア!)
「シャドウガールちゃんもあたしの中にいるですニャ?」
(われらはひとつ……さあ、みんなでハニィを助けるのだっ)
「よ、よっしゃあっ! わかったですニャ!」
胸の前で両腕をクロスさせると、マリアの指の爪がシャキンと伸びる。
すっかりネコ娘と化した彼女は、怪人たちに向かって身構えた。
「シャドウマリア、参上だですニャ!」
「「グゲゲゲッ!!」」
襲い掛かる怪人たちをもの凄いスピードで避けると、マリアは鋭く伸びた爪をふるって怪人たちを切り裂き、倒していく。
「どうだ〜〜ですニャ!」
マリアは得意げに決めのポーズを取った。
「マタンゴレディ、そいつを動けなくしてやりなさい」
「グゲッ!」
Dr.シマムラの命令に応えて、マタンゴレディが頭の傘から黄色い毒胞子を撒き散らし、己の体からむしったキノコを手にマリアに襲い掛かる。
だが、マリアはマタンゴレディの動きを見切ったように毒胞子の舞う空間を避け、その懐に飛び込んだ。
マタンゴレディは手に持ったキノコをマリアの口に押し込もうとする。だが彼女はその手をひょいっと避けると、爪でキノコを持った腕ごと切り飛ばしてしまった。
「ウ、ウゲェ!」
「とどめだですニャ! シャドウマリア、パ〜〜〜ンチ!!」
すっ飛ばされた右腕を見て慌てふためくマタンゴレディ。その正面からマリアは正拳突きを放った。
ぼこっと音がして、マリアの腕がマタンゴレディの身体を突き抜ける。
「グ、グガァ!!」
シャドウマリアの腕で身体を貫かれたまま、マタンゴレディは塵になって消えてしまった。
「やった……ですニャ!」
嬉しそうにガッツポーズを取るシャドウマリアだった。
「マリアちゃん……いいえ、みんな、あたしの為に無理しないでっ」
「大丈夫だですニャ! さあハニィ、早く指輪をつけて!」
(先生、やりましょう! がんばってくれているマリアちゃんやシャドウガールたちのためにも!)
「うん、そうだな……よおし、いっくぞ〜〜っ!」
蜜樹は手にした指輪を自分の右手薬指にはめた。そして――
「ハニィ、フラ〜〜〜ッシュ!!」
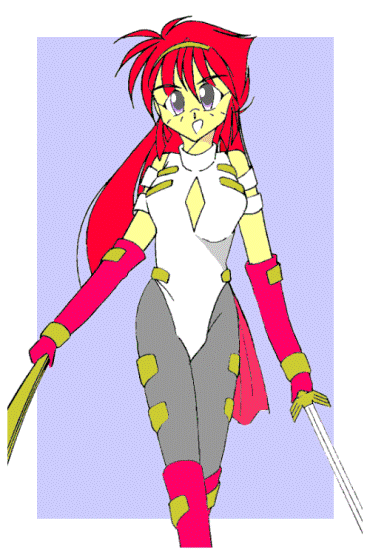
蜜樹が叫ぶと、途端に彼女の身体が光り輝き、その光の中で姿がさらに変わっていく。
ショートカットにしていた赤い髪がするすると腰まで長く伸びていき、そして着ていた赤いバトルスーツが、その色を眩しいばかりの白へと変化させる。さらに肘や膝、手首を守るようにつけられたプロテクターが黄金色に変わった。
左手にプラチナフルーレ、右手には巨大ハリセンが握り締められている。
「スーパーハニィ、参上!」
「ハニィ、その格好は何だですニャ?」
「ん〜、よくわかんないけど、指輪をつけた途端に何だかこの姿が頭の中に浮かんで、それに何かこう、あいつらを封印できそうな気がする」
「封印?」
「うん。ほら、こうして」
蜜樹がプラチナフルーレとハリセンを交差させると、その間から竜巻のように空気の渦が巻き上がる。そしてその中に蜜樹に襲い掛かろうとしていた数体の怪人が吸い込まれた。
「ぐ……ぐげえええっ!?」
竜巻がおさまると、そこには小さな石がぽつんと転がっていた。
(先生、この力……今までの力と違う。そう、これが封印)
「どうしてだろう? こうすればあいつらを封印できるってわかるんだ」
(あたしもです。何かを思い出しそう。あたしは……あたしは――)
「くっ、その姿……遂に覚醒したようね。でももう終わりよっ!」
Dr.シマムラが苦々しそうに蜜樹を睨みつけた。
「お前たち、やってしまいなさいっ!」
ぐえっ!
タランチュラレディが、クロウレディが、ブラックピジョンが、そしてその他の残った怪人たちが二人に襲い掛かる。
「ハニィ、やるぞ!」
(はい! 先生)
襲い掛かる怪人たちを向かって、次々に剣とハリセンを振るうハニィ。その度に、怪人たちが封印され、小石と化していく。
レディ・ティーゲルは向かってくる怪人を剣で切り倒し、シャドウマリアも襲い掛かる怪人をその鋭い爪によって次々と倒していく。
「こいつら、これだけの上級怪人を相手に……これ以上怪人たちをすり減らすわけにもいかないか。仕方ない、みんな引きなさい」
Dr.シマムラの言葉に動きを止め、生き残った怪人たちは後ろに下がった。
「しょうがないわね、ふふふ、結局このあたしが引導を渡してあげるしかないのか。スウィートハニィ……いいえアルテミス、今度は易々と封印されないわよ。覚悟しなさい」
にやっと氷のような微笑みを浮かべたDr.シマムラの姿が、ゆらりと揺れた。
そして再び輪郭を取り戻したその姿――それはさっきまでのDr.シマムラの姿ではなかった。それは……
「……え? どうして?」
(そ、そんな……嘘でしょう!?)
冷酷な目で自分を睨みつけてくるその姿を、蜜樹は驚きの目で見つめ、彼女の中のハニィも息を呑んで絶句した。
「……あなたの息を止めてあげるわ、スウィートハニィ」
彼女たちの前に立っているのは、パンツァーレディだった。