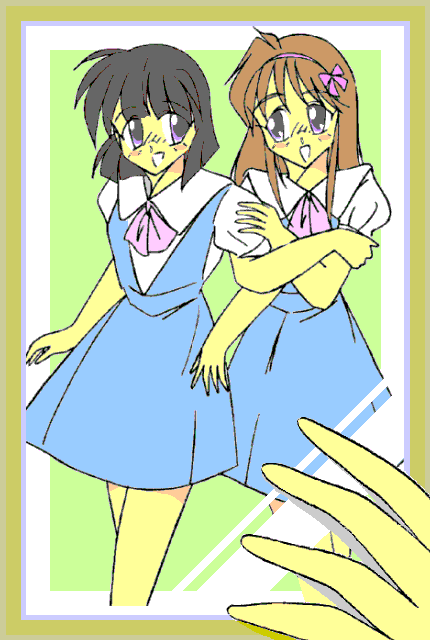
窓のまったく無い、機械とそのパネルだけが並んだ薄暗い部屋の中で、少女とエビの甲羅のような赤い甲冑をまとった女怪人が向かい合っていた。
赤い怪人の腹部には、真新しいX状の傷がついている。
「レッドバクスター、失敗したのか……」
「申し訳ありません。スウィートハニィを我が夢幻界に引きずり込んだのですが……」
「……しくじったというのか。お前らしくもないな」
「夢幻界は人間の夢を寄り代にして作る、我が意のままとなる世界。ですが、肝心の夢幻界がまるでコントロールできず……何者かわかりませんが、夢見の主はただ者ではありません」
「まあいい。ハニィを倒すことが目的ではなかったからな」
「シスター・ミク、それよりも面白いことがわかりました」
「面白いこと? 何だ?」
「スィートハニィの心の奥底には、かなりの迷いやストレスがあるようです」
「迷い?」
「自分の存在についての迷いと見受けられます」
「なるほど……あいつは他人の振り、教師なのに生徒の振り、男なのに女の振りをして暮らしているのだからな。おっと、今の私もそうか、きゃはははっ」
自分の言葉に、少女――シスター・ミクは甲高い笑い声を上げた。
「……で、そこに付け込んでみては如何でしょう? このような作戦は――」
「ふむ……ふむ……なるほど面白い……さすが心理戦に長けた夢使いだ。100%成功すれば、スウィートハニィを我が手先とすることも可能だな。……よし、やってみよ、レッドバクスター。但し、深追いはするなよ。今後の計画の遂行にはお前の能力が欠かせないからなっ」
「ははっ!」
戦え! スウィートハニィⅡ
第7話「悪夢の中のハニィ」
作:toshi9
「……はっ!?」
蜜樹が目を覚ますと、そこは自分のベッドの中だった。
外では小鳥のさえずりが朝を告げている。
体を起こすと、昨夜寝る前に着替えたピンクのパジャマを着ている。布団の中から右手を出して見てみると、指輪は無かった。
「……夢だったのか。でも、何てリアルな夢なんだ」
巨大な神殿のような場所で、『ネオ・虎の爪』の怪人と戦った夢。それも、マリアも変身して一緒に戦う夢……バトルスーツ姿で恥ずかしそうにハリセンを振るうマリアの姿が、蜜樹の脳裏に鮮やかに思い浮かぶ。
「あの怪人、確かファミレスの名前みたいな……そうそう、『レッドバクスター』って名乗ってたな。それに、マリアちゃんまでバトルスーツ姿に変身して、『スウィートシスターズ』なんて宣言して二人で戦ったんだ……でも何であんなことを口走ったんだ? 全く、変な夢だ……」
(夢の中では有り得ないことが起こっても不思議じゃありませんけど……でも先生、あれってただの夢なんでしょうか?)
「……どういうことだ? ハニィ」
(新しい『ネオ・虎の爪』の怪人の攻撃じゃないんですか? 注意してください、先生)
「ああ、わかってるさ……」
そうづぶやきながら、布団から身を起こす蜜樹。
その時、部屋の扉を開けて奈津樹が顔を覗かせた。
「蜜樹、起きてる? うなされていたみたいね。あたしの部屋まで声が聞こえてたわよ」
「え? そんなに?」
「うん……いろいろあったし、疲れているんじゃないの?」
「そ、そうかな……」
「あたしは授業があるから今から大学に行ってくるけど、もっとゆっくり寝ていたら? 停学っていっても気にすることないわ、誤解なんだから。お父さんが説明すれば、校長先生もわかってくれるわよ」
「ありがとう、奈津樹……姉さん」
奈津樹の姉としての気遣いがくすぐったい。
ベッドの上で目を伏せる蜜樹を、奈津樹はじっと見詰めた。
「蜜樹」
「え?」
「そのパジャマ、かわいいわよ。よく似合っている」
そう言って奈津樹は、いたずらっぽくウインクした。
「え? そ、そんな……」
恥ずかしさに思わず視線をそらす蜜樹。今着ているパジャマは幸枝が買ったものだ。「早く女の子に慣れなきゃ」と、半ば強引に思いっきりかわいらしいデザインのパジャマを着せられている。
「ほんとよ。もっと女の子として自信を持ちなさい、蜜樹。……じゃあね」
そう言って扉を閉めると、奈津樹はトントンと階段を下りていった。
「自信、か……」
(先生、どうしたんですか?)
「いや、生田蜜樹として、君として生きていくと決めたものの、女の子の暮らしってなかなか慣れないもんだなあって思ってね」
「あら? そうですか? 最近、随分馴染んできたなって思いますけど」
「そんなことないよ。さてと――」
ベッドから降りた蜜樹は、パジャマを脱ぐとドレッサーを開けた。
ドレッサーの内側についた鏡には、下着だけを身につけた自分の姿が映し出されている。
もちろん「如月光雄」の姿ではなく、こぼれんばかりの大きな胸を清楚な白いブラジャーで隠した、茶色い髪をショートカットにした少女だった。
「…………」
そう……これが今の自分なんだ。
見慣れてきたとは言え、改めてその姿にため息をつく蜜樹。
ドレッサーの中に掛かっていたハンガーから赤いセーターを外して頭からかぶり、続けて濃紺のスリムジーンズに脚を通して、ぐいっと引き上げる。
「全く、女の服って、どうしてこんなきついんだ……よいしょっと……」
ぴちっとしたジーンズをようやく腰まで引き上げて、ジッパーを閉めボタンを留める。
「今日一日は、家で大人しくしているしかないよなあ……」
(たまにはこういう日もいいんじゃないですか?)
「ハニィはのんきだな」
(先生、もっと気持ちに余裕があったほうがいいと思いますよ。そうでないと思わぬ失敗につながりますから)
「……なあ、ハニィ」
(なんですか? 先生)
「君は本当に高校生だったのかい? 時々俺よりずっと年上に思えることがあるんだけど」
(まあ、失礼ですね。でもあたしも生きている時には思いもしなかったようなことを思いつくことがあるんです。不思議ですね)
「ふーん」
自分の中のハニィと話しながら着替えを終えた蜜樹は、ゆっくりと机に座った。
教科書や参考書が並んだ机の上には、ノートパソコンと写真スタンドが置かれている。スタンドの中に飾られているのは、仲よく腕を組んだ蜜樹とマリアの写真だった。
いや、マリアと腕を組んでいる少女は今の蜜樹とはだいぶ雰囲気が違う。
幸せそうに微笑んでいるその表情だけではない。黒い髪、小ぶりな胸、そして着ている制服はマリアのものと同じだ。
「これが君なんだよな……俺と違ってほんとに女の子らしいし、かわいいよ」
蜜樹は写真スタンドを手にとって、しげしげと眺めた。
そう、写っているのは一年前の蜜樹……即ち、生きていた頃の本物の蜜樹の姿だ。
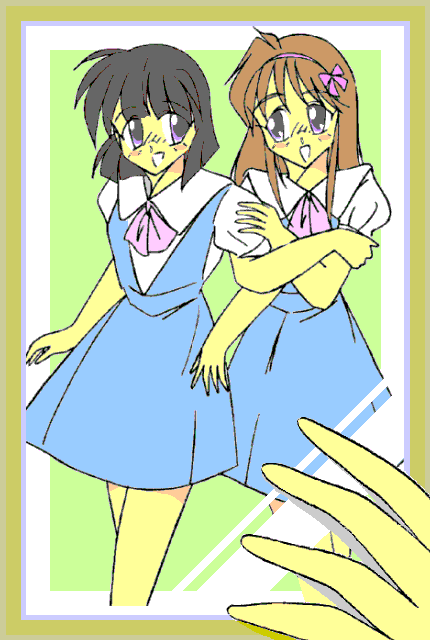
(当たり前ですよ。15年間女をやってきたんですから……でも先生、無理してあたしの真似をすることなんてないですよ。先生は先生、あたしはあたし、どんなに男っぽくてもがさつでも、今は先生が「生田蜜樹」なんですから)
「そうだな……って、がさつは余計だ」
(うふふ、ごめんなさい)
「ぷっ、あっははは」
(うふふふふ)
思わず笑い出す二人。
そこに、今度は幸枝が顔を出した。
「蜜樹、いつまで寝て……あら、起きてたのね」
「あ、お……おはよう、お母さん」
「ねえ蜜樹、今日はあたしに付き合ってくれない?」
「……え? 付き合うって?」
「お買い物に行きましょう。あなたの服を買いに」
「で、でも停学中に街を出歩くなんて……それに、お父さんがあたしのために学校へ誤解を解きに行くっていうのに、あたしのほうがそんな遊びに出るような真似をするなんて、できないよ」
「堅いこと言わないの。家の中で悶々としていても体に良くないでしょう。それにもうじき冬なのよ。今のあなたに一年前の服はサイズが合わないんだから、そろそろ冬物を買い揃えなくっちゃいけないでしょ?」
幸枝もまた母親として自分のことを気遣ってくれている。それをひしひしと感じる蜜樹だった。
それに幸枝の言うことももっともだ。スウィートハニィに変身したまま元に戻れなくなった今の蜜樹の姿は、本来の蜜樹に比べて胸もお尻も出るところは出、腰は反対にきゅっとくびれている。そのスタイルは高校生離れ、いや日本人離れしていると言ってもいい。
「ん~、わかった」
「決まりね、それじゃ食事が済んだら出かけましょう」
「あ、シャドウガールは?」
「デパートにペットは連れて行けないから、留守番していてもらわなくっちゃね」
「ペットねえ……でも仕方ないか。シャドウガールったら残念がるだろうな」
シャドウガールの「ハニィ、あたしも行きたいんだニャ~っ」と叫ぶ声が聞こえてきそうだった。
そして二時間後、蜜樹と幸枝は都内の某デパートのティーンズ向けの婦人服売り場にいた。
案の定一緒について行きたがったシャドウガールを何とか説き伏せて、二人だけてやって来たのだ。
「ほら、これなんかどう?」
幸枝が次々と蜜樹の前に服を持ってきては、試着するよう強要する。
しぶしぶ着替える蜜樹だが、これがまたどれを着ても似合うのだ。美人は何を着ても美人と言うが、そんな言葉が今の蜜樹にはぴったりかもしれない。
「スタイルがおよろしいんですね、とっても良くお似合いですよ」
「そりゃ、あたしの娘ですから」
新しい服に着替える度に、店員は熱意を込めて蜜樹を褒め、幸枝もにこにこと嬉しそうに答える。
「それじゃあ、これとこれ、包んでちょうだい。送り先はここにお願いね」
幸枝はさらさらとクレジットカードの伝票に記入すると、
「さて、次はっと……」
「え? 次?」
「ほら、行きましょう」
蜜樹を引っ張って次に向かったのは、ランジェリーコーナーだった。
そこにはピンクや水色、ベージュ……と、色とりどりのショーツやブラジャーが並んでいる。
「こ、ここは!?」
「ついでだから、下着も少し買っておきましょうね」
「買っておきましょうって、あ、あの……」
ジャングルの中に放り込まれた小うさぎのように、緊張感に体を固くする蜜樹。
そう、下着をつけたマネキンの間を歩く蜜樹にとっては、まさに赤や白のジャングルの中をさまよっている気分だった。
「お、お母さん、ちょっと待って――」
「さあ、試着してみなさい」
ピンクのブラジャーを胸に当てられ握らされ、蜜樹はフィッティングルームに押し込められる。
「はあぁ……まいったな……」
目の前の鏡には、恥ずかしそうにブラジャーを握り締めている自分の姿が映っている。
(先生、何を焦っているんです? これくらい大したことないじゃないですか)
「だって……こんな色っぽい下着を付けろなんて……」
(よく似合うと思いますよ)
「い、いや、そんな意味じゃなくて――」
「蜜樹、まだできないの?」
カーテンの向こうから幸枝が呼びかけてきた。
(ほら、お母さんが待ってますよ)
はぁ~っ。
蜜樹は仕方なくセーターを脱いでブラを外すと、新しいブラジャーを胸にあてた。そしてストラップを肩に通すと、背中でホックをパチリと留める。
「うっ……か、かわいい……」
フィッティングルームの鏡に映っているのは、下半身の見事な曲線を浮き上がらせたスリムジーンズをはき、上半身には大きな胸にぴったりとフィットしたかわいいブラジャーをつけた自分の姿だ。
童顔に似合わぬアンバランスな肢体が何とも色っぽい。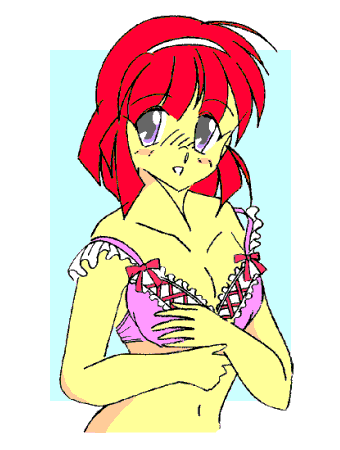
「あら、いいじゃない。ショーツもお揃いで買いましょう。」
「でも、これってちょっと派手……」
「そんなことないわよ。蜜樹も女の子なんだからもっとおしゃれに気をつかいなさい。下着だって変なものをつけていると、ボディラインが崩れるし、いざという時、男の子に嫌われるわよ」
「いざという時……男の子にって……」
自分の下着姿を他の男に見せる? 『いざという時』の情景を思い浮かべ、蜜樹は顔を真っ赤にした。
「冗談冗談。それじゃ蜜樹、それを包んでもらったら上でお昼にしましょう。評判のいいフランス料理店があるのよ」
「は、はい」
時計は既に12時を回り、空腹感を覚えていた蜜樹はこくんと頷いた。
何より眩いばかりのランジェリーに囲まれたこのジャングルから、一刻も早く脱出したかったのだ。
最上階のレストランフロアにあるフランス料理店に入ると、案内されたテーブルに座った幸枝はランチコースを注文した。
そして自分には赤ワインを、蜜樹にはジンジャーエールをと付け加える。
「あなたは一応未成年なんだから、アルコールは我慢してね」
「そんなの当たり前……あっ」
娘として扱ってくれていても、俺のことを気遣ってくれているんだ。
幸枝の言葉に くすぐったさと少しばかりの寂しさが、すっと蜜樹の心を吹き抜けていく。
やがて二人の前に、次々と料理が並べられた。
「おいし~い」
さすが評判に違わぬ美味しさだ。
前菜からメインディッシュに至るまで、一皿一皿に舌鼓を打つ蜜樹と幸枝。
食事の最後に、二人の前にケーキが出された。色とりどりのフルーツカットと生クリームを上にあしらったフルーツケーキだ。
「最後のこれがまたおいしいのよ」
「ケーキかぁ」
光雄だった時には甘いものはどちらかというと苦手だったが、蜜樹の姿になってからは甘いものに目がなくなっている。
そんな自分の嗜好の変化を不思議に感じながらケーキを口にする蜜樹だが、それにしてもおいしい。
幸せそうにケーキをフォークに刺して口にほおばる蜜樹の様子を見ながら、幸枝の表情もまた幸せそうだった。
あっという間に時間は過ぎていく。
二人が研究所に戻った頃には、もう夕方近くになっていた。
研究所に帰り着いて自分の部屋に戻った時、蜜樹の携帯が鳴った。
ディスプレイを見ると、電話の主はマリアだった。
『もしもしハニィ?』
「あ、マリアちゃん。……どう? 指輪の修復具合は」
『それが親父の奴、思ったよりも手こずっているみたいで。今日届けるというのは駄目みたいなんだです。一日でできるなんてエラそうなこと言っておきながらこのざまで、ごめんなさいです……』
「うふふ、たった一日で修理できるなんて半信半疑だったから、別にがっかりしてないよ」
『修復が終ったら、必ずあたしが届けるです』
「うん。桜塚教授に……お父さんに、よろしくお願いしますって言っといてね。 ……あ、そうだ、マリアちゃん」
『え? なんだですか?』
「あたし、昨日おかしな夢を見たんだけど」
『え? おかしな夢、ですか――?』
マリアは何故か、そのまま押し黙ってしまう。
「マリアちゃん、どうしたの?」
『え? ううん、何でもないです』
「夢の中で、神殿みたいな場所でマリアちゃんと一緒に『ネオ・虎の爪』の怪人と戦ったんだ。それも二人ともバトルスーツ姿に変身して。……ね、変でしょう?」
『その夢って……あたしが見たのと同じだです』
「同じ?」
『うん。あたしも同じ夢を見たんだです。「スウィートシスターズ」だったです』
「そ、そうよ、それそれ。それじゃあマリアちゃんも見たんだ」
『はいです。それに、親父の奴も……』
「桜塚教授も? そう言えば、夢の中に教授も出てきたような……」
『うん、親父の奴もあたしとハニィがバトルスーツ姿で出てきた夢を見たって言ってたんだです。にやけた顔で「お前のあの勇姿を写真に収めたかったぞ」なんて言うからぶっとばしてやったんだけど……親父の話もハニィの見た夢とそっくりだです』
「ふ~ん、じゃあ昨夜は三人で全く同じ夢を見たってこと?」
『そうなるです』
「……匂うな」
『え? 何が匂うです?』
「……カレーの匂い」
「陰謀の匂い」と言うところだったが、下から漂ってくるカレーの匂いにつられて、蜜樹は思わずそう答えてしまった。
『カレー?』
「あ、何でもない。『ネオ・虎の爪』の怪人の仕業かもしれないから、マリアちゃんも注意してね」
『わかったです。でももし変な奴が現れても、またハリセンのサビにしてくれるんだですっ』
「ぷっ。駄目よ油断しちゃ、ふふふ」
マリアの言葉に思わず笑い出す蜜樹。
『うふふふ、それじゃハニィ、明日また電話するです』
「うん、じゃあね」
やっぱり指輪は簡単に修復できないか。
マリアにがっかりしていないと言ったものの、電話を切ると、蜜樹は「はぁ~っ」と嘆息する。
「ハニィ、どうしたんだニャ?」
「シャドウガール、あなたそこで寝てたの?」
ベッドの中に潜っていたシャドウガールが這い出てきて、蜜樹に声をかけてきた。
「うん。この中って気持ちいいんだニャ。ところでハニィ、とってもいい匂いがするんだニャァ」
「カレーの匂いね」
「カレーって何だニャ?」
「日本人が一番好きな料理の一つよ。しかも誰でも簡単においしく作れるの」
「ふーん、確かに美味しそうな匂いなんだニャ」
シャドウガールがくんくんと鼻を鳴らす。
(……このカレーの匂い)
「どうした? ハニィ」
(この匂い、お父さんのカレーだ)
「え? それじゃお父さんが作っているの?」
台所に下りると、確かにエプロンをつけた賢造が、ガステーブルの火にかけられた鍋の中のカレールーをゆっくりとかき混ぜている。
「あ、ほんとだ」
「おや、お帰り」
台所に蜜樹が入ってきたのに気がついて、賢造が振り向く。
「お父さんが料理を作るなんて、一体どうしたの?」
「ああ、早く帰ってきたんで、たまには作ってみようかと思ってな。どうだ、今夜は久しぶりにカレーパーティをやらないか?」
「カレーパーティ?」
(お父さんったら、まさかアレを)
「アレ?」
ハニィに言葉に首をかしげる蜜樹。だがその謎はすぐに解けた。
「よし決まりだな、今夜は久々の闇鍋カレーだ、うーん楽しみだな」
「え? 闇鍋カレー?」
(生田研究所名物……というか、お父さんが大学時代からやっているそうです)
闇鍋カレーって、何なんだ?
そんな疑問を抱きつつも、蜜樹は気になっていた学校の様子について賢造に聞いた。
「お父さん、ところで学校のほうはどうだったの?」
蜜樹の問いに、賢造はぐつぐつと煮上がった鍋の火を止めてテーブルに座った。
そして真剣な眼差しで、蜜樹を見詰めた。
「校長先生の誤解は解けたよ。如月先生も校長室に来て『私の勘違いでした。お騒がせして申し訳ありませんでした』と私に謝まったぞ」
「あいつが謝ったんだ……」
監禁されていた――などど勘違いで言えることではないのに、あっさりと認めたところが腑に落ちない。
「偽者だとわかっていても、あの “如月先生”
が偽者だという証拠はどこにもない。だから今日は黙って聞いていたがな」
「そうですか。いずれにしても疑いは晴れたということは、明日から登校していいんですね」
「いや、明日までは登校を禁止された。行けるのは明後日からだ」
「ええ? どうして?」
「明日もう一度職員会議に諮るそうだ。校長の誤解が解けたと言っても、私らが如月先生を監禁していたという噂が校内でどんどん尾ひれがついて広がっているそうだ。一度燃え広がった火事は容易に消せんということだな」
「ふぅ~、そうなんだ……」
長い嘆息を漏らす蜜樹の肩を、立ち上がった賢造がぽんぽんと叩いた。
「気を落とすんじゃないぞ。まあ、試験休みのつもりで気楽にいるんだな」
見上げる蜜樹に向かって、「わかったな」とばかりにこくりと頷く賢造。暖かい笑顔だった。
「ありがとう、お父さん!」
そう言うや、蜜樹は賢造に抱きついて嬉しそうに体を密着させた。
抱きつかれた賢造は、驚きの表情を浮かべたものの、すぐに照れ笑いに変わる。
(先生、いやに積極的じゃないですか?)
(うん、俺も賢造さんと幸枝さんの二人に積極的に飛び込んでいかなきゃと思ってね。二人ともこんなに一生懸命になってくれているんだ。こっちが遠慮していると、いつまでたってもほんとの親娘になれないと思う。そうだろ?)
(ありがとうございます、先生)
そこに幸枝が顔を出す。
「あらあら、あなたったら何を嬉しそうにしているんです?」
「蜜樹がこんな風に私に抱きついてきたのは、いつ以来かなと思ってな」
「あら、そんな昔だったの?」
「ま、まあな……」
「ふ、うふふっ」
「あっははは」
台所は、しばし三人の笑いに包まれていた。
夕食のカレーパーティは、賢造と幸枝、宝田をはじめ研究所に居残っている数人の職員、そして奈津樹と蜜樹とシャドウガールが参加した。
各々が持ち寄った食材をカレーの中に放り込んで煮上げる。そして鍋からカレールーと一緒にすくい上げたものは、必ず食べないといけないルールだ。
「ゲッ……これって、鯖?」
「あ、それあたしが入れたんだニャ」
「カレーに魚か……あ、でも意外に合うじゃない」
鯖カレー……意外な取り合わせだが、美味い。
千葉県民は知っている事実だが、それはまた別なお話。
「こ、これは?」
「うはっ、こんにゃくだ!」
「げ……トマトが丸ごと入ってる」
「ありゃ? なんだこの細い……きんぴらごぼうだ!」
「こっちも細長いんだニャ」
「それってソバじゃない?」
「うひゃあ、これを食べるんですか? 勘弁してくださいよ~」
「だ~め、ルールはルールよ」
次々とルーの中から姿を現す怪しげな食材。その度に室内は次々と歓声に包まれる。
夜更けまで、わいわいと盛り上がる研究所の一同だった。
(こんなに楽しいパーティ、いつ以来だろう……)
パーティがお開きになったその夜のこと。
部屋の机に座ったままうたた寝していた蜜樹がはっと目覚めると、辺りの様子がおかしいことに気がついた。
自分の部屋でうたた寝していたはずなのに、座っているのは部屋の机ではなく、教室の机だ。
見回すと、そこは教室だった。
「あれ、いつの間に学校に来たんだっけ?」
キョロキョロと教室内を見回す蜜樹。だが中には蜜樹以外誰もいない。
「変だな、部屋の中だったはずなのに……こほん、あれ? 声が」
妙に声が低い。それは蜜樹の声ではなく懐かしい声だった。そう言えば体の様子もおかしい。
机の上に投げ出していた腕は、制服のではなく白いワイシャツに包まれている。そして椅子に座った下半身はスカートではなくズボンを履いている。
そして胸にはリボンではなく、紺のネクタイを締めていた。
ぽんぽんとシャツの上から胸を触ってみると、そこは平たく、存在感を示していた巨乳は跡形も無くなっていた。
慌てて立ち上がって教室の後ろに備え付けられた鏡に駆け寄り自分の姿を映すと、そこには蜜樹の姿ではなく、如月光雄の姿が映っている。
「俺だ! 元に戻ったんだ!」
そう言って、ぽんぽんと顔を叩く光雄。
そう、蜜樹は元の男の体に、如月光雄の姿に戻っていた。
「間違いなく俺の体だ……でも、いつのまに元に戻ったんだ? それに生徒たちはどうしたんだ。相沢は? 桜井はどこにいる?」
時計は昼休みの時間を指している。だが不思議なことに、光雄の他には誰も教室にいない。
ガラガラ
突然教室の扉が開くと、一人の女子生徒が入ってきた。
それは桜井幸だった。
「おお、桜井じゃないか」
幸は光雄の姿を見止めると、嬉しそうに駆け寄ってくる。
「先生!!」
だが光雄に抱きつこうとした寸前、突然その足がぴたりと止まる。
「桜井、どうしたんだ?」
「いやっ!」
幸の表情に困惑と嫌悪の色が浮かぶ。
「先生って変態だったんですね」
「え? 変態? お前何を言って……」
「先生、どうして先生は女子の制服を着ているんですか?」
「え? 女子の制服だって?」
気がつくと、さっきまでのズボンの感触が消え、股の間をスーッと風が通り抜けている。
ズボンは、いつの間にか短いプリーツスカートに変わっていた。
ワイシャツも女子制服のブラウスに変わり、胸には巨乳がこんもりと盛り上がっている。
慌てて脇の鏡を見る光雄。
そこに映った光雄の姿は、首から上は光雄のままなのに、首から下は女子の制服を着た女の子の体に変わっていた。
胸は大きく膨らみ、腰はきゅっと細い。
それは蜜樹の体だ
「そんな! どうして!?」
大きな胸を両手で押さえ、そしてプリーツスカートを摘み上げて蒼ざめる光雄。
「あなたなんか先生じゃない!」
じりっと後ずさる幸
「え? 俺だ、俺だよ、桜井」
「俺って誰よ」
「俺だ、如月光雄だ」
「何言ってるのよ、あなたはハニィじゃない。そっか、ハニィの正体って先生だったんだ。先生が今までハニィに化けていたんだ。そしてあたしたちをだましてたのね」
「え? あっ!」
顔を抑える光雄、いや、その顔も既に蜜樹の顔に変化していた。
そう、光雄の姿は、いつの間にか蜜樹の姿に変わっていた。
「桜井、ちょっと待ってくれ、違うんだ。誤解だ」
「何が誤解よ。近寄らないで! いやらしい。あたしを、クラスメイトを今まで騙して、女子生徒に変装して着替えを覗き見するなんて変態じゃない」
「ち、違う、俺はそんな……」
抗弁しようとする光雄だが、そんな光雄を幸は白い目でじっと睨みつけている。
そしてその時、教室に相沢謙二を先頭にクラスの生徒たちがぞろぞろと入ってきた。
「そうか、やっぱりそうだったんだ」
「え? あ、相沢」
「おかしいと思ってたんだ。転校生なのに妙に俺たちのことを知っているし、男っぽいし」
男子生徒も女子生徒も、幸と同じように光雄を白い目で睨んでいる。
「先生って変態だったんですね。女子生徒に化けて僕たちを騙すなんて、信じられない」
「うわぁ、こんな奴の授業を受けていたなんて、いや、こんな奴が今まで俺たちのクラスメイトでございって顔していたなんて。きもいぜ」
「ハニィ、あなたの正体が先生だったなんて」
「違う、みんな、これは違うんだ」
その声も最早蜜樹の声に戻っている
そんな蜜樹を取り囲むクラスメイトたち。
「変態! 変態! 変態! 人間のクズ あんたなんか死んじゃえばいいんだ」
「そうだ、よくも俺たちを騙していたな」
「許せないよな」
前後左右から蜜樹を容赦なく糾弾する生徒たち。
「違うんだ、みんな、聞いてくれ」
「汚らわしい、女子の中に混じってあたしたちの着替えを覗いたり体に障ったりしてたのね。この変態教師!」
「違う、違う」
ぐるりと取り囲んだ生徒達に蜜樹は罵倒され続けた。
「違うんだ、みんな、俺は正義の為に戦ってたんだ」
「何言ってるの、そんなの詭弁じゃない。そんな大きな胸なんかしちゃって、そんなかわいい顔して、でも中身は男。うげぇ、変態そのものじゃない」
「なりたくてこの姿になったわけじゃ……」
「そんなかわいい姿なのに、なりたくてなったわけじゃない? 信じられないな」
生徒たちは口々に光雄を非難する。
堪えきれなくなった蜜樹は、両手で耳を塞いで座り込んだ。
「う、うわぁ~~~」
(先生……)
「は、ハニィ、何でこんなことになったんだ。助けてくれ」
(先生ってやっぱり変態さんですよ。戻れなくなったのをいいことに、あたしの体で着替えたりお風呂に入ったり、いろんなことを……この変態!)
「は、ハニィ」
(先生なんか……死んじゃえっ!!)
「……!!」
ハニィまでもが?
頭の中で囁かれるハニィの声に、蜜樹の、いや光雄の精神は限界を超えた。
蜜樹はその場にがくりと両手両膝をついてうな垂れた。
そしてそのままの格好で固まってしまう。
真っ白な灰になったように。
突然教室が真っ暗になると、スポットライトが蜜樹を照らした。
そこは教室ではなく、コンサートホールの舞台に変わっていた。
今までいた筈の生徒たちはどこにもいない。舞台にいるのは固まったままの蜜樹だけだった。
だが蜜樹は周囲の変化に気づくことなく、ぴくりとも動かない。
「ふふふ、遂に心を閉ざしたな。後はお前を消し去ってしまえば、スウィートハニィの体はもう心を持たぬ抜け殻だ。そしてこれからは私の、いや『ネオ・虎の爪』の忠実な操り人形になるのさ」
舞台袖から、赤い甲冑を身にまとった女怪人・レッドバクスターが舞台中央に出てくる。
「ふふふ、これはお前の悪夢を元に作った夢幻界。何でも私の思うがままさ。全て私が囁いていたとも知らずに……馬鹿な奴だ」
うずくまった蜜樹の後ろに立ち、ほくそ笑むレッドバクスター。
「スウィートハニィ、覚悟!」
レッドバクスターの手が鋭い鋏状に変化し、その腕が蜜樹に向けて振り上げられた。
だが、蜜樹はうつろな瞳で一点を見つめ、動こうとしない。
絶体絶命!
だがその時、ホール内に大音声が響いた。
「止めなさいっ!!」
「……!! だっ、誰だ!?」
振り上げた腕を下ろし、舞台上からきょろきょろと観客席を見回すレッドバクスター。
すると観客席の一番奥の扉が突然開き、そこから人影が一人、中に入ってきた。
カツーン、カツーン……
観客席の階段を、一歩一歩ヒール音を響かせて、ゆっくりと下りてくる黒いシルエット。だがその姿は誰なのか、薄明かりの中でよくわからない。
「この夢幻界にはスウィートハニィ以外、誰も引き入れていない筈なのに…………き、貴様は誰だ!?」
レッドバクスターは狼狽えて、舞台に歩み寄ってくるシルエットに向かって叫んだ。
シルエットの人物の口から、真っ白な歯がこぼれる。
「ある時はかわいい女子高生。
またある時は先生の良きパートナー。
しかしてその実体は……愛と正義の戦士スウィートハニィ!!」
スポットライトが声の主を照らした。
そこにはプラチナフルーレを高々と振り上げた、真っ赤なバトルスーツ姿のスウィートハニィが立っていた。
「なっ、何っ? スウィートハニィが二人だと!?」
目の前でうずくまったままの制服姿の蜜樹と、観客席に立つスウィートハニィを見比べ、レッドバクスターは混乱した。
ハニィは客席から、うずくまったままの蜜樹に声をかけた。
「先生、しっかりしてくださいっ! 先生はレッドバクスターの術中にはまっているんですっ! 負けちゃだめですっ!!」
「……!!」
はっと顔を上げる蜜樹。その視線の先で、スウィートハニィが微笑んでいる。
「……ハニィ? ……まさか、ハニィなのか?」
「そうですっ。先生、言ったでしょ? あたしたちいつも一緒だって。先生の夢の中でなら、あたしはこうして実体化できるんです」
そう言って、もう一人のハニィは大きく頷いた。
「さあ戦いましょう。指輪があるって念じてください」
「指輪……だって?」
「そうです。ここは先生の夢の中。先生の願いは何だって叶うんですよっ」
「そうなのか?」
「信じるんです。願いは叶うと」
蜜樹は自分の右手を差し上げてじっと見詰めた。その薬指には、既に指輪がきらきらと輝いている。
「ほんとに指輪が……よし!!」
蜜樹は指輪を胸に当てて叫んだ。
「ハニィ・フラアアアッシュ!!」
叫ぶと同時に蜜樹の体が光り輝く。その光の中で蜜樹の着ていた制服が粉々になった。
一瞬裸になる蜜樹……だが、彼女を輝く空気がまとわりつき始めかと思うと、新しい服が形成されていく。
下半身は黒いスパッツで覆われ、両手と両足を白い手袋とブーツが包み込む。同時に上半身全体を赤い生地が覆っていく。
そう、彼女の見事なボデイラインを浮き出させたそれは、赤いレオタード様のバトルスーツだった。
その手には細身の剣、プラチナフルーレが握られている。
「とおっ!」
蜜樹が変身し終えると同時に、観客席にいたハニィは大きくジャンプして空中で一回転すると、トンと軽い靴音を立てて舞台に降り立った。
「今度こそ逃がさない。見るがいい、ハニィ、剣の舞!!」
ハニィはプラチナフルーレの剣先を、目にもとまらぬ速さでレッドバクスターに繰り出した。
「う、うぬぅっ!!」
連続して繰り出される剣先を、鋏でかろうじて受け流すレッドバクスター。
プラチナフルーレと鋏のぶつかり合う金属音が、ホール内に響く。
「いっけぇぇえええっ」
ハニィが渾身の突きを繰り出し、レッドバクスターはたまらず両手の鋏でそれを受け止めた。
「さあ先生、今です!!」
「よしっ、いくぞっ!!」
蜜樹はプラチナフルーレを中段に構え、裂帛の気合で叫んだ。
「光武流奥義、桜・華・天・翔っ!! てやあぁああっ!!」
蜜樹はもう一人のハニィと切り結んだままのレッドバクスターの脇を、つむじ風のように駆け抜ける。
プラチナフルーレの剣先がレッドバクスターの甲冑を一閃、次の瞬間レッドバクスターの甲冑は真っ二つに切り裂かれた。
「……お、おのれぇっ! こ、この私が夢幻界での戦いに、敗れる、などどは…………も、申し訳ありません、シスタ……ぐばぁっ!!」
真っ二つになったレッドバクスターの体は、塵状になって消えてしまった。
「やった!!」
蜜樹の指からも指輪が消える。同時に変身も解け、蜜樹の服は元の制服に戻ってしまった。
その蜜樹に、もう一人のスウィートハニィが笑顔で向かい合った。
「ハニィ、君は……」
「嬉しいです。こうして先生とお会いできるなんて……もしかしたらあの怪人に、ちょっと感謝しないといけないかな? でも、あたしはもう……」
そう話しながら、ハニィの姿はぼやけていく。
「は、ハニィっ! 待て、待ってくれっ!!」
「大丈夫、心配しないで。あたしたちは、ずっと一緒――」
「……はっ!?」
蜜樹が目を覚ますと、そこは自分のベッドの中だった。
外では小鳥のさえずりが朝を告げている。
「……い、今のは? 今のもまた全部、夢だったのか?」
(はい。あの赤い怪人が、先生の夢を使って先生の心を潰そうとしてたんです。危ないところでした)
「何て恐ろしい奴だ……全くひどい悪夢だったよ。ハニィ、ありがとう」
(ふふっ、どういたしまして)
「でも夢の中とはいえ、君に会えてよかった」
(あたしもです)
蜜樹は、自分とは違う本物のハニィの勇姿を心の中にしっかりと焼き付けていた。
一方その頃。
「くそう……あれほど深追いはするなと言ったのにっ。レッドバクスターめっ、功を焦ったかっ」
「申し訳ありません」
夜が明けても戻ってこなかったレッドバクスター。
シスター・ミクは烏――いや、クロウレディに当たり散らしていた。
「奴は今後の計画を進める上で欠かせぬ手駒だったのにっ、くそっ!」
「シスター・ミク、次のご指示を」
「う、うむ。済んだことを悔やんでも仕方ない。……とにかく指輪だ。壊れたものでもいいから、必ず手に入れろっ」
「全力で探査いたします」
「それから戦力の揃わない今、これ以上怪人を失う訳にはいかん。パープルカメレオンには指示があるまで動くなと伝えておけ」
「はっ」
「ブラックピジョン、新基地は完成したのか?」
「準備は整いましてございます。いつでも稼動できます」
「よし、早速新基地に向かえ。そして怪人どもの集結を急ぐのだっ」
「ははっ!」
シスター・ミクの声とともに、トレーラーがゆっくりと動き出す。そして、それは朝靄の中、いずこともなく走り去っていった……
「うふふっ……待ってらっしゃい、スウィートハニィ」
(続く)