|
この世の中には実に様々な人がいるもの。この世に新しく登場する人もいれば、この世を去らなければならない人もいる。今日できることは今日のうちにやる人、明日でもいいと延ばす人。世の中に存在する人たちの環境は常に矛盾することばかりが取りだたされていると言っても過言では無い。
そう言うわけで、自分の人生について数多く悩み続ける一人の男がここにいる。悩みに悩んで生きているせいもあってか、いつも彼の表情は暗く、友達もほとんどいない彼。一生をこのままで終わらせてしまってもいいものかと、思うには思ってもなかなか前へ進む気力すら無いとのこと。
前向き思考が流行ると、前向きに生きたいと思うのですが、長続きせずに終わる。自己啓発の本を読んではそのたびに自分をよくしようと励みますが、3日どころか1日も持たないのが彼の特徴。とにかく精神をよい方向に持って行く持続力が足りないと言うのが、結局現在の彼を作ってしまったのだろう。
ところが、その彼に突如としてある変化が起きた。彼が生きる希望を見つけたかのごとく、毎日を楽しそうに過ごしているではないか。あれほど精神力溢れる彼を見たことがあったのか?友人がいない彼にとってその変化に一番気づくのは会社の同僚たち。会社の中でもその噂が一気に広まり、どうしてこうなったのか調査を始めることになった程。この変化は彼のこれからを、そして周辺の環境を大きく変えるものとなるのですが、その切っ掛けはちょうど1週間前にさかのぼります。
ここは彼の会社があるビル。彼の会社はここの15階にあります。そのため、昼休みが終わる時間にはここのエレベーターがものすごい混むのは有名な話でした。15階まで行くのがまるで朝のラッシュのような状態で、とても気分のいいものとは言えませんでした。
「桜井さん。桜井さん」
1階のロビーでエレベーターを待っていると後ろから声をかけられたのは、桜井文恵(さくらいふみえ)だった。モスグリーンのベストにタイトスカートと、それに肩まで伸びた髪と言ったいでたちの彼女は、先に紹介してた彼と同じ会社に勤めている。声をかけた主は柴田潤蔵(しばたじゅんぞう)と言って文恵のいる総務課の課長。
「やあ。桜井くん。昼休み終わるといつもここで会うよね。今日は彼女たちと一緒じゃなかったの?」
「えぇ。今日は恵美(めぐみ)たちとは時間が合わなくて一人で食事をしに行きました」
「えっ?一人で行ってきたの?君にしてはめずらしいよね。昼ご飯は必ず誰かと一緒に食べないと気が済まないって言ってたじゃない。入社して初めてじゃないか?」
どうやら、いつもと違う文恵の行動に潤蔵は興味津々のようです。
「課長。私だって時には一人で食べますよ。子供じゃあるまいし」
「そうか。それだったら、さっき言ってくれたらよかったじゃないか。たまには一緒につきあってやるから」
「いや、課長とはやめときますよ」
そうして、文恵は潤蔵との目線を外した。
「どうして?今度、一緒に飲みに行くのだっていいじゃないか。奢ってやるから」
「そう言われても駄目なんです」
「なんで……」
そう言っているうちにエレベーターがいよいよ到着した。
「課長。エレベーター来ましたよ。先に乗りますね」
そう言って文恵は先にエレベーターに乗ってしまった。いつもの文恵だと「課長が先に乗ってください」と言ってくれるのに、さっきから妙な胸騒ぎがしてしょうがない潤蔵だった。
エスカレーターの中には予想通り多くの人が乗ったが、いつもよりも混んでいなかった、文恵と潤蔵はエレベーターの一番奥の隅に向かい合っていた。混んでいないとは言っても文恵の胸が潤蔵の目の前に迫ってくるのはいつ見ても快感だ。潤蔵が話を仕掛けてきたのはこれを狙ってのことと言うのも考えられるのです。
潤蔵の目の前にはモスグリーンのベストを膨らませる文恵のふくよかな胸があるのだから、男性ならどんな人でも興奮してしまうものなのかも知れない。しかも、それが自分の部下だとしたら更にだ。文恵からはかすかな香水の匂いがしている。2人の間には沈黙の時が流れるが、こうしているうちにお目当ての15階へと停まりました。
エレベーターから降りると文恵は、紺のパンプスから右足を出して、前屈みをする姿勢で手を使って揉み始めた。
「やっぱり、まだこの靴慣れてないなぁ」
独り言で言ったつもりの文恵だったが、その声は潤蔵にも聞こえた。
「その靴、今も慣れてないって?やっぱ、今日の桜井くんはどうかしてるね。医務室にでも言って休んできていいんだよ」
「大丈夫です。ちょっと足がむくんだだけなので、すぐに午後の仕事を始めます」
そう言って、文恵は再びパールホワイトのストッキングと一緒にパンプスの爪先に足を入れ直した。
「じゃあ、午後の仕事頑張ろうか」
そう言いながら潤蔵は先に会社へと入って行った。
潤蔵は昼休みが終わってから席に着くときに、お茶を自分で汲んでくるのが日課だ。自然と体が覚えてしまったためか、給湯室へ入ると手際よく自分のお茶を湯飲みに入れて自分の席へと運びました。そこに座ったとき潤蔵は不思議なことに気づきました。いつもは自分から見て右側にいるはずの桜井文恵が左側に座っているではありませんか。そこの席はこの物語の主人公となる田口康夫(たぐちやすお)の席。桜井文恵が席を間違えるなんてことはするはずが無いのですが、パソコンを開いて熱心に中身を見ているようなので、何か頼まれ仕事が入ったのかと聞いてみることにしました。
「桜井さん。田口くんから何か仕事を頼まれたかい?」
そう言われた文恵は顔を真っ赤にして言いました。
「あっ、いつもの癖でついこっちに座っちゃいました。私の席は反対ですよね」
これまた桜井文恵の行動にしてはおかしな行動だった。そして、潤蔵が目を机にやると田口康夫の欠勤届が出ていた。
「おい、これって。桜井さ〜ん、田口くんはどうしたの?」
「あっ。田口さん、ものすご〜く体調が悪かったみたいで、先に帰りましたよ。課長いなかったので私が代わりに受け取りました」
「代わりにって……まぁ、いいよ。今日は桜井くんもちょっとおかしいみいたいだから、急いでやる仕事も無かったから幸いだよ」
こうやって午後の仕事がはじまると、田口康夫がいないのを除くといつもと同じような感じだった。しかし、このときから田口康夫を取り巻く環境の何かが違っていたのです。
こうやって午後の仕事がはじまると、田口康夫がいないのを除くといつもと同じような感じだった。しかし、このときから田口康夫を取り巻く環境の何かが違っていたのです。
午後の仕事はいつものように始まった。総務課長である柴田潤蔵はいつもよりも1人少なかったためか忙しかった。田口がやるはずの仕事までやらなくてはならなかったからだ。そんな潤蔵の目からは桜井文恵はいつものように仕事をしているように見えていた。
そうやって終業時刻を迎えた。潤蔵は今日の分の仕事を終え帰り支度を始めたが、文恵はなぜかまだ終わらないようだ。残業をするようなことは嫌いで、いつも終業時刻になるとすっと帰っていくというのに、今日はどういう風の吹き回しだろう。文恵の様子が午後になってからおかしい、何があったと言うのか?疑問になることはあっても、潤蔵は珍しく文恵よりも先に帰宅をした。
文恵が帰り支度を始めたのは潤蔵が帰ってから少しあとのことである。実は隣の会計課にいる後藤恵美(ごとうめぐみ)の仕事が終わるまで待っていたのだ。実は午後の仕事の途中で恵美からメッセンジャーで夜のお誘いが入っていた。そのために、いつもは先に帰ってしまう文恵が恵美の仕事が終わるのを待っていたという。
恵美の仕事が終わると文恵にまたもメッセンジャーで先に更衣室で着替えて欲しいとメッセージを送っていた。文恵はそれを合図に13階にある更衣室へと移動した。女子更衣室はなぜか二つ下の階にある。15階ワンフロア全部が文恵の会社なのだが、部署が多くなって社員が増えた。そのためたまたま13階にちょうどいい大きさのスペースが空いたためにそこに更衣室をつくったのだ。
13階の更衣室は男女に分かれていて女子更衣室の方が大きくなっている。女子更衣室に先に着くといつもよりも時間が遅いためもあってか誰もいなかった。するとなにやら嬉しそうな表情で自分のロッカーを開いた。どこの会社にでもある普通のロッカーだが、それを開くと、そこには文恵の私服や通勤用に使っているカバンと青色のヒール6cmのパンプスが置いてある。化粧品もここに置いてあるのだが、文恵はまずその中に入れてある小さな瓶を取り出した。
手の中にすっぽりと入ってしまいそうな小さな円筒形の小瓶だが、化粧品の試供品が入っている入れ物と同じくらいの大きさ。この円筒形の小瓶は透明な素材でできているので、中に入っているものがわかるようになっている。そんな小瓶を取り出してロッカーにある椅子の上にそっと置いた。
それから、文恵は私服に着替えを始めた。そして、不思議なことに時々小瓶の方を見ては口元を緩めて笑っていた。何がおかしいというのだろうか、文恵は私服に着替え終わると、ロッカーの入口にある姿見に映し出される自分の姿を見ながらうっとりとしていた。
「これが、文恵さんの私服姿なんだね。想像していた以上にとてもきれいだよ」
文恵は独り言を言っているのだが、さっきの小瓶に向けて言っているように見える。すると、小瓶がカタカタと揺れている音がした。
そのあとで、文恵は椅子に座りさっきの小瓶を右手に持って眺めている。中に見えるのはなんだか小さくて可愛いものだ。人形のようにも見えるがもっとリアルにできている感じがする。それもそのはず、小瓶の中にあるのは紛れもなく人間の姿だったのだ。そして、それは桜井文恵の姿にそっくりでなんと裸の状態だった。
|
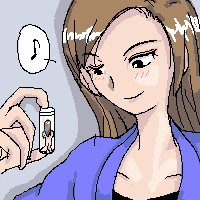
|
|
|
(絵:あさぎりさん)
|
|
「こんな姿になっても文恵さんはやっぱり可愛いよね」
文恵は小瓶の中にいる文恵に向かって話かけている。
「この瓶は小さいけれど僕に大きな力を与えてくれたよ。まずは君を使って試したけれど。最初に餌食になってくれたので、特別にこの仕組みを教えてあげよう。まぁ、どうせ僕の正体を知らないからね」
ここまで言ったときに、携帯の着メロが鳴り出した。着メロを聞くだけで恵美からメールが入ったのがわかる。メッセージの内容は「思ったよりも時間がかかって、早くても10分かかるよ。ゴメンね。待っててくれる?」だった。すかさず文恵は慣れた手つきで返信メールを打っていた。内容は「わかった。待ってるよ」の簡単なものだった。
文恵は小瓶の中にいる文恵に軽く笑ってからさっきの話を続けた。
「君がこうなったのはもちろんこの小瓶のせいだよ。この小瓶の威力でこうなっている。もちろん僕もそうさ」
ここで文恵は呼吸を置き、話を続ける。
「最初はこの小瓶が空の状態を考えてみて欲しい。この場合は何も起こらないが、ふたを回転させて開いてからすぐそば(この定義はまだ未解明)にいる人の名前を呼ぶだけで、名前を呼ばれた人が小さくなりながらこの中に入ってしまうんだ。身につけていたものは小さくならないので、その場に残されるよ」
小瓶の中にいる文恵は恐怖と激怒によって発狂しそうな状態に見える。
「ふたを軽く閉めるだけで中に入った人は出られなくなるけれど、完全に閉めるとそのふたを閉めた人がその中にいる人に変身してしまうんだよ。完全に閉めるまではその名前を呼ばれた人は気を失っているので、隠れたところで使えば誰がやったのか正体がわからないってわけ。変身した時に服はそのままになるので着替える必要があるけれど、中に入った人の身につけていたが残されているので、それを着てしまえばいいわけだね。仮密閉と完全密閉に時間差を付ければ、いつでも好きな時に変身ができるってわけ。だから、これを使って僕は君、そう桜井文恵になったんだ」
ということで、小瓶の中にいる文恵が本当の桜井文恵だったのだ。
「小瓶の中にいる小さな文恵が本当の桜井文恵で、女子更衣室の中にいる大きな文恵は実は偽物なんだけど、誰もそんなの疑うことがないように、この小瓶がすごいのは、変身するとその人の能力も記憶も使えることだね。もちろん元の状態に戻すにはこの逆をやればいいってわけ」
そう言うと、小瓶の中にいる文恵には何をやるにも力が無くなってしまったようだ。
「あっ、そうそう。小瓶の中にいる間は何も食べなくても生き続けられるよ。シャワーを浴びなくてもきれいな状態に保たれるし、小瓶生活も結構快適なものだよね」
そう言うと、今度は携帯電話から音楽が流れてきた。
「あっ。恵美?ようやく終わったの?早く来てよ。ずっと待ってるんだから。うん、わかった。すぐに来てね」
恵美から電話がかかってきたのだ。悔しいけれど、小瓶の中にいる文恵が聞いても自分と全くそっくりだった。誰が私になりすましているのかわからないけれど、今朝まではこんなことになるなんて思っていなかったのだ。小瓶の中にいる文恵はすっかり絶望の淵まで追いやられていた。
「今日ね〜。恵美と飲みに行くの。あなたが行きたかったでしょうけど。私が行ってくるからね。とりあえずは、かばんの中に入れてあげるから、あなたも一緒にいけるわね」
そう言いながら、偽の文恵は本当の文恵が入った小瓶を自分のカバンに入れ、青のパンプスに履き替えて、あと少しで恵美が来るのを待っていた。
恵美が最後の仕事を終えると文恵に電話をかけた。
「文恵。今終わったところ。早く行くからね。待たせてごめんなさい」
そうやって電話を切ると階段を使って13階まで降りた。2階程度の移動はエレベーターを使うよりもずっと早いからだ。恵美は勤務を終えたばかりなので、モスグリーンのベストにタイトスカートの格好は文恵と同じだった。ただ、恵美の方がちょっとスカートの裾が短いように見える。足下に気を付けながら一段一段小走りの感じで降りて行くのだが、会社の中で履いているサンダルでは精一杯の力で駆け下りても遅くなってしまう。
そんな恵美を待っている文恵は、女子更衣室の入口にある大きな鏡の前で自分の姿を眺めていた。青いカーディガンにひざ上丈の白いタイトスカート、パールホワイトのストッキングには青のパンプスが光っている。肩まで伸びた髪は軽く赤茶色に染めているようだ。恵美は身だしなみのチェックしながら恵美がやってくるのを待っている。文恵は大きな鏡の前で何度かポーズを決めてみるのだった。そんなことをしているうちに女子更衣室のドアが開いた。もちろん入ってきたのは後藤恵美である。
「文恵。こんなに遅くまで待たせて、ごめんなさいね」
左腕にはめてある時計に目をやりながら恵美は文恵に言った。
「ん。私は全然気にしてないよ。これから恵美と飲みに行くんだから」
そう言うと、文恵は口から舌をペロッと出して笑って見せた。すると、2人の笑い声が女子更衣室の中に響いた。
恵美が着替えいる間に、文恵はトイレに行くことになった。文恵は女子更衣室を出ると、パンプスをコツコツと鳴らしながらトイレの前まで来た。赤いマークを確認してから中へ入ると一番奥にある個室にノックをして入る。文恵はふたをしたまま便座の上に腰をかける。カバンの中からさっきの小瓶を取り出すと、小瓶の中にいる本物の文恵に向かって微笑んだ。
「どうだった?恵美には本当の文恵にしか見えていないでしょう。私って完璧ね」
小瓶の中にいる本物の文恵にこっそりと話かけると、カバンの中に再び小瓶をしまい用を足した。個室から出て洗面台の前に立つと、カバンの中から化粧道具を取り出す。文恵になってから化粧直しはまだやっていなかったが、これから夜の街にでかけることを考えるとそれを意識してちょっと濃い目のメークを始めた。
メークをしている途中で誰かがトイレに入って来た。恵美が着替えを終えてやったきたのだ。ベージュのカーディガンにブラウンパンツ姿、黒いパンプスを履いた恵美は制服姿よりも大人っぽい雰囲気を醸し出している。
「文恵。私、準備できたよ。あれぇ。今日のメークはずいぶんと気合いが入ってるのね」
文恵は目元に筆を入れながら恵美に話し返す。
「そうかな?ちょっと今日は騒ぎたいだけ。金曜日の夜だからゆっくりできるでしょ」
すると、恵美も横に並んで化粧の確認をはじめた。文恵よりも長くてパーマのかかった髪の毛は茶色に染めてある。こうやって2人は夜の街へ繰り出す前に念入りにチェックをした。
トイレから出て来てエレベーターの前に立つと文恵が「下」のボタンを押した。ちょっと待っているとエレベーターがやって来た。エレベーターには恵美の上司の大塚大和(おおつかやまと)課長が一人乗っていた。
「あれっ。後藤さん。それに、桜井さんだね。夜遅くまで頑張ってるね。ご苦労様」
大塚課長は2人をねぎう言葉をかけた。
「課長は今日も残業なんですね。ご苦労様です」
「いやぁ。たいしたこと無いよ。年度末の決算が終わって、ちょっと一息ついたからね。後藤さん。もしかして今日は桜井さんと一緒に飲みに行くのかい?」
大塚課長は恵美と文恵の私服姿をじっくりと見ながら言ってくる。
「そうなんですけど。わかりました?」
こんな風に話している間にエレベーターは1階へ到着した。ドアが開いてすぐの所に3人が降り立つ。
「まぁ。2人で楽しんで来なさい。俺はもう少しやることがあるので、それじゃ」
そう言うと、1階にあるコンビニへと大塚課長は向かう。残業をする時にはいつもこうやってコンビニに行くのが日課のようになっているのだ。大塚課長がいなくなって再び2人きりになる。
1階のロビーはシーンとしている。まだ勤務時間が過ぎて1時間ぐらいしか経っていないと言うのに。ビルの外に出てからどこに行くのか話を始めたがなかなか決まらない。恵美が行きたい店と文恵の行きたい店が全く違うから、どちらかが話を譲らないと行けなくなった。強情を張ってもしょうがないので、ここは文恵が譲ることにした。
「恵美が、そんなに行きたいって言うなら恵美の言うお店にしましょう。今度行くときに私の行きたいお店に行くってことでいい?」
「わかったわ。今度行くときは文恵の行きたい店にしましょう」
こうして、2人は恵美の行きたい店に向かって足を向け始めた。
恵美と文恵は、恵美が来てみたかったイタリアンのお店に来ている。ここで食事もしながらお酒が飲めると言うこともあるが、何よりも店内が女性向けに作られているために、雰囲気が良くて入りやすい店だった。ここに来るまでは会社から歩いて15分ほどかかった。思ったよりも場所がわかりづらかったが、きちんとたどり着いた。
店の一番奥のデーブルに恵美と文恵は向かい合うように座るとさっそくウェイターが水を持ってくる。なかなかのイケ面の彼から「注文は?」と聞かれたが、まだ決まるわけがないので、「まだ決まっていません」と恵美がウェイターに言うと彼は定位置に戻っていった。
二人で何を食べるのか、ああでも無いこうでも無いと話ながら、恵美はアラビータ、文恵はカルボーネを頼むことに決めた。加えて二人でボトルワインを1本飲むことにした。なんとも贅沢な二人である。
さっきのウェイターに見えるように恵美が手を挙げると、さっそく彼がやってきてオーダーを取り始める。文恵はそのやりとりを黙って見ているが、やはり恵美の方が誕生日が早いせいもあって、文恵がオーダーを取る時よりも色っぽく見えた。オーダーの確認を終えると、彼はキッチンの方へと向かっていく、この間に文恵は今日ここまでの出来事を思い返していた。
---------------------------------------------------------------------------
そう、あれは昼休みの始まる前のこと。総務課の課長である柴田潤蔵は会議室に詰めていた時のことである。総務課には桜井文恵と田口康夫しかいなかった。田口康夫はこの時が来るのを知っていたため、ある計画を実行するために文恵に話かける。
「桜井さん。今時間あるかな?」
どことなく具合の悪そうな声だ。
「えぇ。何か急な仕事でもできましたか?」
「いや、そうじゃないけど、ちょっと風邪がひどくなったので、午後休取ろうと思ってね。課長の会議が長引きそうだから。桜井くんに頼めないかと思ってね。ゴホン、ゴホン」
そう話ながらも康夫は咳が出て仕方が無いようだった。
「はい、わかりました。田口さん大丈夫ですか?課長には私が言っておきますので、先に帰ってもいいですよ」
「うん、ありがとう。じゃあ、お先」
そう言うと康夫は昼休みが始まる15分前に会社を出て行った。
康夫が席を立つや否や、文恵は康夫の机の上に携帯電話が置いてあるのを見つけた。
「あっ。田口さん。携帯電話忘れてるじゃない」
そう言うと、隣の課にいる大塚課長へ一言、携帯電話を届けて来ると伝えると更衣室へと急いで向かった。階段を駆け下りる彼女の手には田口康夫がいつも大事に持ち歩いている携帯電話が握りしめられていた。
男子更衣室の前まで来ると、その中へ入ろうかどうか躊躇した。昼休みの始まる前の時間なのでここには誰もいない。勝手に入っても大丈夫だろうと男子更衣室の中へと足を踏み入れた。いつも自分は入ることの無い部屋なので、文恵は少し緊張している。中はロッカーが並んでいるが、入口に入ってすぐのところから見えるところに田口の姿は無かった。
奥にもロッカーがあるからと、更に奥の方へと足を動かした時、目の前の物がどんどん大きくなり始めた。いや、性格には文恵が小さくなっていたのだ。自分の着ている会社の制服もスルリと体から落ちていき、小さくなりながら全身裸になって行ったのだ。手に持っていた携帯電話も持てなくなって地面に落ちた。そうかと思っている内に、体が宙に浮き始め何かに向かって飛んで行く。そして、気を失ってしまった。
その時、康夫は男子更衣室の一番奥にいた。入口からは見ることができない場所、さっき文恵が足を踏み入れようとした場所だ。康夫は手にふたのついた小さな小瓶を持ったまま、怪しい笑みを浮かべている。その小瓶を持ったまま男子更衣室の鍵を閉めると、大きな鏡の前で自分の服を脱ぎ始めた。
さすがに裸になるのは恥ずかしいとトランクス1枚だけは残すことにした。先ほどの小瓶の中をよく見ると小さくなって全裸姿の文恵がいた。これは一体何だというのだろうか?
「こんな姿になっても文恵さんはやっぱり可愛いよね」
康夫は小瓶の中にいる文恵に向かって話かけている。
「それで、この小瓶のふたをカチッと音がするまで閉めると……」
そう言いながら、康夫は小瓶のふたがカチッとするまで閉めた。カチッと音がしたあと、大きな鏡を見てみるとなんとそこには康夫のトランクスを履いた文恵の姿があった。
「この小瓶はやっぱりすごいよなぁ」
男子更衣室には似使わない女性の声が響いた。文恵の姿に変わった康夫が小瓶の中を覗いてみると小さくなった文恵の意識が戻ったようだった。
「可愛い文恵さんがお目覚めだね」
小瓶の中にいる文恵には目の前にいるの文恵が偽物なのはすぐにわかる。小瓶の中から大きな声で叫んでいるようだが何も聞こえてこなかった。もちろん、小瓶を叩いてもびくともしないのは当然のことだ。
「いいかい。よく聞くんだ。俺が文恵でいる内は文恵さんが2人もいる必要が無いだろう。とりあえず、この中にいてくれよ」
そう言うと、さっきまで文恵が着ていた制服や履いていた紺のパンプスを見つけ、着替え始める。着替えが終わるとすっかりさっきまで目の前の席にいた文恵と寸分違わぬ姿になった。小瓶をベストの胸ポケットに入れると。
「昼休みからは俺が桜井文恵をやらしてもらうよ」
そう言って、そっと男子更衣室から出ると女子更衣室にある文恵のロッカーを開けた。文恵のカバンに小瓶を入れ、香水の瓶を出して軽く付け直すと昼休みの時間になっていたので、文恵の姿をした康夫はそのまま昼休みの休憩を取ることにしたのだ。
15階にある会社に戻ると自分が座っていたデスクの上に康夫の携帯電話を置いた。総務課長の柴田はまだ席に戻って来ないので、隣にいる大塚課長に「田口さん見つかりませんでした。携帯電話机の上に置いておきますね」と伝えると、エレベーターで1階に降りて昼ご飯を食べに行くことにした。
文恵はコンビニでおにぎりを買うと公園のベンチに座って食べていた。いつもは康夫がこうして昼ご飯を取っているのだが、文恵の姿で同じことをしてみると周りの視線が違う。行き交う人々の視線が自分の方に向かってくるようだ。食事を終えると公園の中を歩きながら、文恵の動き方を真似てみた。誰にも聞かれないように言葉の練習もしてみた。
小瓶の威力が更にすごいのは、変身すると変身した相手の能力や記憶までまったく同じになれることだった。自然な形で文恵の動きができている。康夫は午後からは文恵を演じるんだと思うと興奮せずにはいられなかった。
そんなわけで、昼休みが終わる時間になると会社のあるビルに戻った。そして、エレベーターを待っている時に後ろから総務課長の柴田に声をかけられたのだ。やはり課長は文恵さんと俺とでは目つきからして違うのがよくわかった。午後の仕事をしていても、きつく叱ってこないし、文恵として仕事をするのも楽しかった。
---------------------------------------------------------------------------
「文恵。文恵」
水のグラスを持ったまま考え事をしている文恵に恵美が声をかけてきた。
「何考え事してるのよ」
恵美はキッチンに行ってしまったウェイターの動きを見ながらそう言った。
「ん?別に何でも無いよ」
とぼけるのはいつもの文恵も同じだ。
「わかったわ。私、トイレ行ってくるから」
席を立とうとする恵美に文恵が腕を掴んで言った。
「恵美。今日は思いっきり飲もうね」
そう言う文恵の目がいつもよりも輝いていることに恵美は気づいていなかった。
トイレから恵美が戻って来るとすぐに注文をしていた料理が届けられた。もちろんさっきのウェイターが運んで来た。文恵はウェイターの左胸につけてあるネームプレートを見た。さっきから何度も名前を読もうと思っていたのだが、今になってようやく読めた。上には漢字が書いてあって五十嵐祐介(いがらしゆうすけ)と読めた。どうやら恵美は彼に気があるらしいのがなんとなくわかったのだ。
恵美の目の前にはアラビータが、文恵の前にはカルボーネが置かれ、祐介がボトルワインをワイングラスに注いでくれる。このとき恵美は祐介の動きに惹かれているように見えた。もちろん文恵はその表情を見逃してはいない。2人はワイングラスを持って乾杯をすると食事をはじめた。
フォークをスプーンの上でもってパスタに絡めて行く、口に入れると絶妙な味に驚かされた。2人とも料理の味にご満悦で、会社であった無駄話をしながら、ワインを更に1本追加するほど機嫌がよくなってしまった。こうなるとウェイターの祐介がまたやって来る。ワインをグラスに注いでいる際に、恵美が祐介に自分の名刺を差し出した。裏にはいつの間にか携帯電話の番号が書いてあるのだ。祐介は一瞬もらうのを躊躇ったが、素早く自分のポケットに入れた。
「あとで電話してね。待ってるから」
祐介がいつもの持ち場へ戻る間際に恵美はこの言葉をかけた。このとき、文恵はワインの酔いがかなり回って来ていた。顔が赤くほてっていてちょっとぼーっとして来ていた。恵美はお酒に強い体質のため、びくともしていない。
食事が終わると文恵はトイレへ行って来ると言って、トイレへやって来た。個室の中に入るとスカートのホックを外して便器に座っていた。ずっと我慢していたので、出てくる水も思ったよりも多い。トイレットペーパーで軽く拭き取ると、立ち上がってスカートのホックを止めた。文恵の動きが板についてしまっている。
個室からでると、洗面台の前に立ち。手を洗い化粧を直す。お酒を飲んで赤くなった顔を見ているだけでも実は興奮気味だった。頭の中にこれからの計画が練り上げられてきたからである。席に戻ると会計を済ませ、2人は店の外に出てきた。今日の食事はよほど機嫌がよくなったのか恵美が全部出してくれた。
外に出るとさすがに夜風は冷たい。しかし、酔っている体にはこの風が気持ちよく感じるのだ。地下鉄の駅に向かって歩き出すと、文恵の足下がふらふらしてるのに恵美が気づいた。青いパンプスの動きが悪いのは文恵が思った以上に酔っぱらっているからだろう。
「文恵。大丈夫?」
「大丈夫よ。私はまだまだ飲めたのに〜」
「じゃあ、まだ飲むって言うの?」
「私は大丈夫だよ。まだまだ飲み足りないぐらいだから」
そう言いながらも文恵は恵美に支えられながら歩いていた。
「飲み過ぎたみたいよ。今日はこの辺で帰りましょう」
恵美がそう言うと、文恵の歩きが止まった。
「えぇ〜っ。もう帰るの?夜はこれからだって言うのに〜」
「文恵のためを思ってなんだけど。どうしたらいいって言うの?」
恵美は困った表情で言った。
「私、今日は帰らないわよ。一緒に飲みに行こうよ」
恵美にとっては、今日の文恵はいつもよりも少し頑固に見えた。
「しょうがないわねぇ。じゃあ、私のうちにおいでよ。うちで飲み直しましょう」
「えっ!?恵美の家に泊まっていいの?」
文恵は突然、ニンマリとした表情をし始めた。
「文恵もそうだけど。私だって一人暮らしだからね。たまにはいいよ」
「じゃあ、恵美の家に行こう!」
文恵は両手を空に向かって高く掲げながら大声で叫びました。するとすれ違う人たちは2人をじろじろ見ながら通り過ぎて行くのです。
「わかったから。静かにしなさいって」
2人は恵美の家に向かうべく、地下鉄駅に向かって再び歩き始めたのでした。このとき、文恵がしてやったりの表情をしていたのを恵美は見逃していたのです。
地下鉄駅に到着すると、改札をなんとか通り抜け、プラットホームで電車を待つことになりました。まだ電車が来ないので2人はプラットホームをゆっくりと歩いています。すると、見覚えのある人がプラットホームに立っていました。恵美はその人の姿を見ると心臓がドキドキし始めました。そう、そこにいたのはさっきの店のウェイターである五十嵐祐介だったのです。
祐介がこっちの方に気づくと、お互いに軽くお辞儀をしました。当然のことながら2人の顔はまだ記憶に残っていたのです。
「仕事終わったんですか?お疲れ様です」
祐介は店にいる時と違って私服姿。そんな私服姿の彼に声をかけたのは言うまでも無く恵美からだった。
「今日はたまたま早く帰してもらいました。これから用事があるんで」
「これから?そんな遅くから約束ってあるんですか?それって、彼女と?」
彼に気のある恵美はもしや彼女がいるのではと思いそんな言葉が出た。
「彼女なんていないよ。俺の妹が突然入院したって聞いたもんだから。今から病院に行くことろ。あっ、そんなこと言ったって関係ないよね」
始めて会ったというのに祐介は恵美に親しげに話してくる。
「そうですか。大変ですね」
そんなことを話しているうちに電車がやって来た。一緒に電車に乗り込むと、3人は無言の状態が続いていた。
地下鉄からは恵美たちが先に降りることになった。恵美の家がある駅の方が先に到着するからだ。
「じゃあ、時間があったら電話してね」
電車から降りるとき恵美は祐介にそう言い残して別れた。一緒にいる文恵は半分眠ったような状態だったので、文恵を抱えながら駅の改札を通り抜けるのも一苦労だった。恵美の家はここから歩いてすぐのアパート、2人の夜はまだまだ続くのだ。
駅から歩いてくると恵美のアパートの前の前に到着した。恵美の家はここの2階にあるため階段を使ってあがって行く。たがが2階とはいえ文恵を抱えながら2階にあがるのは大変だった。恵美の家の前に到着すると文恵を一度通路に座らせるとバッグの中から鍵を取りだし、玄関を開けた。
玄関の扉を大きく開けて閉じないように固定すると、また文恵を抱えて玄関へと入る。恵美は自分のパンプスを脱ぎ捨てると、文恵のパンプスも脱がして、部屋の中へと入った。文恵をベッドの上に寝かせると、玄関の扉をしっかりと閉めて来た。パンプスも整理してから文恵のいるベッドのそばに行った。
恵美はベッドの上に置かれた文恵をしっかりと寝かせつけてから、冷蔵庫の中からミネラルウォーターを取りだして、文恵に差し出した。
「文恵。あなたはお酒に弱いんだから、これ以上飲めるわけないでしょ。水でも飲んで頭を冷やしなさい」
同じくらい飲んだのに恵美はしっかりとしている。やはりアルコールに弱い文恵の元の体質まで同じなのだから当然のことではある。
恵美の部屋はワンルームにキッチンとユニットバスのついたタイプ。部屋の真ん中にはテーブルが置いてありベッドと冷蔵庫を置いて、洗面所には洗濯機まで置いてあるから比較的大きめの部屋だ。文恵に水を渡すと、恵美はクローゼットを開けて中からバスタオルと部屋着を取り出した。
「私、シャワー浴びてくるから。そこでおとなしく寝てなさいね。テレビでも見るんだったらつけてあげるけど、見る?」
そう言うと、ベッドの中で寝ている文恵は枕の上で首を横に振った。恵美はシャワーを浴びるためにバスルームへ向かう。
恵美はシャワーを浴びながら、今日の出来事を考えていた。結局、文恵を家に連れてくることになったけど、思ってもいなかった展開になってしまった。一緒に食事に行こうと誘った時から思っていたけれど、いつもよりも積極的な感じがした。文恵もたまには積極的になるんだなって思ったれど、こんな風に一緒に家にやってくるとは、友達とは言っても世話がやける。
シャワーから出てくる温かいお湯が体に当たるたびに、一日の疲れが溶けていくよう。文恵との出来事も楽しい思い出として残っていくことだろうと思い返した。バスルームの外ではテレビの音が聞こえる。さっきまで文恵はテレビを見ないと言ったのに、少し調子がよくなったのかも知れない。一度シャワーを止めてボディーソープで体を洗っていた。
恵美はボディーソープで洗った全身を洗い流すために、再び温かいお湯の出るシャワーの蛇口をひねった。シャワーをフックにかけたままゆっくりとボディーソープを洗い落とした。そして、足の踵についたソープを落とそうとしている時に恵美はシャワーの粒がだんだんと大きくなっているのに気づいた。
シャワーの粒がだけが大きくなるのではなかった。実は、シャワールームにある全てのものが大きくなって行った。実は恵美の体が小さくなっていたのだ。体が石けんよりも小さくさくなるといつの間にか、小さな小瓶に閉じこめられていた。外には見慣れた自分の部屋が見える。
いつの間にかと書いたが、正しくは小さくなって行くときとと小瓶の中にいた時の間のことは記憶にない。なので、シャワーを浴びていつの間にか小瓶の中に入ってしまったのだ。小瓶の中で意識を取り戻すと、シャワーの音が止まる音が聞こえた。小瓶に閉じこめられた恵美はシャワールームの中に人影があるのを見つけたのだ。
あれは誰なの?文恵なの?それとも……恵美の頭にはとっさにそんなことが浮かんだ。シャワーの音が止まってから1分くらい経ってからシャワールームの扉が開き、中からついに人が出てきた。バスタオルで体を拭きながら出てきたのは、なんと恵美の一番よく知っている自分の姿だったのだ。
バスタオルで体を拭きながら出てきた恵美は、裸姿のままバスルームから戻ってきた。恵美の入った小瓶を手に取ると、ニヤッとした表情を浮かべる。ベッドの上には文恵が黄色いパジャマ姿ですやすやと眠っていた。小瓶の中に入っている恵美は一体何が起こったのか理解できないまま、恵美のドレッサーにある化粧箱に入れられてしまった。
恵美はドレッサーの前に座りながら、さっきの出来事を想像した。目の前にいる恵美の姿を手に入れるまでの短い出来事ながら、思い出すだけでも気分がいいようだ。それは、恵美がシャワールームに入った時から実行された。
---------------------------------------------------------------------------
「私、シャワー浴びてくるから。そこでおとなしく寝てなさいね。テレビでも見るんだったらつけてあげるけど、見る?」
そう言うと、ベッドの中で寝ている文恵は枕の上で首を横に振った。恵美はシャワーを浴びるためにバスルームへ向かう。
恵美がバスルームの中に入ると、文恵はベッドの上から起きあがり、まずはテレビのスイッチをつけた。シャワーの音と同じくらいのボリュームになるようにすると、自分のカバンの中から本物の文恵が入っている小瓶を取り出した。小瓶をテーブルの上に置くと、文恵は自分の服を脱ぎ始める。
小瓶の中に入っている文恵もどうやらお酒に酔っているらしい、実はこの小瓶の中にいると変身している相手の状況と同じ状態になってしまうのだ。お酒を飲むと飲んでもいないのに飲んだようになり、頭が痛いと本物の文恵まで頭が痛くなってしまうのだ。そう変身した相手と本物の文恵がある意味、運命共同体として生きて行かなくてはならなかったのだ。
小瓶の中にいる文恵はお酒の影響ですっかりと寝てしまっていた。そのため、偽物の文恵が服を脱いでいるのにも気づいていない。偽の文恵は全裸になると小瓶を手に取ってふたを回してゆるめた。するとみるみるうちに文恵の体が田口康夫の体に戻っていくのだ。さっきまでスリムな文恵の姿をしていたに、中年太りの男に戻ってしまった。自分の体に戻った時点で、彼は小さな文恵を小瓶の中からベッドの上に出した。
文恵の体はすくすくと大きくなっていき、元の大きさになってベッドの上に横たわっている。もちろん全身裸のまま。康夫はさっきまで自分が身につけていた下着を文恵の体に着せると、恵美のパジャマを探し出してそれを着せた。この時、シャワールームの中にいる恵美に気づかれないようしなくてはならなかったので、気持ち的に大変だった。
文恵は寝ている状態なので、パジャマに着替えさせても起きることは無かった。ベッドの中にきちんと寝かせると、彼は空になった小瓶を手に取った。
「後藤恵美」
恵美の名前を言うと、恵美の体が小さくなって入ってしまった。例によって気を失っているため、彼の正体がばれることがない、今は文恵が起きてしまうのが怖いので、急いで小瓶のふたを閉めた。カチッと言う音とともに、彼の体は再びやせ細り恵美の体へと姿を変えていた。
シャワールームではシャワーが出しっぱなしになっているので、小瓶をテーブルの上に置いてシャワールームへシャワーを止めに行った。そして、バスタオルで体を拭きながらシャワールームから出てきたのだった。
---------------------------------------------------------------------------
ドレッサーの前にいる恵美は鏡の中にいる恵美に向かってほくそ笑んだ。
「こんなもんね。恵美も簡単に手に入れた」
まだ裸のままだったので、クローゼットから下着を身につけるともう一つあったワンピース型のピンクのパジャマに着替える。
ベッドに眠っている文恵の寝顔を見ながら、ちょっと懐かしい顔を見るような感覚を得ていた。電気を消してから文恵の横に一緒に布団をかぶる。さっきまでの獲物が新しい獲物と一緒に寝ている。そう思うと恵美はなかなか眠れなくなっていた。
すると、さっき出会ったばかりの祐介から携帯電話にメールで初めてのメッセージがやって来た。
『五十嵐祐介です。初めて会ったのに初めてのような気がしませんでした。明日、時間があったら会ってもらえますか?メール待ってます。』
内容はこんなものだった。しかし、祐介も恵美に対して好意を持っていたのは、文恵として見ていたので明らかだった。やっぱり来たかと思いながら、送られてきた祐介のメールに返信をする。
『実はわたしもそう思いました。明日、わたしの降りた駅で正午に待っています。』
すると、祐介からすぐに返事が来た。
『ありがとう。明日会いましょう。お休みなさい。』
簡単なメールのやりとりだが、恵美の感情は悪くない。恵美の気持ちはやはり祐介にかなり好意を持っているのがわかった。こんな気持ち久しぶりだなぁ。恵美に変身した康夫は思いもしない感情を楽しんで、ゆっくりと眠りについた。
文恵はカーテンの隙間から入ってきた日差しによって起こされた。ここはどこかと気がつくと恵美の家のようだった。前にも何度か来ているのでよくわかる。しかし、いつの間にここへ来たというのだろうか。たしかさっきまで会社で仕事をしていたはずだ。
自分のカバンが目に入ったので携帯電話の画面を見てみると次の日を指していた。自分の知らないうちに何が起こっていたと言うのか、どこか狭い所に入っていたような記憶もあるが、うまく引き出せない。会社からいきなり恵美の家にいるなんてことを説明することができなかった。
そうしていると、シャワールームの方から恵美がバスタオルを胸に巻いてやって来た。妙に気分が乗っている恵美の姿。文恵の方に近づきながら声を掛けてきた。
「文恵。起きたの?」
「うん。今起きたところだけど、私、どうして恵美の家にいるの?」
「会社が終わってから飲み過ぎてうちに来たんじゃない?文恵ったら、覚えていないの?」
そう言うと、文恵は顔を立てに振った。
「そっか。かなり飲んだからね。記憶が飛んじゃったのかも」
文恵は自分の知らないうちにお酒を飲んだと言うことを聞いて、ますます不思議に思った。
「私がそんなにたくさん飲んだって言うの?」
文恵は恵美の方をじっと見ながら聞いてくる。
「うん。飲めないのに飲み過ぎたからやっぱり記憶が無い見たい」
そう言うと、恵美は冷蔵庫からミネラルウォーターを出してコップに入れる。
「はい、これ飲みなさいよ」
文恵は自分の体からアルコールが完全に抜けていないことに今頃気づいた。
「かなり頭が痛いと思ったら、二日酔いになってる〜」
「じゃあ、文恵はもう少し休んでいなさい。私は昼までに出かけなくちゃならないから、家に帰る時は……」
そこまで言うと、文恵が言葉を返してきた。
「オートロックになってるから、扉が閉まったのか確認してから帰ってでしょ」
「わかっちゃったの。さすが」
恵美はいいながらペロッと舌を出した。文恵が恵美の家に来るときはいたってこうなることが多いので、文恵はすっかりと覚えてしまったようだ。
恵美はゆっくりと出かける支度を始めた。ドライヤーをパーマのかかっている茶色い髪にあてて整えると、着替えるためにクローゼットから服を取り出す。スカイブルーのHラインスカートに白いキャミソール、そして、スカートよりも少し濃いめのブルーのカーディガンを取り出すと、颯爽と見に纏う。
恵美がでかける準備をしているうちに文恵が静かになっているのに気づく、文恵はこの間に再び眠りについたようだった。恵美は再びドレッサーの前に座って化粧を始める。化粧水とファウンデーションでベースを整えると水色のアイシャドーを目先に加える。眉毛を描いてから、引き出しの中から誰かとデートをする時のために使おうと思っていたリップスティックとリップグロスを取り出す。ピンクのリップスティックを唇に塗ったあとにラメ入りのリップグロスを軽くつけた。全体的に不足しているものを確認して化粧が完成。
大きな姿見に立つと全体のバランスを見てみる。全体的に青で統一しているのでなんとなくさわやかな感じが見える。ストッキングをまだ履いていなかったので、クローゼットからベージュのダイヤドット柄の入ったものを取り出して、すらりとした足を入れていく、この時点でもう一度姿見の前で確認をしてから、でかける時に持って行くハンドバッグの中身を整理する。
ハンドバッグの中に、本物の恵美の入った小さな小瓶をすぐには見えない場所に入れ、化粧品や財布、家の鍵に携帯電話を準備した。ドレッサーにまた座るとエレガントな香りがする香水を軽くスプレーした。この香水もハンドバッグの中に入れ、また大きな姿見で確認。姿見を見るたびに何かそわそわする気持ちを感じながら、足りないものを付け足していく。
そんなことをしている時に恵美の携帯電話に祐介からメールが届く。
『祐介です。ぐっすり眠りましたか?今日の正午に会いましょう。それじゃ。』
恵美がこのメールを読むと、返事を書く前に玄関で靴を選び始めた。今日の服装によく似合うのはふと探してみるとちょうどいい靴があった。文恵の青い靴に似ているが、それよりも光沢が入った革でつくられた9cmのハイヒール。
履く靴も決めて、ベッドで寝ている文恵のそばに行って行くと、文恵を眠りから起こして言った。
「文恵、私行くから。帰る時は携帯に連絡入れてね」
眠そうな顔をしながらも文恵は、恵美の言葉をちゃんと聞き入れ軽く顔を縦に動かした。玄関へ行ってハイヒールを履くと、恵美は携帯電話をバッグから取り出して祐介にメールを送った。
『恵美です。今から、家を出ますね。あとで会いましょう。』
そうして、玄関を開けると恵美のデートがはじまろうとしていた。
ここは祐介と恵美が待ち合わせることになっている地下鉄駅。この駅には待ち合わせのスペースが用意されており、噴水の真ん中に置かれた大きな時計の針が正午になるためには時間が30分もある。この噴水の前で待ち合わせをする人の中に祐介の姿があった。
祐介は噴水の前に来るとさっそく恵美の携帯電話に向けてメールを送った。メールの内容はここで待っていると言った内容のみ。朝にメールをした時に恵美は家を出たとのことだったので、どうやらどこかへ寄ってから来るらしかった。
恵美からの返事が返ってくると、祐介はさっそくメールを読んでみた。思ったよりも時間がかかって正午を少し過ぎるかも知れないと言う返事だった。噴水の前で待っている人は祐介だけでは無いが、待ち合わせをしている人がいなくなって行くたびに、早く会いたい思いが募っていく。
そんな時だった。一人の女の子が祐介に向かって声を掛けてきた。肩まで伸びる茶色の髪、くりっとした瞳、軽くピンクに染められた唇。白いワンピースからは白い素肌が見える。足下の水色のミュールによって涼しげな雰囲気がした。
「お兄ちゃん。ここで何してるの?今日は仕事じゃ無かったっけ?」
実はこの女の子は祐介の実の妹だった。祐介が小学校に入ってからできた妹だけに年の差は7歳もある。
「よっ。絵奈」
祐介は右手を軽く挙げ、苦笑いをしながらも絵奈に愛嬌を振る舞ってやった。
「お前に隠しておいてもしょうがないからな。今日はデートだよ」
「へぇ〜。お兄ちゃんもたまにはやるもんね〜」
絵奈は祐介を見上げながら話してくる。絵奈の身長は150センチも無くてかなり小さめだから、まっすぐ見ると祐介の首しか見ない。
「絵奈はこれからどこへ行くんだい?」
そう言うと絵奈は長い髪を手で触りながら。後ろにいる友達をちらりと見て言った。
「私は友達とプールに行ってくるよ。いつも土曜日はそうしてるでしょ」
すると祐介は忘れてたかの表情を一瞬見せてから。
「あっ。そうだった。土曜日はいつもプールに行くんだよな」
そう言いながら、絵奈の胸に手を出してくる。しかし、絵奈の手が一瞬早く防御姿勢に入って、祐介の手を追い返してやった。
「いつも、やめてって言ってるじゃない。私だって年頃のレディーなんだから」
いつもの言葉を言ってくる。
「わかった。わかった。友達に悪いからさっさと行けよ」
「うん。わかった。お兄ちゃん、デート頑張ってね」
そう言うと絵奈は友達が待つ中へと帰って行った。
絵奈がいなくなると、また退屈な時間が始まった。正午まではまだ10分も残っているし、恵美が正午に来られなければ更に待つことになる。時計の針と戦うのも嫌なので、携帯電話を開いて恵美に向けてメールを送ろうとした。
メールを送ろうとした瞬間、携帯電話の着信音が鳴った。携帯電話を開けるとメールの内容が表示されていた。
『今終わりました。これから駅に向かいますね。遅くても5分までには行きま〜す。(m_m)』
と言う内容、やはり恵美からのメールだった。
すぐに祐介は、
『駅の噴水の前で待っています。焦らないでゆっくり来てください。(^^ゞ』
と恵美に返信したのだった。残っている時間は15分。15分、噴水の前で待つのはかなり退屈なこと。祐介は携帯電話にダウンロードしておいたゲームをやることにして暇つぶしを始めた。
噴水の真ん中にある大きな時計が正午を指した。恵美が来るまで遅くてもあと5分。携帯ゲームもさすがにつまらなくなって、あとの5分は周りの風景を見ながら黙って待つことにした。祐介は噴水の前を行ったり来たりする人の流れを見ているのもおもしろいものだと思った。
行き交う人の流れは老若男女さまざまだった。もちろん1人で歩いている人もいれば、カップ、グループといろんな形態があることに気づく、みんな始めは知らない同士だったのだろう。もちろん周りのことなんか普段は気にすることが無い。恵美が祐介の働く店にやって来なければ恵美を待つことも無かったのだ。
昨日の夜に会った恵美の姿を思い浮かべながら、恵美が来るのを今か今かと待つ思いがだんだんと膨らんでくる。時間的にもそろそろ来るはずで、噴水に近づく女性の姿を見ては恵美の姿に見えていた。
噴水の前で恵美を待つ祐介。祐介は約束の時間30分も前からここで待っている。その約束した時間もすでに過ぎてしまった。恵美からはメールで遅くても約束の時間5分過ぎまでには来るともらっていたので、もう少し辛抱する必要があった。
祐介は携帯ゲームをやめたあと噴水を眺めていた。ゆっくりと見てみると、噴水の動きはなかなかおもしろかった。噴水の真ん中にある大きな時計の針は3分を指していた。じれったいがここで恵美を待つしかないのだ。不思議にイライラとはしていなかったが、恵美に早く会いたいという気持ちは更に高まっていた。
すると「祐介さ〜ん」と遠くから聞こえた気がした。噴水の周りをキョロキョロしてみると、まだ恵美の姿は見えない。そんな中で一人の女性が近づいて来たのに気づいた。
「祐介さ〜ん」
しばらく考えてから、祐介が女性に向かって話しかけた。
「あっ。恵美さん。髪型変えたんだね。似合ってるよ」
「ありがとう。祐介さんって女性の髪は長いのが好き?短いのが好き?」
恵美がさりげなく質問してくると、祐介は少しためらいながら答えた。
「俺の場合は関係ないっすよ。似合ってればどっちでも」
「よかった。短くしたら祐介さんに嫌われるかなって思ったけど、思い切って切っちゃいました」
恵美の髪型は昨日見た背中まであるロングヘアーからショートへと変わっていた。そんな恵美の姿を祐介はじっと見ている。
「昨日は、お客さんとしての意識が強かったんですが、恵美さんって俺のタイプです」
恵美は口に手を当てながら軽く笑いつつ。
「ははは。お世辞はよしてくださいね」
にこやかな表情を祐介に見せていた。
「お世辞じゃないですよ。俺がピ〜ンと来たからデートに誘いましたから」
こんな時、恵美が何かを思い出したかのように手を叩いて聞いてきた。
「そういえば、祐介さん。妹さん入院したって大丈夫でしたか?」
「えっ?あっ。あれは結局、嘘だったんですよ。昨日は恵美さんに会えるかもと思って早く帰るために適当な理由をつけて仕事を終わらせたんです」
すると、恵美が祐介の胸に抱きついて来た。
「私のためって。もしかして、祐介さんもそう思ったんだ」
恵美には祐介の心臓がドキドキしているのがわかった。そして、噴水の前で2人が抱きついたまま無口になって時間が始まった。
「恵美さん」
沈黙を破ったのは祐介のこの一言からだった。
「恵美さん。これから恵美って呼んでもいいかな?」
祐介の純粋な目が恵美の目をじっと見つめながら言ってきた。恵美は何も言わずに、自分の鼓動を楽しんでいた。このドキドキする感覚は恵美には何度もあったことだが、恵美になっている田口にとっては初めての経験だったからだ。沈黙した時間がゆっくりと流れながら、恵美はゆっくりと首を縦に振った。そして、久しぶりに口を開いた。
「私、祐介さんのこと好きです。だから、恵美って呼んでください」
すると、祐介が全身全霊の力を振り絞って言った。
「俺とつきあってくれますか?」
恵美はさっきと同じように首を縦に振り、祐介の胸の中と頭を入れてきた。
「喜んでつきあわせてください」
恵美が言った声は祐介には嬉しくて聞こえていなかった。そして、恵美になった田口は恵美が祐介を恋する気持ちにを楽しみはじめていた。この時、恵美の頭の中には家を出てきてからここまでの出来事を不思議に思いだしている。
---------------------------------------------------------------------------
不思議な気持ちに包まれながら家を出た恵美は、待ち合わせの時間までに十分に時間があることに気がついた。待ち合わせの正午までにはまだ3時間はあるからだ。階段から降りてくるとバッグの中からコンパクトを取りだして、顔を覗いてみる。せっかく祐介に会うのだからもっときれいになってあげたい、そう思った恵美は美容室へ向かうことにした。
いつも行く美容室に電話を入れると、今からすぐにやってもらえると言うことだった。その美容室からだと地下鉄の駅までは歩いて5分くらいだ。美容室のそばにはお気に入りのカフェもあるため、待ち時間の調節にも使える便利な場所だ。
恵美が美容室の中に入ると、いつも恵美を担当している男性スタッフの山下省吾(やましたしょうご)に出迎えられた。美容室の中にはまだお客さんがいなかった。どうやら恵美が今日はじめてのお客さんとなったようだ。椅子に腰をかけると、今日はどんな風にしたいのかを聞いてきた。恵美はどうやら長くなった髪がうっとうしくなったので切りたいと思った。
しかし、祐介が長い髪を好きだったらどうしよう。そんな迷いが出てしまう。髪を短くして嫌われてしまうのも嫌だった。それならばと、恵美の本当の正体である田口だったらどうするか考えてみる。自分の好きなつきあってもいない女性が突然髪を短くしたら。田口の本心だとそんなことは関係ないだろうと思ったのだ。
ならば、恵美の心は決まった。髪を短くした上で、更にウェーブパーマをかけてもらうことにしたのだ。山下省吾には一瞬驚くほどだったが、大胆なほどのイメージチェンジということでかなりはりきってやってくれた。完成した時にはこれがさっきまでの恵美かと思うほど雰囲気が違っていた。
美容室でヘアースタイルが完成すると、祐介に、
『今終わりました。これから駅に向かいますね。遅くても5分までには行きま〜す。(m_m)』
と言う内容のメールを送っていた。この姿で早く驚かせてあげたいと言う気持ちと、何か胸のなかをくすぐるような気持ちを楽しみながら、美容室を出て駅に向かったのだ。
---------------------------------------------------------------------------
恵美が髪を短くしたことが逆に祐介の告白を早くする切っ掛けになった。祐介の彼女となった恵美はすっかりとこの雰囲気にのめり込んでいる。もちろん、これから初めてのデートによって2人の愛は深まることになるのだ。
ここは地下鉄駅の噴水前、恵美と祐介はこれからのデートをどうやって過ごすのか決めようとしていた。もちろん祐介には恵美が本物の恵美では無いことなんて知るはずもない。この近くにある映画館でも行こうか、それとも喫茶店で話でもするのがいいのか、祐介は実は優柔不断の男のようでなかなか決まらない。恵美は祐介に一任することにしていて、わざと困らせているようだった。
噴水の時計の長針が6を指そうとしている。まだどこに行くか決まらない。実は祐介は恵美に会う後のことを全然考えていなかった。恵美の行きたい所に行けばいいと気楽に考えていたのだ。自分の意思よりも周りの気持ちに流されやすい男だった。
そんなことをしているうちに、噴水の前に立っている二人に迫ってきている人物がいた。しかし、二人はまだ気づいていない。二人のことをさっきまで物陰に隠れて観察していたようだが、じれったくなって近づいてきたらしい。
長針は7を過ぎていた。祐介はここに1時間以上も滞在していることになるのだ。恵美がここに来てからも30分。同じ場所でずっと立っているせいもあってか、恵美は足が疲れてい来ているようで、何度も足を組み直している。ハイヒールの影響もあってかすっかりくたびれた様子だ。
「祐介さん。どこでもいいんだけど、まだ決まらないの?」
「恵美とは初めてのことでせっかくだから、どこか良い場所に行こうかと思って、考えているんだけどなぁ。なんかどれもこれも今ひとつパッとしなくて……」
「そんなぁ。。。祐介さんって見た目に似合わず神経細かいですね」
「まぁ。そんなとこ」
そう言いいつつも、まだどこへ行きたいか思いつかない祐介はかなりイライラを募らせていた。
「じゃあ、私が行きたいところにしましょうか」
「そうするか」
と言ったあとで間髪入れずに祐介が続けた。
「と言いたいところだけど、やっぱ俺が決めないと……」
恵美の顔にはあきらめの表情と足の疲れのピークが来ているようだった。
恵美は周りを注意しながら手を使って足をもみ始めた。そして、どこか座るところが無いのか探していた。遠くの方にピントを合わせているうちに、祐介を見ている一人の人物がいるのに気づいたのだ。
「あれっ?誰かしら。私以外にも祐介さんのファンがいるみたいよ」
恵美は体を立て直してから祐介に耳打ちをするようにして言った。
「えっ?」
デートの行き先を考え続けている祐介は、恵美に言われた方を向いてみた。しかし、人影すらどこにも見あたらない。
「どこだって?」
「だから、あそこにいるんだって」
二人の意見はなかなかかみ合わないようだった。そして、ついには恵美でさえもその人影を見失ってしまったのだ。
「結局、誰もいないじゃない」
「おかしいなぁ。さっきまであそこに見えていたのに、わ・か・い女の子だったよ」
恵美はわざと若いを大きい声で強調して話して来た。
「そんなのいるわけ」
そこまで言ったところで、祐介は急に前を見ることができなくなった。誰かの手が祐介の目を隠していたのだ。
恵美は祐介の後ろにいるのがさっきの若い女の子だとすぐに理解した。恵美はわざと祐介を助けようとしない。
「祐介さん。やっぱり、私以外にもファンがいたのね」
「そうじゃないだろ」
祐介は少し怒った口調で恵美に言う。そして、目隠しをして来た人物を確かめようと、目隠ししている手を振り払って、一気に後ろを振り向いたのだ。
そこにいたのは、祐介のとてもよく知る人物。妹の絵奈だった。
「えっ!?お前。プールに行ったんじゃ」
そこまで言うと、それ以上の言葉は喉から出て来なくなっていた。
絵奈の出現は祐介はもちろん恵美にとっても予想外のことだった。そもそも絵奈は毎週土曜日は友達と一緒にプールに行くのだ。祐介は絵奈が誰と会ってるのか気になっていたのではと予想していた。
喉から言葉が出なくなった祐介の変わりに恵美が言葉を出した。
「あなた。誰なの?祐介さんに慣れ慣れしいようだけど」
「祐介さん?はぁ〜ん。そっか、待ってた人ってあなただったんだ」
「何よ。年の差がずいぶんとあるのにタメなんか使って」
恵美は目の前の女の子に対してすっかり気分を害す。いや、害したふりをしてる。
「いいじゃないの。あたしの格好いいお兄ちゃんを守るのは、あたしの役目だもの」
「えっ?あっ。」
恵美は表情では騙されたような顔をしているが、内心してやったりと思っていた。
「そっか。あなたが妹さんなのね」
「妹さんだなんて。あたしには絵奈って名前があるんだからね。五十嵐絵奈って立派な名前があるんだからさぁ。妹さんだなんて呼ばないでよ」
すると恵美は、さっきまでの警戒したような表情を一気に和らげた。
「そっか。わかったわ。はい」
そう言うと恵美は自分の右手を絵奈の前に差し出す。
「何よ?」
「握手しよって。私は後藤恵美。よろしくね」
絵奈は少しためらったが恵美の手を握った。恵美のすべすべした肌を触ると早く大人になりたいと思ってしまう。
「あたしもよろしく。絵奈って呼んでよ」
「祐介さんの妹なんだから、恵美って呼んでいいわよ」
「それって、ちょっと恥ずかしいじゃん」
絵奈は案外照れ屋さんのようだ。
「いいのよ。今度、一緒に買い物したりしない?それに、化粧道具も貸してあげる」
この言葉を聞くと絵奈の表情が一気に恵美のものになった。
「えっ?いいの?恵美。恵美の使ってるのって高い化粧品でしょう。こんな小娘に貸すような代物じゃ無いじゃん」
「いいの、いいの。うちの会社の取引先からたくさん持ってきてくれるんだから」
女二人が話をしている間、祐介はまだ言葉を失っていた。いや、二人の会話に入り込めない様子だった。
「じゃあ。今度、ゆっくり相談とかのってくれます?」
「もちろん。私の妹みたいな存在だものね」
「やったぁ。あたし、昔からお姉ちゃんが欲しかったんです。いつも、あんなお兄ちゃんを見てばかりで、お兄ちゃんじゃなくてお姉ちゃんが欲しかったって。」
「そっか。私も兄しかいなかったからね。気持ちわかるわよ」
絵奈はすっかり恵美に気持ちを許せるようになった。
「じゃあ、あたしと恵美で姉妹同盟でも組まない?」
「姉妹同盟?」
「だからぁ。義理の姉妹として誓い合うって、それだけじゃん」
「あっ。そうか」
恵美は妙に納得してしまった。
「そう言えば。恵美って何歳?」
「25だけど」
「お兄ちゃんとタメなのね。あたしは18歳で女子高通ってる」
絵奈がそれを言うと、恵美は目を疑った。
「女子高生なの?女子大生かと思ったわ」
「ははぁん。最近の女子高生って、制服着てないと簡単に女子大生に化けられるのよ。そんなの常識じゃん」
「あたしの時はルーズだって無かったもの。わかるわけないよ〜」
「いわゆる、ジェネレーションギャップですね。はい」
恵美はそう言う絵奈を軽く手で叩いた。
「そんなこと言わないの。私だってまだ若いんだから」
二人の会話が少し収まったとき、ようやく祐介が言葉を発して来た。
「何、ぶつぶつ話しているんだよ。ともかく、絵奈。どうしてお前、プール行かなかった?」
正気を取り戻した祐介はいやに冷静に話してくる。絵奈は恵美の方から祐介の方へ体を向き直して言った。
「あっ。プール行ったには行ったよ。でも、臨時休館日だって帰ることにしたの」
「じゃあ、そのまま家に帰ればよかっただろう」
絵奈は手を後ろに回し、両手をつなぎながらゆらゆらした格好で祐介と話をしている。
「だって〜。ここに来たら、まだお兄ちゃんがいるんだもの。しかも、隣に女まで連れちゃってさ。気にならないわけないじゃん」
「そんなのは、気にしないで放っておけばいいんだぞ」
「女の気持ちはわからないでしょ。お兄ちゃんはねぇ。たとえ性格が悪くても格好いいところあるから。これでも嫉妬するんだって」
「お前、馬鹿か?俺とお前は兄妹なんだぞ。恋愛の対象とは違うだろ」
この時、恵美はトイレへ行くと言ってここをさっと離れて行ってしまった。
「でも、そんなのがあるよ。お兄ちゃんのことずっと気にして来たんだから」
「気にしてもらわなくてもいいよ。俺は俺、お前はお前だろ?」
「いいよ。お兄ちゃんのわからずや!」
「こらっ。お前、そんなこと言うなって。」
「私、お兄ちゃんのこと心配だっただけじゃん」
絵奈のさっきまで威勢のいい声はもう無くなっていた。
「わかった。わかった。俺がわるかったよ」
「それならいいわよ。相手が恵美のような人でよかった。あたしのお姉ちゃんみたいで安心したから。これからは、お兄ちゃんより頼りになりそうよ」
「おいっ。俺とつきあうのだってまだ日が浅いんだからな。恵美を取るようなことはするなよ」
絵奈は勝ち誇ったような顔を祐介の目の前に持ってきた。
「わかったならいいわ。あたしが恵美と仲良くなるのだって、お兄ちゃんのためになるんだからね」
「わかってるって。だから、今日は二人きりでデートをしたいんだ。さっさと帰ってくれよ」
「わ・か・り・ま・し・た。邪魔者は消えることにします。あたしもトイレ行きたくなったから、恵美に挨拶して帰るね。」
そう言うと絵奈はトイレのある方角へと消えていった。
ここは地下鉄駅にある公衆トイレ、公衆トイレとは言っても最近はすさましいほどに施設が豪華だったりする。日本トイレ学会のトイレ100選にも選ばれているトイレで、特に女性用は充実したつくりだ。
絵奈と祐介の話の途中で抜けて来て、恵美は女性用トイレに入った。公衆トイレに入るのはこれが初めてのこと、文恵の体を使って会社のトイレにも入ったが、やはり見知らぬ人が使う環境だけに違った刺激を受ける。
個室が8つ並んでいる中で、一番奥の個室に入った。ドアが開いていたので、ノックをしなくても誰も入っていないのが確認できた。今までも何度かやって来たように、まずは便座をトイレットペーパーで拭いてから座る。恵美になってからどうやら恵美の感覚が優先されるので、便座を拭かないと気持ち悪いと感じるようだ。
次に、スカイブルーのHラインスカートのホックを外し、膝の上まで引っ張る、同時にショーツとストッキングも一緒におろした。これでようやく用が足せる状態。力を入れないでも自然と流れて来た。トイレットペーパーを小さく取ると力を入れないように軽く拭き取る。あとは、そのまま便器の中に紙を落として、水を流した。
そして、立ち上がって、下着をしっかり履いてから、スカートを腰まであげてホックをかけた。ここで、恵美は個室から出るのでは無く、また便器の上に座ったのだ。ハイヒールを脱ぎ、足をもみ始めた。さっきしばらく立っていたのが効いているらしい。足が痛くてたまらないのだ。
「ハイヒールが、こんなに足を痛くするなんて知らなかったぜ。恵美の奴、よくこんなの買うよなぁ。まぁ、今は俺が恵美だから、恵美の気持ちからすると買いたいのはよくわかるけどな。せっかくだから。」
恵美は個室の中で独り言を始めていた。もちろん、誰にも気づかれない音量で喋っている。恵美は足を空中に浮かせたまま、ハイヒールを手に取った。そのまま自分の鼻に近づけて匂いを嗅ぐ。恵美の靴の匂い、なんともたまらない香りだと恵美は思った。
ハンドバッグの中から本物の恵美の入った小瓶を取り出し、地面に垂直に置いた。中の恵美は驚いた顔をして、恵美の方を見ている。短くなった髪型、手にはハイヒールを持ち匂いを嗅いでいる姿をまじまじと見せられたからだ。中にいる恵美は泣きそうな顔をしていた。
恵美はハイヒールを地面に起き、その上に足を載せた。そして、小瓶の蓋を持ちながら「同期」と唱えると、たちまち小瓶の中にいる恵美の頭はショートでウェーブパーマのかかった髪型になってしまった。そう、外にいる恵美のスタイルに同期してしまったのだ。これには小瓶の中にいる恵美は涙を流さずにはいられなかった。苦労して延ばした髪が一瞬にして短くなってしまったのだから。
恵美は本物の恵美が見せる行動を楽しんだ後、再びバッグの中に小瓶をしまった。ハイヒールをしっかり履いてから、個室の外へと出る。洗面台の方へ行って手を洗いながら、目の前の鏡を見ながらニヤニヤしていた。
そう、恵美の頭の中は、絵奈のことで頭がいっぱいになっていたのだ。どうにかして絵奈を小瓶に入れてしまいたい。しかし、今は小瓶は一つしか無いために一度元の体に戻らなくてはならないのだ。
そんなことを考えていると、絵奈がやって来た。
「恵美。あたしこれから帰るからね。お兄ちゃんとデートして来て」
「うん、絵奈。わかったわ。」
すると絵奈と恵美は携帯電話の電話番号とメールアドレスの交換を始めた。
「いつでも電話してね。困ったことがあったら私が相談にのってあげるから」
「わかった。何かあったら恵美に相談する。お兄ちゃん頼むね」
恵美はとりあえずデートを楽しむことにし、絵奈とこの場で別れた。
一人になった祐介は相変わらずデート先を考えていた。今度はしっかりと決めようと携帯電話を取り出し、友達の一人に電話する。最初の電話はつながらなかったようで、今度は違う番号に電話をかけた。今度はしっかりとつながって友達にデート先でいい場所がないか聞いていた。
電話をかけ終えた時、ハイヒールをコツコツと鳴らしながら恵美がやって来た。音が止まないうちに、祐介が恵美に駆け寄って、さりげなく地下街の方を目指して歩くように促した。祐介は恵美の腰に手を回すと、恵美も同じようにやってくれた。ようやく二人のデートが始まるのだった。
地下街には色とりどりの色彩が飛び交っている。それでも週末にしては人混みは少なかった。祐介の目は周りを歩く女性の姿を彷徨っていたが、恵美の視線も同様に女性の姿にあった。
「あっ。あの子の服かわいい〜」
すると祐介が返事をする。
「そうそう。俺もそう思った」
そう言いながら、祐介は苦笑いを浮かべる。
「なに思い出し笑いしてるのよ〜。さっきの子が気に入ったんでしょう。わかるわ」
「そんなこと無いって。あの服をお前に着せたらもっと似合うのにって」
「そう?」
「そうだよ。そう思ったんだって」
そう言う風に話をしているうちに二人の歩幅が揃っていた。
「祐介。あのスカートどう?」
「あの子の着てる服か?」
「そうじゃなくて。あの店のディスプレイにあるスカートよ」
二人は人の合間をすり抜けながら目標とするお店へとやって来た。
「ねぇ。このスカートかわいいよ」
恵美は白いフリルスカートを見ている。
「おい。これって、少女趣味っぽくないかよ」
「いいの。こういうのが好きなんだから」
「恵美のスタイルからしたら全然違うじゃん」
「私だって、こういうの着てみたいと思ったりするんだって」
恵美の今の服装からすると、体のラインをきれいに見せるようなスタイルを好むものだと思っていた祐介には意外なことだったりする。
「ねぇ。中に入って見てもいい?」
「見るだけだぞ」
「うん」
そう言うと恵美は自分の気に入るようなスカートを探し始めた。店の奥に目をやると黄色い七分丈のワンピースが目に入ってくる。
「祐介」
恵美は店の前で立っている祐介に、こっちに来るように呼びつけた。ゆっくりと祐介は恵美の方へと寄って来た。
「なんだよ。いいのが見つかったのか?」
「そうなの。あれ」
指を指した先には、恵美が目をつけたワンピースがある。
「おっ。いいねぇ。恵美に似合いそう」
「私ねぇ。髪を短くした時に今の服装がちょっと似合わないなぁって思ったのよ」
「とりあえず、試着してみたら?」
恵美は祐介の声を聞く前からワンピースを手に取り試着室へと向かっていった。中に入る前に祐介に一言。
「ぴったりだったら買ってちょうだいね」
「はいはい。考えておくよ」
祐介がそう言うと試着室の扉が完全に閉まった。
ここは試着室の中、ワンピースに着替えるためにはまずは着ている服を脱がなくてはいけない。恵美はバッグの中から例の小瓶を取り出すと試着室の片隅に置いた。本物の恵美はどうやら眠っていたようだ。目の当たりにした状況に驚いているが、これから自分の着替えを見るだから、なんともやるせない思いだ。本物の恵美はすでに反発する意思が薄れている。そのまま恵美の試着姿を見るしか無かったのだ。
恵美はまず、ワンピースをフックにかけてから、手を腰の後ろに回しスカートのホックを外した。スカートが重力の方向にスッと落ちて行く。恵美は本物の恵美に見えるように、自分の股間部に手を当てながら、気持ちの良さそうな表情をした。
その表情を見ながら本物の恵美は、諦めのような深いため息をしているようだ。足下にあるスカートをきれいに畳むと、今度はブルーのカーディガンを脱いで畳み、スカートの上にきれいに重ねる。ブラウスのボタンを一つ一つ外すと、これもきれいに畳んでからカーディガンの上に置いた。下着姿となった恵美は、そのまま試着室の中にある大きな鏡を見ていた。
すると、鏡に向かって恵美は一人芝居をしているかのようだった。
「祐介さん。私をあなたにあげるわ」
「やだ。祐介ったらぁ〜」
鏡の目の前では右手を胸に、左手を股間に持っていった恵美がいる。
「今日は。駄目よ。私はじめてなんだから」
そうしている間、小瓶の中にいる本物の恵美は後ろを向いてしまった。
「ちぇ。もう見てくれないのかよ」
恵美はそう言って、フックにかけてある黄色いワンピースを着ることにした。背中のファスナーを開け、きれいな足を入れていく、下半身はちゃんと入ったが、背中のファスナーに手がなかなか届かない。ようやくファスナーに手が届くと、一気に首筋まであげていった。
姿見の大きな鏡を見ると、黄色いワンピースを着ている恵美が完成した。小瓶をバッグの中に閉まってから。試着室の扉を開ける。祐介は恵美の姿を見ながら、目を丸くしてしまった。
「きれいだよ。さっきよりもずっときれいになったみたい。サイズはどう?」
「私にぴったりよ。これ気に入っちゃった。欲しいなぁ」
恵美は甘えた声を祐介にかける。そのまま可愛いらしいポーズで祐介を見つめた。
「これって、高いんだよなぁ……」
「そんなに高く無いよ。背中のところに値札がついてるんだけど、見てみてよ」
「えっ。どこにあるの?背中に無いって」
「中にはいっちゃったんじゃないかな。手を入れてみてよ」
祐介が背中に手を入れると恵美の柔らかい肌の感触が伝わってくる。値札のついてる糸をたぐっていくと、ブラの位置に値札があった。そのまま引っ張り出すと、ようやく値段を見ることができた。
「2万9千円!!これってそんなにするのか?」
「安いじゃない。普通は5万ぐらいしたっておかしくないんだからぁ〜」
祐介は店員さんを呼んで聞いてみた。もちろん店員さんは恵美と同じくらいの女性だ。
「あの。これもっと安くなりませんか?」
「これですか?」
店員さんは値札を見てから言った。
「お客様。これはセール商品のため値札価格から3割引かせてもらっています」
そして、レジから電卓を持って来てから出てきた数字を祐介に見せた。
「この商品の場合は2万3百円になります」
恵美の表情は軽くなった。
「祐介、買ってくれない?私に買ってくれるプレゼントにしては安いもんじゃない」
「2万円で安いわけないだろう」
祐介は困った表情をしている。
「あなたって、こんなのも買えない男なの?私、失望しちゃうわ」
「わかったよ。これ買ってやるよ。ちゃんと覚えておいてくれよな」
諦めと同時にやけになったような感じで祐介は言う。
「うん。ちゃんと覚えておくって。祐介からもらったってこと」
「じゃあ、これ欲しいんですけど。いくらでしたっけ?」
祐介は店員さんに向かって値段を確認してみた。
「2万3百円になります。消費税を入れると2万千315円になりますが、よろしいですか?」
祐介は苦笑いを浮かべながら。
「2万円にできませんか?」
「それは、ちょっと」
そう言うふうに言い合っているともう一人の店員さんが近寄ってくる。ちょっと年が行ってるようなので、ここの店長さんのようだ。
「お客様。2万円でよろしいですよ。彼女へ初めてのプレゼントと言うことで、サービスさせていただきます」
「えっ。そうですか。ありがとうございます」
祐介は財布の中から2万円を出すと、さっきの店員さんに手渡した。すると店長さんと思える店員さんが祐介と恵美に話をしてきた。
「その服があまりにも似合ってる人、初めてなんですよ。なかなか売れなかったので、そろそろ処分したいと思っていたのですが、これから大切に着て下さいね」
「あっ。このまま着て行かれますか?」
店員さんが聞くと、恵美は首を立てに振った。すると、店員さんは背中にある値札を取る。
「着ていた洋服を入れたいので、袋をいただけますか?」
「もちろんです」
店員さんは試着室の中にきれいに畳んだ恵美の服を、店の名前がしっかりと入った紙袋に丁寧に入れてくれた。
「ありがとうございました。またお越し下さい」
二人の店員さんの挨拶を後に、二人は店を出た。
「ありがとう。祐介。これから大切に着ますね」
さっきよりも恵美の足取りは軽くなっている。
「いや。どうってこと無いって。俺が切ったんだからな。忘れるなよ」
「わかってますって」
こうやって、二人は再び地下街を歩き始めた。
絵奈は恵美と別れると家に向かうことにした。地下鉄の改札をくぐり、ホームに立って地下鉄がくるのを待つ。いつもは友達と一緒に家に向かうのだが、今日は一人で帰らなくてはならない、だから妙に周りの視線が気になってしまう。
地下鉄が入って来た。人は全く乗っていなくて、がらがらの車両がやって来た。時間帯が功を奏してのことなのか、絵奈は楽に座ることができた。同じ車両には数十人の乗客しかいないので、さっきまでの緊張感から解放されて絵奈は安心した。
自分の降りる駅までは30分くらいは乗らないと到着しないから、水着の入っているカバンの中からMDを取り出し、ヘッドホンを耳にかけて音楽を聴き始めて退屈な時間を過ごしはじめた。
30分後。何事も無く家の近くの駅に到着した。駅の改札をくぐり抜けると、恵美と祐介のことが気になって、電話をすることにした。さっき、恵美から教えてもらった番号に電話をかける。
その頃、恵美は祐介と地下街を歩いていた。ここの地下街は結構長くてまだまだ先が見えていない。恵美の携帯電話から着うたが流れる、恵美の好きな歌手の曲が着うたになっているのだ。小さな液晶を見てみるとそこには絵奈からの電話だと言うのがわかる。さっそく絵奈から電話がかかって来たことがわかると、すぐに電話に出た。
「どうしたの?絵奈」
「恵美。お兄ちゃんと楽しんでる?あたしは家に帰る途中で近くの駅まで来たの」
「うん。楽しいよ。さっきワンピース買ってもらったし」
「えっ!あのお兄ちゃんがプレゼントだなんてぇ。あたしには何もくれないのに、あたしの分も買ってもらうように言ってね」
「わかったわ。絵奈にも何か買ってもらえるように頑張るね」
恵美は祐介に聞こえないように小さな声で喋る。
「恵美、サンキュー。お兄ちゃんと楽しい時間を過ごしてね」
「うん。また何かあったら電話してね。メールも待ってるから」
「ばいばい」
そう言うと絵奈は電話を電話切った。
祐介がプレゼントをするなんて信じられないと思いながら、家までの道を歩いていく絵奈。やっぱりお兄ちゃんも彼女にはそれなりに尽くすタイプだったなんて初めて聞いた。前にもつきあったことがあったみたいだけど、その時は高いものを買ってあげたなんて聞いたことがなかったから。
駅から絵奈の家までは歩いて10分ほど、周辺は1戸建ての続く住宅街だ。絵奈の家ももちろん一戸建て、門をくぐり抜けると愛犬のラブが出迎えてくれた。ラブは生後2年ぐらいになるオスの柴犬。絵奈がいつも世話をしているので、絵奈が帰ってくるとしっぽを余計に振り回して喜んでいる。
「ただいま〜。ちゃんと留守番してくれた?」
絵奈はその場にしゃがんでラブの目線に合わせてあげる。ラブは舌を出しては絵奈の手をなめて来てくすぐったい、そんな微笑ましい光景からはこのあとに起こる出来事が予想だにできないのだった。
絵奈から電話を受けたあと、恵美と祐介は靴屋さんへと足を運んでいた。さっき高い買い物をしたからと拒んだ祐介だったが、恵美の強引さにはどうやら勝てないらしいかった。相変わらず恵美は色とりどりの靴を見て回っている。
「祐介。これ、可愛いでしょ。履いてみよっかぁ」
恵美は気に入ったものを見つけては試着して行く。黄色いワンピースに似合うように白いのが欲しいと言い出したから、試着するのは白い靴が主体。さっきまではハイヒールを見ていたが、気に入ったものが見あたらなく、ヒールが6cmぐらいのパンプスの中に恵美の気に入ったデザインがあった。
「祐介。これどう?このワンピースにぴったりじゃない?」
そう言っても祐介からは言葉が出ない。
「祐介!感想すら何もないの?」
祐介はふてくされた表情を見せながら恵美に言う。
「いいって言えば、買わなくちゃいけないだろう。似合わないって言うにもいかないし、言葉を無くしてしまうんだって」
「そんなことないって。見てるだけなんだって」
「それならいいけど」
「でもなぁ。このワンピースには私の青いハイヒールが似合わないのよねぇ。服と靴と似合わないのは格好悪いよねぇ。誰かに聞かれたら彼氏が買ってくれないのって言うしか無いでしょ。どうしたらいい?ゆうすけ〜」
すると、祐介は靴屋の外へと出て行こうとしながら捨てセリフを残していった。
「それって、また買って下さいってことだろ。今度は、絶対に買わないからな」
「わかったわよ。私が出すから」
恵美は会計を済ませると自分の履いてきた青いハイヒールを箱に入れてもらった。白いパンプスに履き替えたことで全体的な一体感ができた。
靴屋の前には祐介がふてくされたまま立っている。そんな祐介を横目にして恵美は地下街の流れに入っていった。
「おい。待てよ。恵美」
「あんたなんて知らないって。私が買ってもらいたいって思ったものも買えないような男なんだから」
新しい靴のヒールが、すぐにすり減りそうな音を立てながら、恵美は祐介の方を見向きもせずに前へ前へと進んで行く。後ろから祐介が駆け寄って来て、恵美の怒りをなだめるように言った。
「恵美。今度、また俺が服を買ってやるから。今日のところは勘弁してくれ。今日の持ち合わせじゃ、靴まではとても買えないんだって」
「服買ってくれるって!?それ本当?」
「本当だ。だから、一緒に歩こう」
そう言うと祐介は自分の左手で恵美の右手を握った。しかし、恵美は祐介の手を振り払う。
「手をつないでいいなんてまだ言ってないわよ。まだ怒ってるんだから」
「どうしたら怒りが収まるんだよ」
祐介は一旦恵美を立ち止まらせて言った。
「そうねぇ。疲れてきたからちょっと休まない?とりあえず、奢ってちょうだい」
「コーヒーか?」
すると恵美は首を横に振って答えた。
「チョコレートパフェ」
「おいしい所があるのよ。付いて来て」
恵美は祐介の腕を強引に引っ張りながら喫茶店へと向かおうとした。そのとき、恵美が思い出したかのように一言。
「あっ。その前に私トイレ行きたいんだけど」
こうして、恵美と祐介はトレイに向かうことにした。
祐介は男性用、恵美は女性用に別れて入って行く、女性用のトイレに入った恵美はまたも一番奥にある個室に入った。すると、便器の蓋をとらずにその上に座り、買ってきた袋を地面に置いた。バッグの中から小瓶を取りだし、今度は携帯電話を取り出した。小瓶の中にいる恵美は、見たことの無い黄色いワンピースを見てやるせない思いが込み上がってくるようだった。
左手には本物の恵美の入った小瓶、右手には携帯電話を手に持った恵美。携帯電話を使って絵奈に電話をかけはじめた。本物の恵美に電話をかけているところを見てもらうためだ。
絵奈が自分の部屋でくつろいでいると携帯に電話が入ってきた。携帯の小窓を見ると恵美からの電話だとすぐにわかった。
「恵美。うまくやってる?」
「まぁまぁかな。今トイレから電話してるんだ」
「トイレからって、お兄ちゃんに聞かれちゃまずいってことか」
「そう言うこと。でさぁ。さっき、靴も買ってもらおうと思ったら。祐介が絶対に駄目だって。なかなか頑固なところがあるのねぇ」
「あっ。お兄ちゃんって普通はそうだって。なかなかお金使おうとしないんだって」
「そう?ワンピース買ってくれたじゃない」
「それねぇ。あたしもそんなお兄ちゃんは初めて聞くよ。恵美のことよっぽど気に入ったのかもね」
「でも、靴は駄目なの?」
「ワンピース買ったのが精一杯なんだって」
「そっか」
「あっ。恵美。あとでうちに来ない?あたしなんか暇でさぁ」
「ん〜。そうねぇ。祐介が何て言うかわからないけど。私はいいわよ。うまくやってみるわ」
「なるべく早く来てね」
「わかった」
「ばいばい」
恵美は携帯をバッグにしまうと、ニヤッとした表情を小瓶に向けてやったのだ。
恵美はまだトイレ個室に座っている。目の前にある小瓶を手に持って、中にいる本物の恵美に向けて話しをする。
「絵奈ちゃんって、あいつの妹よ。あなたのように小瓶の中に入れてあげようかなぁ」
小瓶の中にいる恵美は精神的にはかなり参っているようだった。
「あなたがこの小瓶から出られたとしても、小瓶のことは記憶に残らないからね。また、あとで遊んであげる」
そう言ってバッグの中に小瓶を閉まって、個室から出て行った。
トイレの前では祐介が待っていた。恵美の顔を見かけると、ほっとした笑顔を見せてくれるので、恵美も笑顔で答える。
「すっきりした?」
「そんなの聞いて恥ずかしくない?」
「恵美に聞くのは恥ずかしいことじゃないだろ」
「そっか」
そう言うと恵美は祐介の胸の中に頭を入れる。
「そういや、チョコパフェ食べに行くんじゃ無かったか?」
祐介がそう言うと、恵美はぺろっと舌を出す。
「あっ。そうだったっけ。私、もう食べたい感じしなくなっちゃった。代わりに行きたいところあるんだけど」
そう言いながら恵美は祐介の左腕をつかんでいた。
「ん?どこ行きたい?」
祐介はクールな顔で答える。その表情を見て、恵美は内心笑っていた。
「祐介の家」
すると、祐介はあわてたような表情を浮かべる。
「えっ!?うちって」
「そうよ。祐介のうちに行きたいんだけど、駄目かな?」
「俺のうちに来てどうするんだよ。それに、まだ時間も経ってないのに、家に入れていいのかよ〜」
「部屋の中が片づいてないから嫌なんでしょ。わかったわ。行きたいって言わないから」
そう言うと恵美は祐介から離れて道の反対に向かって歩き出す。祐介は恵美を追いかけ恵美の行く手を阻んだ。
「怒ったのかよ。おい、恵美」
恵美は何も言わずに、前へ進もうとする。
「痛いって、早く行かせてよ〜」
恵美の怒った表情を見て、祐介はどうやら考えを変えたようだ。
「わかった。わかったって。恵美をうちに入れてやるよ」
すると恵美の怒りが一気に収まったようだ。
「そう?ほんとにいいの?」
「いいって。俺のうちに来いよ。ただし……」
祐介は少し間を開けてから言葉を続けた。
「家の前でちょっと待ってくれよな」
祐介の顔を見ながら、恵美は軽い笑顔を見せながら応える。
「うん」
二人はそのまま地下街をまっすぐと歩いた。このまままっすぐ行ったところにも地下鉄の駅があり、そこから祐介の家に向かうことができるのだ。待ち合わせに使った駅よりも利用する人は少ないようだが、広さだけはさっきの駅に負けていない駅だ。
祐介は自動券売機で2枚の乗車券を買って来て、1枚を恵美に渡す。改札を通りプラットホームで二人は電車が来るのを待ち始めた。地下鉄を待っている間、二人の間には会話が無く、ただ、手をつないでいるだけだった。
恵美はそれだけでも、なんとなく温かい気持ちを感じていた。不思議な思い、祐介に対する恵美の気持ちがこんなに温かいものだとは、普通には体験することのできなこの気持ち、本物の恵美から奪っているという優越感を感じているのだった。
電車に乗った二人は、隣に座りながら、祐介が恵美の肩に手をかけて来る。祐介の家がある駅まで、恵美はこうやって祐介の中に守られていた。そして、駅に到着すると、いよいよ恵美は祐介の家の前まで来たのだ。
祐介の家に着くと、この家の番犬であるラブが恵美に向けて吠えながら襲いかかって来た。もちろん鎖があるために本当に襲われることは無いが、さすがに番犬としてのしつけがしっかりと行き届いている犬。恵美に対しても吠えてきた。しかし、そんなラブも祐介がいるのでおとなしくなり、恵美にも慣れたようだ。
この周辺は住宅街が続くためか至って静かな環境。祐介が自分の家の鍵を開けている間、恵美はこの家の愛犬であるラブと遊びながら家の外観を見ていた。思った以上に裕福な家らしく、恵美の住んでいるマンションはもちろん、祐介の目の前にいる恵美の正体である康夫の住むアパートとは桁違いの一軒家だった。
祐介が玄関を開けると恵美に入るように促す。恵美は祐介のあとを追うようにして広い玄関へと入った。玄関の空間だけでも1つの部屋ができるくらいの広さ。横にある下駄箱はまるでクローゼットのようだった。
「祐介の家って、大きいわね。私玄関に入る前からびっくりしちゃった」
「まぁね。うちの親父のおかげだよ。俺にはお金が無いけど、この家は親父が一代で築いたものだから」
「そうなんだ」
そう言うと恵美はさっき自分で買ってきた白いハイヒールを脱ぎ、きれいに揃えて玄関に置いた。この時に祐介の脱ぎ散らした靴もきれいにそろえてやる。本来ならやらないこともすんなりとできる。これも恵美の性格を引き出している成果らしかった。
玄関でスリッパに履き替えた恵美は、祐介のあとをついて行った。ウサギ小屋に住んでいる恵美にとって、この家の中はまるで迷路のように大きく感じたからでもある。階段を上がっていき、祐介は2階にある自分の部屋を開けた。
祐介の部屋。そこは12畳はあろうかと思う大きさで、オーシャンブルーで統一されたインテリアが、祐介という男の魅力をさらに高めているようだった。祐介はベッドの上に座ると、ドアのところで立ち止まっている恵美に横に座るように手招きをした。恵美はドアを閉めてベッドの方へ近づいてj来る。
「ここが祐介の部屋?」
「まぁ。そんなところだけど」
恵美は祐介のベッドに腰をかけながら祐介の部屋をぐるりと見渡している。
「私にはなんだか落ち着かない感じ。見るからに高そうな家具ばかりだし」
「そんなことないよ。この部屋のインテリアは母さんの趣味で集めたものばかりだから」
「そうなの?」
「そうだって。この家を建てる時には母さんがすべてのインテリアを揃えてたよ」
「じゃあ、絵奈ちゃんの部屋も?」
「そう。絵奈の部屋も物はこの部屋と同じで色彩が違う感じだよ」
そういう風に話しながら恵美は祐介の腕の中へ自然に入り込んで行った。
「ねぇ。祐介。一つ聞いていい?」
「なんだ?」
「この部屋に何人の女を連れ込んだことあるの?正直に応えてみてよ」
「何人って。そんなの数えるだけしかいないぞ」
すると恵美の表情がちょっとむっとする。
「数えるだけって、やっぱいるんじゃない」
「そりゃな。俺だってこの年で初めての彼女ってわけじゃないもの」
すると、恵美はベットの枕元に視線を移す。
「そうよね。犠牲者がいるのは当然の年齢よね。じゃあ、あそこのピアスもそれをもの語ってるのかしら?」
祐介は枕元を見ると金色のハート形をしたピアスが落ちているのに気づく。
「えっ。あれは何かの間違いじゃないの?」
祐介は枕元に落ちているピアスを手に取りながら、何か考えているようだった。
「これってうちの母さんのものだよ」
ピアスを恵美に見せながら弁解して来た。
「えっ。本当!?でも、こんなところにあるなんておかしいわよね」
恵美は手にとったピアスをじっくりと見ながら、今度は祐介の目をじっと見つめた。
「祐介のお母さんいつ帰ってくるの?」
「夕方になれば帰ってくるはずだよ」
「じゃあ、その時にでもはっきりするわね。その時までこれは私が預かっておくわ」
すると、恵美は自分のワンピースにある隠しポケットの中へピアスを入れた。
二人の時間をこうやって過ごしていると廊下の方で足音がするのが聞こえた。足音は徐々に祐介の部屋へと近づき、祐介の部屋の前で止まった。
「お兄ちゃんいるの?」
どうやら声の主は絵奈のようだった。絵奈がドアを開けようとしても鍵がかけられていて開けることができなかった。
「恵美も来てるんでしょ?ねぇ」
「絵奈。ちょっと待ってて」
祐介が動く前に恵美がドアを開けに向かった。恵美が鍵を開けるとドアが開いて、目の前にはグレーの部屋着に着替えた絵奈が立っていた。
「やっぱり来てたんだ。恵美」
「うん。あとで遊ぼうね」
「わかった。まずはお兄ちゃんと楽しんでよ。私は何も気にしないから」
そう言って絵奈は自分の部屋の方へとスタスタと歩いて行った。
恵美が祐介の家に到着した頃も文恵はまだ恵美の家にいた。前の日に飲んだ後遺症なのか、昼までゆっくり寝ていてても頭が少し痛い感じが残っている。昨日起きた出来事について覚えていないなんて、不甲斐なさを感じていたが、恵美の家で休んで少しは楽になった。
文恵は起きてからシャワーを浴びたのだが、シャワーを浴びている間も今まで何があったのか思い出そうとしていた。思い出そうとしても思い出せない、どうやら昨日のことはうろ覚えになっているようだ。
恵美の部屋には何度も来ているので、部屋の使い勝手もわかっている。シャワーからあがった文恵は、バスタオルを体に巻き付けたままで冷蔵庫から牛乳パックを取り出した。洗ったばかりのコップをシンクから取ってきて、その中へ注いだ。
文恵は久しぶりにのんびりとした休日を過ごすことに決めた。このところ仕事で疲れていたのかも知れないし、たまには何もしない休日もいいと思ってのことだ。そうやってゆっくりと準備をしてから自分の家に向かうことにした。
ちょっと汗の匂いやアルコールの匂いが残った服を着ると軽くメイクをして準備が整った。ここから文恵の家までは地下鉄に乗って15分ほどかかる。まずは家を出て行く時は恵美にメールを送って欲しいと頼まれていたので、さっそく恵美に送ってあげた。
玄関にある青のパンプスを履いて恵美の家を出た。扉がちゃんと閉まっているのを確認すると、文恵は久しぶりに自分の足で地面を歩いて近くの地下鉄駅へと向かった。
---------------------------------------------------------------------------
さっき祐介の部屋をのぞきに来た絵奈は、コーラルピンクを基調にした部屋に戻った。祐介の部屋とはまた違って落ち着いた暖かみを感じる部屋。ベッドの上には大きなイヌのぬいぐるみが置いてある。絵奈はそのぬいぐるみを抱きかかえるようにベッドの上に座ると、携帯を片手に持ちながら恵美のアドレスを眺めていた。
「お兄ちゃんの彼女か……ってことは私の何?」
天井を見上げながら絵奈は初めて会った恵美に好印象を持っているようだ。さっきからずっと恵美のことばかり考えている。祐介のような兄しかいなかったのでどこかお姉ちゃんに憧れる気持ちがあるようだ。そして、絵奈はいつの間にかイヌのぬいぐるみの中に包まれながら眠りについてしまった。
--------------------------------------------------------------------------------
絵奈が恵美がいるかどうかを見に来たあと、恵美の携帯にメールが届いた。メールの送り主を見ると文恵からのメッセージで、これから家に帰るとのことだった。ついでに昨日の出来事はやっぱり覚えていないということも付け加えられていた。恵美はこのメールを見てニヤッとした表情に変わった。
このニヤッとした表情を祐介に見つけられ、恵美は慌てて普通の表情へと戻した。しかし、時すでに遅し祐介には不思議な感じに写ってしまったようだ。
「恵美。携帯見て何ニヤッとしてたんだ」
「あっ。友達からのメールがおもしろくてね」
恵美は携帯を閉じながら、祐介と目線を合わせないようにしている。
「そう。何かおもしろいことあんのかなって思ったけど、そんなことね」
祐介はこれ以上追求しなかった。どうやら、個人の根深いところまで聞いてくるタイプでは無いらしい。
相変わらず二人は祐介のベッドの上に座っていた。祐介の腕が恵美を包み込むような感じで、恵美はこの腕が暖かい気持ちにさせてくれることを知った。しかし、ちょっとお腹の調子がよくなくて下腹部に違和感を同時に感じていた。恵美はとっさにトイレに行くことを思いついた。
「あのさ。私、トイレ行きたいんだけど、どこにあるの?」
お腹の下の方を手で押さえながら祐介に聞いた。
「部屋を出て、さっき上ってきた階段の方に行くとすぐにわかると思うけど」
祐介がその言葉を言うや否や恵美はトイレに駆け込んで行った。
恵美は祐介の家のトイレに駆け込むと、大慌てでワンピースの裾を捲し上げ、ショーツを下げるとお腹の中に溜まっていたものを便器の中に吐き出した。ウォシュレットを使ってお湯でお尻をしっかりと洗うと乾燥させながらホッとした息をついた。
「危ないところだったぜ。急にお腹が痛くなり出して、一時はどうなるかと思ったぞ」
恵美は一人でいる空間で独り言をつぶやいていた。冷静さを無くして、恵美の行動を真似ることはできないでいるらしかった。
「少し、ここで落ち着かせてから祐介の奴と遊んでやるかぁ。。。待てよ」
そう言うと、恵美にいい考えが浮かんでいた。
「そろそろ、あいつをここに呼ぶことにするか。俺はあの絵奈ちゃんがたまらなく気に入ったんだが、俺一人の状況じゃちょっとまずいからな。よし、決めた」
そう言うと必死に持ってきた携帯を手に取り、どこかへ電話をかけ始めた。
「もしもし、直樹か?」
直樹とは田口康夫の親友の真矢直樹(まやなおき)のことだ。恵美の声で聞かれた直樹は知らない声に驚いているようだ。
「知らない女の声で直樹かって、あんた誰?」
全然気づかないので、恵美はちょっとここで直樹をおちょくってやることにした。
「私よ。田口康夫って知ってるわよね」
恵美はとびっきりの色声を使って話し出す。
「あぁ、もちろん。俺の親友だからな。であんたは、康夫とどう言う関係なのさ」
「んっと。会社の同僚で恵美って言うわ。田口さんに頼まれてあなたに電話してくれないかってね」
直樹はまだ恵美の正体に気づかないようだ。
「なんで、あんたの携帯からかける必要があるのさ。康夫の奴から何を頼まれたって?」
「田口さんがねぇ。頼まれたのは、小瓶の効果がすごいって伝えて欲しいって、それだけだったわ」
直樹は小瓶と聞くと一瞬にしてぴ〜んと来た。
「メグミさんだっけ、なんであんたが小瓶のことを知ってる?あれは俺と康夫との間で秘密にしていることだ、もしかして、康夫なのか?」
「あなた何馬鹿なこと言ってるの?私が田口さんだなんて。そんなこと、あり得る話よね」
「やっぱりだ。康夫だろ。メグミって会社の同僚なんだろ。まさか本当に小瓶を使ってみたんだな」
「鈍感なのね。直樹のこと信用してるの私しかいないじゃない」
恵美は相変わらず恵美の話し方そのものを使っていた。しかし、直樹にとってはたまらない事実であった。
「俺だって、お前のこと信用してるよ。やっぱり、あの小瓶の効果って本当だったんだな」
「そうね。すっかり恵美に成りきっちゃったわ」
「どうやら、変身したら完璧になるみたいだな。俺でさえ最初は気づかないわけだよ」
「そうだろ。俺の迫真の演技力もまんざらじゃないだろ」
思わず康夫の口調が出てしまう。
「お前、その声でそのしゃべり方はやめてくれよな。俺と話をしてるのはメグミさんなんだから、元通りやってくれなきゃ」
「わかったわ。直樹ったら女が好きなんだから」
「俺以上にお前の方がすごいだろ」
「お前って何よ。恵美って呼びなさいよ。ちゃんと名前があるんですから」
「いいから、いいから。で、何か俺に用があって電話したんだろ。今どこだよ」
「今?彼氏の家に来てるわよ。あとで、詳しいことはメールするから。とにかく、小瓶を何本か用意して持ってきてくれる?」
「あぁ。わかったよ。俺も小瓶を使ってお前のいるところに潜り込んでやるから」
「うん。ありがとう」
そこまで言うと、恵美は携帯の通話口にチューをした。
「すっかり、メグミって子に慣れちまったな。あとで俺が行くから待ってろよ」
電話を切ると、恵美はしっかりと手を洗い、トイレから廊下に出た。廊下に出ると絵奈が自分の部屋のドアを少し開けて、顔を出しながら、手招きをしている。祐介の部屋を開けて、ちょっと絵奈の部屋に行ってくると言付けをすると、恵美は絵奈の部屋へ向かって行った。
「なんなの?絵奈。後で遊ぼうって言ったのに、祐介に言ってちょっとこっちへ来たんだけど……」
そう言いながら恵美はバッグを持って絵奈の部屋に入っていく、コーラルピンクで統一された部屋の中は祐介の部屋とは違って可愛い雰囲気だ。クローゼットの前には絵奈の制服がかかっていて、当の本人はベッドの上で携帯と睨めっこをしていた。
「恵美。やっと私に会いに来てくれたんだね」
携帯をちょっとよけると絵奈の顔が見えた。
「絵奈の部屋って可愛いわね。私の部屋もこんなに可愛かったら勉強できたかも知れないなぁ」
大きな机が置いてあって、ちょこんとパソコンが置かれていてる。無造作にデジカメが置いてあるのを見ると、恵美はそのデジカメを手に取った。
「あっ。デジカメだ。これって絵奈のものなの?」
「うん。そうだよ。私のもの。中の写真見ていいよ」
すると恵美は再生モードに切り替えてから電源を入れる。思ったよりも起動が早かった。
「あれっ。これって部屋の中で写真撮ってない?絵奈しか写ってないじゃない」
写真に写っているのは絵奈ばかり、しかも部屋の中で何かポーズを撮りながら写っていた。ちょっと目を横にやると三脚が置いてあるのがわかる。
「これに載せて撮ったのね」
すると、絵奈は突然ベッドから飛び上がって恵美を抱きしめた。
「私って可愛いでしょ。恵美みたいに色っぽさには負けるけど、若さ溢れる18歳だからね」
そして、絵奈は机の上にあったデジカメのメモリーに交換しはじめた。
「こっちにはもっと面白い写真が入ってるよ」
そう言われて恵美がのぞき込むと、そこに写っていたのは絵奈のパンチラ写真だった。
「えっ。絵奈ってこんなのに興味があるの?」
すると、絵奈はニヤけた顔をしながらうすら笑いをしている。
「そうなんだ。恵美もやってあげよっか。結構お金にもなるし〜」
そして、何枚か写真を見ている内に最後に出てきた写真を見て、恵美の表情が固まってしまった。ちょっと青ざめたような表情をしている。
「これって何なの?」
そこに写ったのはなんと、小さな小瓶に入った裸の絵奈を撮った写真だった。
恵美は冷や冷やしながら、絵奈の口から出てくる言葉を待った。
「えっ?どの写真?」
そう言うと恵美は絵奈に小瓶の写真を見せてやる。
(あっ。やべぇ、消し忘れた)
恵美に聞こえないくらいの小さな声で絵奈は独り言を言った。
「何なのこの写真?」
執拗に聞いてくる恵美に対し、絵奈は何も言おうとしなかった。そして、絵奈は黙りこくったままドアの方へと向かい、鍵をしっかりと閉めた。絵奈の部屋にはライトアップピアノが置いてあるため、部屋の防音設備はしっかりとしている。何か重要な話をしはじめるようだ。
「もしかして、あなた絵奈じゃないわね」
恵美の口から出たの一言に、絵奈はすぐにビクっと反応する。すると、絵奈はこう反論して来た。
「あなたも恵美じゃないのよね」
今度は恵美の方がビビってしまった。
「そんなわけないでしょ。私は後藤恵美よ。誰が見たってそう思うじゃないの」
すると、絵奈は鋭い目線で恵美を睨み付けてきた。
「いや、誰が見たっては嘘でしょ。同じことやってればわかるじゃない、康夫ったら鈍感!」
絵奈の口から康夫の名前が出てきたのだ。
それでも恵美は平静を誘うかのようにしているが、目の前の絵奈が絵奈では無いことはわかったし、康夫のことを知っている奴と言うこともわかった。もしかして、こう言うことができるのは……そう、康夫の中に思い浮かんだのは真矢直樹の姿だった。
「お前。ひょっとして直樹か?」
絵奈はヒョロンとしたまま嫌らしい表情で恵美を見ている。
「康夫。ようやく分かったな。お前とさっき電話したばかりの俺だよ」
すると直樹は枕の後ろに隠してあった直樹の携帯電話を取り出した。
「お前いつから?絵奈に変身してたんだよ」
康夫はすっかり恵美の演技を忘れている。
「ん?それなんだけど、結構前からだぜ。この娘がプールにやって来た時にたまたま通りかかって、俺がちょっと話しかけてやったんだよ。すぐにひかかって、駅のトイレで変身してやったってわけだ。お前からここ最近連絡が無いから、もしかしてたらと思ったらお前も同じことやってたなんてな。それに、なんて世界は狭いものか。さっきまで全然気づかなかったぜ」
絵奈は女子高生に似合わない口調で話した。
「そうか。お前からもらった小瓶を使って、女子社員になってみたんだけど、まさかお前も一緒に小瓶を使ってたなんて知らなかったぞ」
「それはこっちの台詞だって、俺だってお前がこの娘の兄貴の彼女になってるなんて思ってもいなかったからな。さっき、トイレで電話して来た時にようやく気づいたってわけだ」
「じゃ。さっきのはどうやったんだ?」
端からみると恵美が絵奈に向かって話しかけている。
「何が?」
「お前の電話に出た時は、絵奈の変身して無かったじゃないかって」
「そんなの単純なことだろ。この部屋には誰も入れねぇんだ。電話がかかって来たら変身を解くだけでいい。蓋をちょっとゆるめればすぐに変身は解けるからな」
ちょっと考えてみればすぐにわかることだったが、恵美に変身している康夫にとっては不思議なことだった。
「あぁ。そっか、そっか。それで、さっき」
「そうそう。トイレから出て来た時には、すぐに絵奈に変身し直してお前を呼び入れたってわけだ」
「お前って、見かけによらず頭が冴えるよなぁ」
すると、絵奈の長い髪をちょっと横に流してから絵奈らしい座り方に座り直した。
「だって。こんなに可愛い絵奈ですもの」
恵美もそれに応えるように言った。
「そっか。絵奈ってものすごく可愛いものね。あのね。お願いがあるんだけど、今度は私が絵奈になりたいの。変わってもらえるかな?」
すると、絵奈は再びニヤリとした表情を取り戻した。
「もちろんいいわよ。私も恵美のような大人の女になってみたいもの」
そうして、俺たちはお互いの変身を入れ替えることにした。
ベッドから立ち上がった絵奈はクローゼットを開けて、何かを探しはじめた。恵美はバッグの中から本当の恵美が入っている小瓶を取り出し机の上に置いた。絵奈もすぐに本当の絵奈が入っている小瓶を机の上に置いた。
小瓶が2つ揃って、中に入ってるのは裸の女性、しかもその女性に変身してる自分たちがいる。これだけでもかなり興奮しそうな状況だった。
「そう言えば。お前にはまだ教えてなかったよな。こういう状況でお互いの変身だけを入れ替えることができるって方法」
絵奈が恵美にそう言った。
「そんな方法があるのか?俺はてっきりお互いに変身を解いてからやるのかと思ってたよ。で、どうすればいいんだ?」
恵美は目の前にある2本の小瓶をよくみてやる。2人の女性は小瓶の中に長い時間入っているためか、動く気力すら無くなっているらしい。目の前に同じようにされているお互いの体を見たらなおさら気落ちしたことだろう。
「それはだな。簡単なことだって。まずはお前が絵奈の小瓶を左手の掌で掴むように持ってくれ。そして、俺が恵美の小瓶を同じように左手の掌で掴むように持つ。この時に右手で小瓶を持っても何も起こらないからな。そして、そのままお互いの右手で握手をしながら3回縦に振ると、3回目で変身した体同士の入れ替わりが起こるようになってる。簡単だろ」
そして、絵奈が言うようにお互いに相手の小瓶を左手の掌で掴んだ。
「直樹。このまま右手で握手して3回縦に振ればいいんだよな」
「その通り。じゃあ行くからな」
「わかった。やってくれ」
「いち」……「にぃ」……「さん」
右手を3回降ると、二人は一瞬頭の中が真っ白になって行くのがわかった。そして、それはこれから始まろうとしていることへの始まりでもあった。
ここは祐介の部屋。ちょっと行ってくると言った割にはなかなか恵美が戻って来ない。女同士で何をしているというのか、恵美が俺よりも絵奈のことを気にしているのなら気に入らない。一人部屋に残された祐介はちょっと気分が悪いようだった。
しかし、そんなことを考えている矢先に、恵美が部屋に戻って来たのだ。待ちかねていた祐介は恵美の前に立ちふさがる。
「今まで何してたんだよ」
「絵奈ちゃんとちょっとだけ話してました。祐介さん怒らないで」
そう言いながら、恵美は祐介の唇に自分の唇を重ねた。突然のことに祐介も戸惑ってはいたが、舌を入れてくる恵美の濃厚なキスにしっかりと応えていた。二人はそのままベッドの上に倒れ込んだ。
祐介の上に恵美が乗っているような形、恵美はキスをやめると祐介の体をまたいで座りだした。
「ねぇ。祐介って我慢してない?」
「我慢って。何を我慢してるってことかな?俺にはさっぱりわからないけど」
祐介はそう言っているが、恵美は祐介のモノが興奮状態にあることがわかっていた。
「これでも、我慢してないって言えるの?」
恵美は祐介のモノをズボンの上からさすっていた。
「どう?気持ちわよね。でも、もっと気持ちよくさせてあ・げ・る」
そう言うと、恵美は祐介のモノを社会の窓から取り出して、スベスベの手で直接さわりはじめた。
「恵美ったら、昼間っから何をするんだよ。絵奈だっているんだし」
「祐介が気持ちよくなるために協力してるのよ。絵奈はさっきでかけたから大丈夫よ。これからは二人っきりですごせるの。祐介のその表情ってことは満更でもないのよね」
黄色いワンピース姿の恵美が祐介の足にまたがり、祐介のモノを直接さすっている光景がそこにはあった。
「ねぇ。このワンピース邪魔なんだけど、脱がしてくれる?」
恵美がそう言うと、祐介は更に興奮しはじめたようだ。
「脱がしてやるよ。後ろ向いて」
恵美は祐介に言われるがままに後ろを向いた。首元にあるファスナーを腰のあたりまでおろすと、恵美の柔肌が露呈してきた。そして、祐介は恵美の着ているワンピースを強引に脱がして言った。
「祐介も脱いで」
恵美の一言で祐介はあっと言うまに服を脱いでしまった。さっきまで精神的なガードをしていたようだったが、恵美が心を開いたと思った途端に、そんなものが解き放たれてしまったようだ。
二人は祐介のベッドの上で裸の体を寄せ合うと、更に激しい交わりをするようになった。祐介の部屋の中で恵美と祐介の快楽を伴う声が響いていた。祐介が恵美の体を嘗め尽くすと、恵美の方も逆に祐介の体を嘗め尽くしていた。
「ねぇ。祐介。これつけてよ」
しばらく体の交わりをしたあとで、恵美は突然ゴムを取り出し、祐介のモノにはめていく。出会って間もない二人にしては至ってハイペースだ。ゴムの皮に包まれた祐介のモノが恵美の体へ挿入されて行く、二人の交わりはまだまだ続くのであった。
祐介の部屋に恵美が戻る前のこと。そう、直樹が変身していた絵奈と康夫が変身していた恵美がお互いの変身を入れ替えたばかりだった。さっきまで絵奈に変身していた直樹は恵美に変身して、恵美に変身していた康夫は絵奈になった。客観的に見ればお互いに入れ替わったように見えるが実際にはそうでは無かった。
その証拠に着ている服はさっきのままであった。恵美になった直樹はさっきまで絵奈として着ていたグレーの部屋着を着ている。サイズが小さいためかストレッチ素材がずいぶんと伸びている。そして、絵奈になった康夫はと言うと、恵美の着ていた黄色のワンピースを着ていた。絵奈の方もサイズが大きいようだ。
とりあえず二人はお互いの着ているものを全て交換することにした。二人は恥ずかしさを見せることも無く、服を脱いでいる。もちろん下着もである。お互いに何も付けていない、全身素っ裸の状態になった。二人は不気味な笑いを浮かべながら、お互いの白い肌を見つめ合っていた。均整のとれたスタイルの恵美と、まだ成長途中の絵奈のスタイルが絵奈の部屋にある大きな鏡に映し出された。
「なぁ。康夫。このまま写真でも撮らないか?」
恵美の姿をした直樹が絵奈の姿をした康夫に聞いてきた。
「そっか。デジカメがそこにあったよな。これってホントに絵奈のなのか?」
「それって俺のモノだよ。この機会にたくさん撮っておこうぜ。」
二人は小瓶の中に入っている二人を目の前にしてやりたい放題だった。
絵奈のデジカメでお互いに裸の姿を写すと、お互いに自分の下着を身につけた。絵奈は出かけることにしたので、なぜかクローゼットの前にあった制服に手を取った。絵奈の制服は典型的な紺のセーラー服だった。スカートはもちろん紺のヒダスカート、足を入れてファスナーを留めると腰でひっかかった。絵奈の膝頭が見える膝上丈だった。
そして、上着は中間服だったので白をベースとした長袖に紺の襟がついて、そこには2本の白いラインが入っている。横のファスナーを開いて頭からかぶると、ファスナーを留めてやる。着替えている間、恵美はじっと見つめていた。最後に、紺のスカーフを手に取ると、慣れた手つきで襟の下に結び目をつくってやる。この上に紺のカーディガンを羽織って着替えが完成した。
さすがに康夫だけあって、絵奈の能力を完全に引き出すのはお手のものだ。最後にクローゼットの中から紺のハイソックスを見つけて、それを履いた。着替えを終えると、まだ下着姿の恵美の前でクルッと一回転してみせた。
「どう?恵美。これで完璧でしょ」
すると下着姿のままで恵美は答えた。
「さすが。どこから見ても絵奈にしか見えない」
「だって、私は絵奈だもん。当然よ」
そう言って絵奈は軽く高笑いをした。
「今度は、恵美の番よ。着替えるの見守ってあげるから」
「康夫ったら。すっかり絵奈に成りきってるな」
直樹は恵美の体にまだ慣れていないようだった。
それでも恵美の体に変身した直樹は、さっき絵奈がベッドの上に脱ぎ捨てた黄色のワンピースを手に取り、背中のファスナーに足をゆっくりと入れた。右手を後ろに回して、ファスナーを上まで上げようと思うが、上まで上がらない。
「康夫。ファスナー上げるの手伝ってくれないか?」
絵奈の方を見ながらそう言ったが、絵奈は助けてくれる気配がなかった。
「康夫って誰?私は絵奈なんだけど」
「ん?あっ。絵奈。ファスナーあげてちょうだい」
「うん。わかったよ。恵美」
そう言って恵美のファスナーを完全に閉めることができた。
ワンピースの着心地を確かめながら、目の前の鏡に立つ恵美。
「これで私も完璧ね。端から見るとさっきまでと同じように見えるだろうけど、私たちってさっきまでと違うのよね。フフフ」
恵美は軽く笑っていると、絵奈が隣にやって来て、同じように笑った。
「私たちって姉妹みたいだね。恵美」
「そう?絵奈の体、気に入ったの?」
恵美は絵奈になんとなく気になって聞いてみた。
「うん。恵美の時よりも若いなって」
「そりゃ当然じゃない。でも、私だって若いのよ」
「そっか。大人の女性が好きだもんね」
このままだとお互いの会話が絶え間なく続きそうだ。絵奈は恵美から絵奈の入った小瓶をもらうと、空の小瓶を3本もらった。
「とりあえず、今は3本しかもってないから、それで我慢して。それと、この3本は新しい効果があるからね、使ってみてからのお楽しみってことにしておくわ」
直樹もどうやら恵美の体に慣れてきたようだ。
「恵美。ありがと。私これからでかけて来るからね。セーラー服を着て外出するの子供の頃の夢だったしね。あなたのおかげでその夢がようやく叶うんだなって」
「そうよね。絵奈ちゃんには悪いけど、私たちの願いのためにはちょっと我慢してもらうわね。気を付けて行って来てね」
そう言うと絵奈は本物の絵奈の入った小瓶と空の新しい小瓶を3本、それにデジカメと勉強道具をカバンの中に入れると部屋から出て行きました。
玄関で黒いローファー型革靴を見つけると、それに絵奈の小さな足を入れていきました。玄関の扉を開けると風がスカートの中に入って来てスースーとした感じ、絵奈になった康夫は図書館へ向かいました。
図書館は駅のすぐそば、絵奈になった康夫はさっきと逆の方向へと歩き出しました。憧れのセーラー服と言うこともあって、気分はノリノリ、軽く飛び跳ねるかのように歩いています。周りからはちょっと大胆かとも思えるステップを踏んでいるに違いありません。すれ違う人たちが絵奈の方をじろじろと見てくるからです。
それでも康夫はそんな感覚がとても心地よく思えて、更には絵奈の若さがとてもいいものだと歩きながら感じていたのです。歩くたびにプリーツスカートがふわふわと揺れて、風が強くなると足にべったりとついてきます。
絵奈は図書館への道を歩きながら携帯電話をかばんの中から取りだし、メールを打ち始めました。絵奈の友達の田島優奈(たじまゆな)と佐伯奈美(さいきなみ)の2人に対して宛てるメールだと言うのが送信先を見て分かります。
内容はどうやら図書館で一緒に勉強しない?とのこと、夕方の図書館に集まって勉強をするなんてことで、絵奈も集まってくれるのか不安があったようです。しかし、すぐに返事が返ってきて、二人とも「オッケー」の返事が返ってきました。このメールが送られて来た時に、絵奈は思わず軽くガッツポーズをつくっていました。
道を歩きながら、ガッツポーズを出してる時には誰にも見られていませんでしたが、これからはもっと絵奈らしく振る舞おうと、自分に向かって注意を促しているようでした。
そして、10分ほどで図書館の前に到着しました。図書館と言っても青少年向けの図書館で、高校生が利用しやすい環境のため、この図書館には高校生の利用者が多いのです。絵奈は土曜日で学校へ行かないにも関わらず制服を着たまま図書館の前で二人の友達を待っています。
春先とは言っても、図書館の前で待っていると少し肌寒さを感じる絵奈。スカートの中に入ってくる風は心地よいよりも冷たく感じているようでした。結局、先に図書館へ入ってしまうことにした絵奈は、まずはトイレへと向かいます。女性用のトイレに入ると、一番奥の個室にノックして、誰もいないのを確かめてから中に入りました。しっかりと鍵を閉めて、便座を閉めたままその上に腰を下ろしました。
携帯電話で二人に中で待っていることを伝えると、それぞれちょっと遅れるとすぐに返事が返ってきました。時間があるので、絵奈はさっきかばんに入れてきたものを確認することにします。本物の絵奈が入っている小瓶と、新しい空の小瓶3本があることを確認すると新しい空の小瓶の中から1本を取り出して、直樹が言っていた新しい小瓶の秘密を思い出しました。
その内容を要約してみると、新しい小瓶は前のものと違って外からは透明に見るのですが、実は中からはただの鏡にしか見えません。外の様子をうかがい知ることができなくなるため、安心して変身することができます。名前を呼んだ人が近くにいる場合に小瓶の中に入れることができるのは同じで、小さくなりながら裸の姿で中に入って行きます。服は小さくならないので、その場に残ることになります。
そして、キャップを閉めても変身は始まりません。小瓶を飲み込むことで中に閉じこめた人と同じ姿に変身できるのです。小瓶が体の中に入ってしまうので、小瓶を隠す場所に困ることも無いのです。あとは、その場に残された服や靴を着替えればいいのです。しかし、自分の着ていた身につけていたものが残るので、これは白い小瓶の中に入れておくことができて、同様に飲み込んでしまえば隠し場所に困りません。小瓶は体の中から好きなときに取り出すことができて、それは口から出て来ます。
更に、新しい小瓶だと重ねて変身することも可能。絵奈の姿のまま違う人に変身をすることが可能なので、変身を一度解かなければならなかった点が改良されていた。ちょっと使い方が難しくなったが、絵奈は新しい小瓶をすぐに使いたくてしょうがないような表情をしていた。トイレの中で笑いが止まらなかったのです。
「ねぇ、祐介。気持ちよかった?」
康夫の変身した絵奈が図書館へ到着した頃、直樹の変身した恵美と祐介はベッドの上でゆったりとした時を過ごしていた。ベッドの中に二人は抱き合ったまま寝ている。祐介の中に恵美が包み込まれているような状態。祐介は気持ちよく寝ていた。
「祐介。眠っちゃったの?……睡眠薬ようやく効いたみたいね」
祐介が眠っているのを確認しながら恵美はゆっくりとベッドの中から出た。下着すら着けていない姿のまま祐介の顔をじっ〜と見ていた。
「こいつ、本気で恵美のこと好きみたいだな。恵美の本当の気持ちも知らないくせに……」
そういうと恵美のバッグの中に隠していた本物の恵美が中に入っている小瓶を取り出した。中にはやることが無く退屈な恵美の姿が現れた。小瓶の中の恵美は目の前に全裸の自分がいやらしそうに見つめていることで、衝撃を受けているようにも見える。
「何々?小瓶の中で喚いても誰にも聞こえないって、恵美さん」
そういうと、小瓶を寝ている祐介の目の前まで持って行った。
「こいつが祐介だよ。まだ本当の恵美とは会ったことが無いのに、すっかり本物だと思って、一気に裸の関係まで……」
小瓶の中では目の前のことを見ていられない恵美の姿があった。
「どうせ小瓶の中にいる記憶は無くなるんだ。聞くも聞かないも同じだよ。せっかくだからあんたの言葉を聞かせてよ」
そういいながら、バッグの中に手を入れるとポストイットのようなものを取り出した。そして、小瓶にペタッと貼り付けると、ポストイットのようなものから音が聞こえてきた。すすり泣きのようだった。
「この小瓶用につくったポストイット型スピーカー。これを取り付けると小瓶の中の音声が聞こえるんだけど、泣いていちゃ君の大事な声が聞こえないじゃない、一緒に話そうよ」
すると、小瓶の中からはすすり泣きを抑えながら声が聞こえてきた。
『あなたって一体誰なのよ。こんなことして何が楽しいの?』
「楽しいんだって。あんたのように幸せそうに暮らしているのが気に入らない親友の頼みからはじまったことだからな」
『人の幸せを奪うようなことして偉そうに言わないでよ』
「一応、偉そうには言ってないんだけどなぁ」
『とにかく、あなたは誰?どうして、こんなことができるの?』
「ん?そんなに気になるか?まぁ、教えてやってもいいか、どうせ記憶は無くなるんだから」
『記憶がなくなってもいいから聞きたいの』
祐介がすやすやと寝ているベッドにゆっくりと腰をかけて脚を組んだ。もちろん全裸のままだった。
「そんなに言うなら教えてやるよ。この小瓶には中に入った人物に変身できる効果を持っていて、それを使ってあんたの姿に変身してるんだよ。だから、この身体はあんたの身体のように見えるけど、ただ変身してるってわけ」
『それで、あなたは何者?』
「まぁまぁ。時間はたっぷりあるんだから。あんたの会社にいる田口って知らないかい?」
『えっ?総務課に田口さんっているわ。あなたどうして知ってるの?もしかして、田口さんなの?』
恵美は小瓶の中で目を大きく見開いていた。
「ふっふ〜ん。そうって言いたいけど、今は違うよ。さっきまでは、田口があんたに変身していた」
『えっ。何ですって!?』
「ついさっきまではね。でもって、ちょっと事情があって俺と交代してもらったよ。君の身体にちょっと興味が沸いちゃってね」
『まさか、あなたって田口の親友ね』
「あぁ。そうだよ。俺、真矢直樹があんたの身体に変身してるってわけ」
『信じられない』
そういうと、小瓶の中にいる恵美は一気に力が抜けて気を失ってしまった。すると、恵美はゆっくりとポストイット型のスピーカーを剥がしながら不気味な笑みを浮かべていた。
トイレの中から何事もなかったのような表情で出て来る絵奈。絵奈の姿は周りからみればただの女子高生にしか見えないことでしょう。絵奈は敢えて立ったまま友達が来るのを待っていました。風が吹くと普通はスカートの裾を抑えるのですが、絵奈はそんなこともしないでいます。図書館を出入りする人の目は絵奈に集まっているような気がして、どうやらそれがたまらないようでした。
そんな風に待っているとまずは田島優奈がやって来ました。優奈はちょっとボーイッシュな女の子、小さいときから空手もやっていて、女らしさに少し欠けるところがあります。今日もいつものようにデニムパンツにルーズな着こなしのグリーンのブルゾン姿でした。
優奈は絵奈を見つけると、少し駆け足で近づいて来ました。もちろん、それが本当の絵奈で無いことは知るよしもありません。
「絵奈。なにその格好?今日は土曜日じゃん、学校でも行ってきた?」
優奈は絵奈が制服姿でいることに予定通り疑問を持ちました。
「たまには休みに制服着るのもいいかなって思ってね。今日はプールやってなかってし、なんか気分を変えたくて」
絵奈は優奈に見せるいつもの表情で言って見せた。心の中ではしてやったりと思っていることでしょう。
「まぁ、絵奈らしいな。変わったこと好きだから」
優奈は絵奈を疑うことも無いようだった。どうやら、絵奈がこんなことをするのは別に珍しいことでも無いらしい。
「ところで、奈美はどうしたの?一緒に来なかったの?」
絵奈が優奈に訪ねました。
「あっ。優奈はちょっと遅れてくるって、さっきメール入ってなかった?」
その言葉を聞いてカバンの中から自分の携帯を取り出すと、小窓にメールが入っている証が残っていました。確認してみると奈美からのメールが入っていました。
「さっきトイレに行ってた時にメールが来たから気づかなかったわ。そっか、奈美は少し遅れるのね。残念……」
絵奈は少し首を俯き欠けながら言った。
「そのうち来るんだから、いいじゃん。先に勉強してよう」
優奈はそう言うと絵奈の手首を掴んで先へ行こうとしました。絵奈は仕方なしに優奈について行き、一緒に静まりかえっている静寂な空間へ入って行きました。
---------------------------------------------------------------------------
絵奈が静寂な空間に移動した頃、祐介の部屋には恵美の不気味な笑い声が響いていました。ここには眠っている祐介と小瓶の中に入っている本物の恵美がいます。そして、真矢直樹が変身しちている恵美はその小瓶を右手の親指と人差し指の間に挟んでいました。
「そういえば、あんたに言うのを忘れてたけど、この小瓶は俺がつくったんだよ。他にも色や形の違う小瓶を何本かつくっておいた。それぞれに違った効果を持っている。田口はこれと同じものを1本、違うものを3本持ってるよ。今は祐介の妹、絵奈になって楽しんでるはず」
そこまで言ったところで、恵美の携帯電話にメールが届来ました。宛先は絵奈、つまり田口からのメールでした。それを一気に確認すると、小瓶に向かって再び話しかけました。
「田口は今、図書館にいるって、友達と一緒に勉強会をしているみたいだけど、それが終わったら行動に出るって書いてあるよ。いよいよ新しい小瓶の実験がはじまるってわけよ。新しい小瓶はまだ使ったことが無いから、まずはあいつに試してもらうんだ。どうだい?俺たちのやってることって愉しそうだろう?」
夕暮れ時の部屋の中、薄気味悪い恵美の笑い声には、まだまだ深い謎が隠されているようでした。
ここは図書館、絵奈と優奈が自習室で勉強をしています。これは絵奈の発案によるもので、もう一人の友達である奈美がまだ来ていないので絵奈はちょっと不満でした。なにしろ、絵奈にとっては優奈よりも奈美に興味があったからなのです。
大きな机が開いているのを見つけて絵奈と優奈の二人は向かい合って座っています。一緒に勉強しようと言うことでここに集まりましたが、絵奈はノートの上に俯せになりながら優奈の勉強する様子を眺めています。
優奈が心配そうに絵奈に言いました。もちろん周りに聞こえないくらい小さな声で。
「絵奈。どうかしたの?あんたやる気が無いみたいだけど……」
絵奈はシャープを持った右手を見ながら、優奈に言います。
「奈美がまだ来ないから、なんかやる気無くてね」
「絵奈ったら、私がいるじゃん。試験ももうすぐなんだから、一緒に勉強しようって言ったのは絵奈だったし、なんか嫌な感じ」
「そうだね。優奈がいるんだもの、頑張らないとね。それにしても、試験の範囲広すぎ、試験なんてしばらく受けてなかったから、こんなに大変だったなんて」
「そうだよね。久しぶりだもんね。3年になっての初めての試験だからお互いに頑張ろうよ」
そして、二人は再び勉強を始めました。
---------------------------------------------------------------------------
絵奈と優奈が図書館で勉強をしているその頃、佐伯奈美は二人の待つ図書館へ向かっていました。さっきメールを入れて優奈から返事が返って来たので、二人に連絡がとれてとりあえずは一安心、ゆっくりと図書館に向かっていました。
二人のいる図書館まではあと一駅まで来たところで、人身事故のために電車が遅れてしまったのです。そこで30分も電車が動かなくなったので、結局は遅れて到着することになったのです。
奈美が図書館のある駅に到着して、改札を出ると空はすっかり紅くなっていました。駅に着く前に優奈にメールをしていたので、図書館のホールで待ってもらうことにしました。駅から図書館まではすぐに着きました。図書館の入口から中に入るとホールの中には優奈では無く、絵奈が待っていました。
「待ってたよ。奈美」
出迎えてくれたのはセーラー服姿の絵奈でした。優奈が出て来ると思ったので、ちょっと意外でしたが、絵奈がちょうどトイレに行きたかったので、優奈の替わりにここで出迎えたと言うのです。
絵奈がトイレに行くと言うので奈美も一緒に付いて行くことにしました。二人は女性用トイレに入ると絵奈が一番奥の個室に入り、奈美はその一つ手前の個室に入りました。しばらくすると奈美が水を流して化粧台に向かおうとしたところ、絵奈が小さな声で自分を呼んでいるのです。
絵奈に何かあったのかと思って、奈美は絵奈の入っている個室の戸を開けました。なぜか鍵が掛かっていませんでしたが奈美は不思議だとも思わず、絵奈が俯いたままになっている姿を見つけたのです。
「どうしたの?絵奈。どこか痛いところあるの?」
奈美がそうやって絵奈の上体を起こすと、絵奈はニヤニヤとした表情を浮かべながら何か言って来たのです。
「佐伯奈美ちゃん。どうぞ小瓶の中にお入り下さい」
絵奈が右手に化粧品の試供品を入れているような小瓶を持ちながらそう言うと、奈美は周りのものが次第に大きくなっていくのを感じていました。それと同時に着ているものがするすると体から落ちて行ったのです。
そして、あっと言う間に小瓶の中へ体が吸い込まれてしまったのです。小瓶の中に入った奈美は何が起こったのかわから無い程のできごとでした。周りは全て鏡になっていて、そこには奈美の裸体が映し出されていたのです。
奈美が自分の姿をよく見てみると裸のままでした。周りは鏡ばかりしか無く、そこには裸の姿の自分がいる。外にもでられそうに無いので、絶望に暮れるしかありませんでした。奈美は小瓶の外で行われようとしていることに気づくことも無く、体の力が抜けて座り込むことしかできませんでした。
「絵奈、絵奈。起きてよ。目を覚ましなさいって……」
朦朧とした絵奈の意識がゆっくりと戻って来ると、奈美の声がだんだんと聞こえてきました。意識がはっきりして来ると、ひんやりとした小さな空間にいることにようやく気づいたようです。
ポニーテール姿の奈美がこっちを心配そうに見ています。自分に一体何があったのか、そして、なぜここにいるのか絵奈は思い出そうとしても思い出せません。どうやらここはトイレの1室のようでした。絵奈が目を開けたのを見て、奈美がにっこりと微笑んでいました。
「目が覚めたみたいでよかった。ずっと心配してたんだからね」
上にはスクエアカットの水色のチュニック、黒のデニムのミニフレアスカートと黒のストレッチパンツの重ね着といった姿の奈美が笑顔で絵奈に話かけて来ます。しかし、絵奈は何が起こっているのか状況を把握していないらしいのです。
「私、どうしてここに?ここってトイレじゃない、やっだ〜」
「何言ってるのよ。ここで気絶してたのを私が見つけたんだからね。突然何があったのか驚いたのはこっちの方なんだからね」
記憶を辿ってみるとプールに行くために家を出て、駅に到着してまでの所か思い出せなくなっていた。それに、どこか狭いところにずっと閉じこめられていたように思う。白いワンピースと水色のミュールは制服と黒のローファーに変わっていた。間のことが思い出せないが、自分の意思でこうなったとは思い難いことばかりだった。
「ねぇ、奈美。私、今日の朝までの記憶はあるんだけど、それから全然思い出せないんだ。どうして、ここにいるのか自分でも説明がつかないから」
「ん?そうなの?そんなことってあり得る?」
「あり得る、あり得る。朝に家を出て駅に着いたところ、そうだ!その時もトイレに行ったんだけど、その後から今までの記憶が無いの。いや、正しくはその間の記憶がはっきりしてないって感じかな。ここって図書館だよね」
「図書館に決まってるじゃない。絵奈が呼び出したんだから」
そう言いながら、奈美はちょっとふて腐れるような表情を見せた。
「そっか。やっぱり、覚えている記憶とそうじゃない記憶があるみたい。とにかく、今日の私って変だよね」
「そんな風に見えないって!少しでも一緒に勉強しようよ、外で待ってるから早く来てね」
奈美はそう言い残すとさっさと女子トイレから出て行ってしまった。絵奈は個室から出ると化粧台の大きな鏡に向かって、自分の身に起こった変化をしきりに考えていた。
(一体なんだったんだろう……私の考えすぎなのかな……それとも、これは夢の世界?)
ほっぺたをちょっと捻ってみると痛さを感じる。どうやら夢では無いようでした。
「わかんない!」
思わず頭の中が吹っ切れてしまい、絵奈は大きな声で叫んでしまいました。自分に起こった出来事は覚えていることと覚えていないことが混ざっているようでした。何かに巻き込まれていなければいいけど、そう思いながら絵奈は女子トイレの外で待つ奈美のもとへと向かいました。
絵奈は奈美の待っている女子トイレの前にに出て行きました。
「絵奈。大丈夫?」
「うん。もう、大丈夫。わかんないことはたくさんあるんだけど、あとで家に帰ってから考えることにするから」
「それならいいけど、私が助けられることがあればすぐに相談にのるから」
「ありがとう、奈美。このこと優奈には黙っていてね。優奈がこんなことを知ったらとっても口うるさいんだから」
「わかってるって。」
「優奈が待ってるはずよね。早く行きましょ」
自習室に二人が行くと、そこには優奈が退屈そうに待っていました。二人を見るなり口が開きます。
「いつまで待たせてくれるの。心配しちゃうでしょ。トイレに行くだけなのにずいぶん長かったね。絵奈」
「うん。ごめんね。優奈。ちょっとお腹の調子が悪くて、奈美も待たせちゃった。さっきの続きを勉強しよう」
「優奈。私が遅れたせいもあるんだから、許してあげてよ。絵奈は全然悪くないんだから」
「わかった。早く席についてよ。奈美に聞きたいことがあるんだ」
優奈がそう言うと3人は静かに勉強を始めました。
---------------------------------------------------------------------------
3人が勉強を始めた頃、外はすっかりと暗くなっていました。祐介の部屋にいる恵美のそばで、祐介は未だに寝ていました。恵美は小瓶の中に入った恵美と話すのにも疲れ、そろそろ新しいことをはじめようと思ったのです。夜になれば絵奈が戻ってくるはず、そして、田口のことだからその時の絵奈は本物の絵奈に戻っているはず。そう考えました。
(田口が絵奈の友達になっているとすれば、それは奈美なはず。田口の奴がうまくやってるか見に行かないとな)
恵美は恵美の携帯電話を取り出すと、文恵に電話をかけはじめた。そして、電話のベルが何回も鳴り続けてからようやくのことで文恵が電話に出た。
『恵美?どうしたの?』
「あっ、文恵やっと出たね。ちゃんと家に帰ったのかなと思ってね」
『うん。家に帰って来たわよ。昨日は恵美の家で寝ていたせいか、ちょっと疲れていてね。寝ていたところよ』
「そっか。せっかく、彼の部屋に来たのに彼が疲れたのか寝ちゃってね。そろそろ帰ろうと思うの。今日は私が文恵の家に行ってもいいかな」
『そうだね。これから晩ご飯の支度をしようと思っていて、一人じゃなんだから来ていいよ。恵美は何か食べたいものある?』
「文恵がつくるんだったら何でもいいわよ。じゃあ、家の近くまで行ったらメールするわね」
『うん。待ってるね』
文恵がそういうと電話を切った。本物の恵美が入っている小瓶を恵美のバッグの中に入れると恵美は祐介の揺さぶって起こした。祐介は寝ぼけたような表情で恵美の方を向いた。
「あれっ?俺って寝てたの。ごめんな。一人で退屈させただろう」
「寝顔が可愛かったからね。起こすのも悪いなって寝かせてあげたの。あなたが寝ても一人じゃなかったから退屈じゃなかったし」
「そうか、これから何する?」
「祐介。あのね、今日はこの辺で家に帰ろうと思うの、昨日私の友達と会ったでしょう。彼女の家で晩ご飯を食べることにしたから」
「うちで食べていけばいいのに」
「まだ、私たち早いわよ。それに友達と話したいことがあるから」
「わかったよ。次はいつ会う?」
「そうねぇ。会いたくなったらメールか電話して」
「うん。わかった」
祐介と話しながら恵美は帰りの準備を終え、祐介の部屋を出ようとした。
「玄関までは送っていくよ」
祐介と恵美は階段を下りて行った。
「今日はありがとう、楽しかったよ」
「うん、私も。色々とありがとうね」
「こちらこそ」
「あっ。絵奈ちゃんによろしく言っておいてね。今度また遊ぼうって」
「おい。俺よりも絵奈の方がいいのかよ」
「女同士だもの、時にはいいでしょ」
きれいに揃えてあった白いハイヒールに足を入れると、玄関の扉を開けた。五十嵐家の番犬であるラブが恵美の方を向いて吠えてくる。
「まだ吠えられてる。私のこと警戒してるのかしら」
「大丈夫。何度もここに来たらそのうち慣れると思うから」
「それも、そうね。じゃあ、また」
祐介はサンダル姿で玄関の扉越しにいた。恵美はその祐介の頬に軽くキスをすると祐介の家を後にした。文恵の家に向かい始めたが、キスをした時の感触がなかなか消えることは無かった。
祐介の家を後にした恵美は文恵の家に向かっていました。もちろん、本物の恵美はバッグの中に入れてある小瓶の中に入っています。しかし、周りから見ると誰もが女性が歩いているものと思うしかないでしょう。
すっかり薄暗くなって、駅までの道は街頭が無ければ見えないほどでした。駅までの道筋で周りの視線を感じていたが、それがどことなく心地よかったのです。駅に着くとバッグの中からカードを取り出し、改札口に入れようとした時、恵美にある考えが浮かびました。
(そうだ。図書館に立ち寄ってみよう……)
そう、絵奈たちがいるはずの図書館に寄ってみようと思ったのです。もちろん、田口の奴も一緒にいるはず。そう考えると恵美は方向を変えて図書館へ向かうことにしました。改札口の前まで来ていたので、後ろを振り向くとサラリーマン風の男が恵美にぶつかって来ました。
「あっ」
ぶつかった衝撃で恵美は倒れそうになりましたが、その男の人が背中を押さえてくれて助かりました。
「どうも、済みませんでした」
お詫びをしながら、恵美はその男の顔を見ると、祐介よりちょっと年のいった感じの青年が立っていました。
「気をつけてくださいね。僕は急いでるので、これで」
そう言ってその男は改札口をくぐり抜けて行きました。そして、彼の後ろ姿を見る間も無く、恵美は図書館へ向かうことにしました。
少し歩くと図書館に到着。ここで勉強をしているはずなので、図書館の中にある自習室へ入ってみました。ぐるっと見回してみると高校生ぐらいの人たちが静かに勉強をしている光景が広がっていました。
その一角に見たことのある顔を見つけました。そうです。絵奈たちがいる座席を見つけたのです。どうやらみんなで熱心に勉強しているので、恵美がここに来たことを分かっていないようです。
恵美がゆっくりと歩いて近づくと、絵奈が顔を上げた瞬間に恵美に気づきました。そして、絵奈が手招きするのを見て奈美も恵美が近づいていることに気づいたのです。恵美は初対面になるはずの奈美の動きを見て、もしやと思いながら3人のもとに到着したのです。
3人のもとに到着した恵美と目があった絵奈は、椅子に座ったままなんだか複雑な表情をみせています。恵美とは前にあったような記憶だけが曖昧な状態で思い出されたからです。絵奈は恵美との関係を頭の中では理解できるのですが、会ったことはあまり無かったように思うのです。とにかく、恵美が絵奈の兄とつきあっていることだけは確かにわかってるようでした。
恵美は絵奈の隣の席にワンピースの裾を気にしながら座ると、絵奈は恵美を目の前に座る優奈と奈美に紹介しました。
「えっと、こちらは兄の恋人で恵美さんって言います。私とも親しいんですよね?」
曖昧な記憶はもちろん小瓶の影響によるものです。初めて会ったような気もするのに、前にちゃんと会ったという記憶もあって、それが複雑な表情をさせていたのです。優奈と奈美も一人づつ、恵美に紹介をしました。
「絵奈の友達で、優奈です」
「奈美で〜す」
奈美は愛嬌をいっぱい付け加えて、恵美の方を見ながら軽く舌を出しました。それを見た恵美はどうやら何かに気づいたようです。恵美は隣に座っている絵奈に話をはじめました。
「さっき、帰ることにしたんだけど、祐介を一人だけ残して来たんで、早く帰った方がいいんじゃないかなって思ってね。それだけ言おうと思ってここに来ただけ。じゃあ、私行くわね」
そう言うと、恵美は静かに自習室から出て行きました。残されてまた3人になると、絵奈が思い詰めたような表情でつぶやきます。
「お兄ちゃんが一人だけだったら、ちょっと心配だなぁ。そろそろ帰った方がいいかな、優奈、奈美。私もう帰ろうと思うんだけど……いいかな?」
最初に返事をしたのは優奈の方でした。
「もう夜も遅くなって来たしね。そうしよっか」
「えっ?もう帰るの?私はまだちょっとしか勉強できなかったのに……後から、来たからしょうがないっかぁ。私もいいよ」
外はもう真っ暗、どうやら3人は家に帰ることに決めたようです。3人はテーブルの上を片づけて、勉強道具をカバンの中にしまい込みます。
3人で一緒に図書館の側にある駅まで歩いて行くと、奈美は一人改札口を通って行きました。絵奈と優奈は同じ駅の近くに住んでいても、奈美の家だけはちょっと離れた場所にあるのです。改札をくぐった奈美がホームで電車を待つことにすると、背後から何かが近づく気配を感じたのです。
|